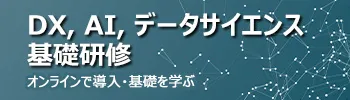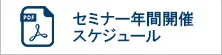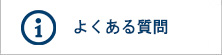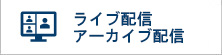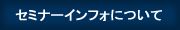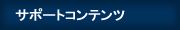|
|
 |
セミナー情報
SEMINAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報
過去に開催したセミナー5855 件中 3601 ~ 3800件を表示します |
| 開催日時 | 2012-04-24(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関の顧客獲得マーケティング ~ SNS・ソーシャル時代の新たな顧客戦略 ~ |
| 講師 | 株式会社アサツーディ・ケイ 価値創造プランニング本部 シニアプランニングディレクター ADK金融プロジェクト 兼務 橋本 之克 氏 デジタルビジネス本部 第1デジタル業推室 室長 埴原 武 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,900円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-04-23(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 投資運用業、投資助言業に対する規制・監督方針の変更と対応のポイント |
| 講師 | 東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,100円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-04-19(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 反社対応にかかる態勢整備等の取組みのポイント |
| 講師 | 金融庁 監督局 総務課 課長補佐 國吉 雅男 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 17,850円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-04-13(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 決済ビジネスの最新動向と今後の展望 |
| 講師 | 株式会社 野村総合研究所 金融・資産運用ソリューション事業本部 金融ソリューション事業二部 上級コンサルタント 宮居 雅宣 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,800円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-04-12(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 住宅ローン収益性評価からリテール事業戦略高度化へ |
| 講師 | 株式会社三菱総合研究所 金融ソリューション本部 副本部長 市川 智 氏 主任研究員 河内 善弘 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,600円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-04-12(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 不動産投資スキームの最新実務課題と法的留意点 近時の法改正により可能となるスキームほか法的・実務的諸問題と新たな潮流 |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 本田 圭 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 我が国の不動産マーケットは、J-REITによる新規物件取得が増えてきていること、海外投資家/海外不動産ファンドによる日本の不動産に対する投資も散見されることなどから、リーマンショック後の長い低迷期を脱し、再び活発化する兆しが見えてきていると思われる。このような状況において、2011年には資産の流動化に関する法律(SPC法)及び金融商品取引法(金商法)が改正され、不動産証券化案件における投資家(特に、海外投資家/海外不動産ファンド)にとってより使いやすい環境が整備されてきた。 本講演では、2011年11月に施行された改正SPC法の内容と「TMK-GKスキーム」などの不動産ファンドスキーム等の新しい可能性、また、2012年の施行を目前に、プロ向け投資運用業の創設等が注目される改正金商法の内容を踏まえ、新たに可能となった不動産投資スキーム/不動産ファンドスキームについて、従前のスキームとの比較をしながら解説するとともに、スキーム組成における法的留意点について、具体的な事例を想定しながら解説する。また、エネルギー政策の転換による不動産投資スキームへの影響として、11年に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」と太陽光発電等に係る設備のための用地取得における証券化/流動化手法の利用の可能性、2011年から開始されている東京都環境確保条例に基づく排出量取引の影響等についても解説する。 |
| 開催日時 | 2012-04-11(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険代理店に対する監査の着眼点と監査手法の考察 ~監査を通じた保険会社における保険代理店管理のポイント~ |
| 講師 | のぞみ総合法律事務所 番匠 史人 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,600円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-04-11(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 欧州債務危機等を念頭に置いた今後のリスク管理と統合的ストレステスト マクロ経済予測シナリオの活用、信用リスクと市場リスクの同一シナリオに基づくストレスシミュレーションの実践的手法 |
| 講師 | NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社 取締役COO 杉本 好正 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | ユーロ危機、円高、東日本大震災、原発事故と想定外の事態が発生するなか先行きの不透明感が増しており、金融機関等においては過去の統計的なデータや経験知に過度に捉われず、様々な事態を想定したフォワードルッキング的な視点での統合的リスク管理が求められている。 金融機関のリスク管理は、バーゼルⅡ規制の影響もあり、従来は過去の実績に基づく確率からそのリスクの発生度合いや影響を推定するアプローチが主流であったが、極めて発生確率が低い複合的なリスクやスパイラルに伝播していくリスクに対しては過小評価するきらいがあり、想定より大きな損失を被る例が少なくない。 ストレステストの手法は、これまで信用リスクと市場リスク、貸出と有価証券、リスク特性や形態ごとに個別にシナリオを設定し、それらが同時に行った場合のリスク量を合算するアプローチを一般に採用してきたが、今後は内外のマクロ経済の先行きに留意し、様々なリスクシナリオのもとで、同時に発生する事態の想定やリスク連鎖の時間軸の妥当性、期間損益や自己資本比率への影響度などを定期的に検証し、適切な経営判断につなげていくことがより重要となってくる。 本講演では、欧米の金融当局が取り組んでいる共通ストレステストの内容やストレステストの目的・意義について解説するとともに、マクロ経済予測モデルを用いて、さまざまなリスクシナリオの下での主要国のマクロ経済指標や金利、為替、株価等の市況の先行きを予想し、金融機関等が保有する運用資産の信用リスクや市場リスクに与える影響度の測定方法の事例を交えながら、統合的ストレステストの高度化の方向性を考察する。 |
| 開催日時 | 2012-04-10(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 新犯罪収益移転防止法が金融実務に与える影響 |
| 講師 | 尾高・浅井国際法律事務所 浅井 弘章 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,800円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-04-10(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】企業税務の基礎 キャッシュフローへの影響を念頭に、投融資やグループ戦略等の実務に必須の知識を基本から解説 |
| 講師 | 並木安生公認会計士・税理士事務所 公認会計士 税理士 並木 安生 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 企業のキャッシュフロー経営に影響を及ぼすものとして税金は大きなファクターであり、自社の財務はもとより、投融資先のキャッシュフローを把握するうえでも税務に対する的確な理解は極めて重要であるが、経理・税務部門以外の実務家にとって税務知識を基本から体系的に学習する機会は少ない。 本講義は、商社ほか事業法人において事業投資やグループ戦略に関与する実務家、また、投融資ほか実務に携わる金融機関の実務家など、必ずしも経理・税務を専門としない実務家や役職者をも対象に、企業税務の知識を基礎から簡潔に、かつ、ケーススタディ等を交えて具体的に解説するものである。 M&A実務ほか会計・税務実務に精通する講師の立場から、投融資先の経営状態の分析やグループ戦略の検討などの実務における必須知識として、法人税に係る一般税務、国際税務、グループ法人税制(連結納税を含む)、M&A税務等について基本から平易に説明するとともに、これらの税目が企業のキャッシュフローに与える影響も併せて解説する。また、実務上の留意点についてケーススタディを通じて具体的かつ実践的な理解を図る。 |
| 開催日時 | 2012-04-06(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社・代理店のウェブ・モバイル戦略とコンプライアンス上の重要ポイント |
| 講師 | 尾高・浅井国際法律事務所 浅井 弘章 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-04-06(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | バーゼルⅢの最新動向及び論点と今後への影響 金融庁告示改正案などを踏まえて |
| 講師 | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ パートナー 桑原 大祐 氏 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー 公認会計士 関田 健治 氏 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアスタッフ 公認会計士 飯野 直也 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | リーマンショックに端を発する世界的金融危機の教訓を踏まえ、国際的に活動する銀行に対する新たな規制についてバーゼル銀行監督委員会において議論され、2010年12月17日にバーゼルⅢテキストとして国際合意の内容が公表された。これを受け、我が国においても、2013年3月31日のバーゼルⅢ国内適用開始に向けて、2012年2月7日に自己資本比率規制に関する金融庁告示の改正案が公表されるに至った。 本講演では、まずバーゼルⅢ導入の経緯や構成などのバーゼルⅢの概要を確認したうえ、バーゼルⅢの各個別論点について、金融庁告示改正案も踏まえ、今後の実務等への影響も念頭に解説を行う。個別論点に関しては、告示の改正案が公表されている分野については、当該告示の改正案を踏まえて解説し、告示の改正案に含まれていない分野(レバレッジ比率、流動性規制)については、バーゼルⅢテキストに基づいて解説することとする。なお、2月7日に公表された金融庁告示改正案は3月7日までパブリックコメントに付されているところ(2月14日現在)、講演当日までに改正後の告示が公表された場合など、最新の情報については必要に応じ、可能な範囲で反映させることとする。 |
| 開催日時 | 2012-04-05(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社におけるシステムリスク管理の課題と対応策 |
| 講師 | 有限責任監査法人トーマツ パートナー 福島 雅宏 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,000円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-04-04(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 投資信託の販売・勧誘における実務上の留意点 ~乗換え勧誘・検査・金融ADRを踏まえて~ |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 (元)金融庁・証券取引等監視委員会事務局証券検査課 課長補佐、専門検査官 鈴木 正人 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,400円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-03-29(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社の経営戦略・販売戦略研究 ~新たな消費者動向・顧客接点、欧米保険会社の経営モデルを踏まえて~ |
| 講師 | ナカザキ・アンド・カンパニー 保険ジャーナリスト 中崎 章夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,700円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-03-28(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | オリックスの金融戦略研究 ~総合金融グループの質的転換と戦略オプション~ |
| 講師 | 経営企画研究所 代表 丹羽 哲夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-03-27(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 不動産関連金融商品取引業者の検査対応 ~検査受検に備えて今確認すべき事項~ |
| 講師 | 有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー 東野 淳二 氏 スタッフ 野本 和宏 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,000円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-03-27(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関における内部監査の高度化を巡る最新の潮流と具体的手法等 個別監査の実施及び経営陣への報告における実務上のポイント、先進事例等を交えて |
| 講師 | あらた監査法人 リスク・コントロール・ソリューション部 ディレクター 公認会計士 駒井 昌宏 氏 あらた監査法人 リスク・コントロール・ソリューション部 マネージャー 高谷 健太郎 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 金融機関における内部監査を巡っては、2011年12月2日、バーゼル銀行監督委員会が市中協議文書「銀行の内部監査機能」(The internal audit function in banks)を公表するなど、その強力な機能の発揮が求められている。金融機関を取り巻く情勢を踏まえて実効性のある内部監査を実施し、組織に付加価値を提供するために内部監査機能の品質を継続的に向上させていくことはますます重要な課題となるといえよう。 本講演では先ず、国内外の先駆的な取組み等に対するPwCのグローバル調査結果等から明らかになった内部監査の成功要因及び最新の規制環境等を題材として、金融機関における内部監査の高度化を取り巻く環境及び今後目指すべき方向性を解説する。そのうえで、専門家として多数の金融機関の内部監査実務を支援する講師らの視点から、主に個別監査の実施及び経営陣への報告において留意すべきポイントについて、国内外の金融機関における事例に基づき、各種手法を具体的かつ実践的に解説することとする。 |
| 開催日時 | 2012-03-23(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社のグループ経営と今後の規制の方向性 ~金融審議会保険WGでの議論をふまえて~ |
| 講師 | 株式会社 日本格付研究所 金融格付部 チーフアナリスト (兼)格付企画部長 金融審議会「保険会社のグループ経営に関する規制の在り方WG」メンバー 水口 啓子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 36,100円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-03-22(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 消費者保護と集合訴訟制度を巡る動向及びポイントと金融機関への影響 「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」、法案提出へ向けた最新の動き等を踏まえて |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 足立 格 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成23年12月、消費者庁より、「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」が公表され、同月9日から28日までパブリックコメント手続に付された。この骨子は、平成23年8月26日に公表された集団的消費者被害救済制度専門調査会報告書を踏まえたものであり、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度(新訴訟制度)については、平成24年通常国会への法案提出が予定されている(平成24年1月16日現在)。 新訴訟制度は、被害を受けた消費者が自ら訴えを提起して被害の回復を図ることを断念しがちと言われている集団的な消費者被害を幅広く回復することを目指すものである。新訴訟制度においては、手続を二段階に分ける等の独自の仕組みが予定されており、また、消費者との取引を行っている企業であれば新訴訟制度の対象となりうる。当然ながら、リテールビジネスを行う金融機関も例外ではなく、新訴訟制度のポイントを把握しておく必要があろう。 本講演は、ともすれば理解が難しい新訴訟制度につき、金融機関にとってのポイントと留意事項も含め、具体的に分かり易く解説することを目的とする。なお、講演当日までに、「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」に対するパブリックコメントへの消費者庁の回答や新訴訟制度に係る法案が公表されていた場合には、状況に応じ、可能な限り反映することとする。 |
| 開催日時 | 2012-03-15(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社における次世代資産運用リスク計測モデル ~経済シナリオジェネレーター(ESG)を踏まえて~ |
| 講師 | PwC Japan あらた監査法人 シニアマネージャー 西原 立 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,700円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-03-14(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融ADR事例を踏まえた金融機関の態勢整備上の留意点と実務対応 |
| 講師 | のぞみ総合法律事務所 吉田 桂公 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,900円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-03-14(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 中国投資を巡る最新トピックのアップデートと実務への影響 グループ内資金管理、VIEスキーム、人民元建て資金調達・投資を中心として |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 中倫律師事務所出向中 若江 悠 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演では、中国投資に関し、特に投資性公司を用いたグループ内資金管理、VIEスキーム、人民元建て対内直接投資といった最新のトピックを中心に解説する。中国の証券、外貨管理、外商投資、オフショア投資といった分野は、複雑な規制がつねに大きく変化しているうえに、実務上の扱いや対応については正確な情報の取得が困難である。キャピタルマーケッツの業務に主に従事した後、中国北京の現地律師事務所に長期出向中の講師が、日々実際の案件及び同僚中国弁護士との共同作業・交流を通じて知り得た最新の実務動向を共有する。 既に中国投資を行ってきた日本ほか外資系企業等にとって、個別の新規設立や買収もさることながら、設立した中国拠点の効率的な管理・運用が大きな課題となっている。投資性公司制度は、外貨管理等の厳格な規制に服している外資系企業が効率的なグループ経営を実現するために制定された制度であるはずだが、2011年、当局の制度(解釈?)変更(国家外貨管理局資本項目管理司「外商投資性公司の再投資に関係する験資確認関連問題の操作手引きに関する通知」匯資函[2011]7号)により、実務に大きな混乱が生じた。この点を切り口として採り上げ、中国におけるグループ内資金管理に関連する検討を行う。 2011年、アメリカ上場中国企業の会計不正疑惑とアリペイ(支付宝)の株式譲渡問題を契機に、海外上場する中国企業の多くが用いてきたVIEスキーム(Variable Interest Entities、外国法人が中国事業法人を契約により支配する仕組み)が注目を浴びた。同スキームには、当初からその合法性、執行可能性やガバナンスの問題は懸念されていたものの、中国を代表するネット企業が次々にこれを用いてNASDAQ等の海外市場で上場し、その際は中国の律師事務所による意見書を取得する実務が浸透していた。しかし、上記事件を契機に、中国政府内部で同スキームに対し批判的な意見が表明され、さらに商務部が「外国投資家による国内企業の合併・買収に係る安全審査制度の実施に関する規定」(商務部公告2011年第53号)において同スキームを用いた買収も安全審査の対象に含める旨規定したことから、VIEスキームの今後について不安が高まった。中国企業に対する投資、またはVIEスキーム類似の契約によるコントロールを用いた投資といった局面に影響があり、その最新の議論を紹介する。 人民元の国際化も2011年に大きく進展した。人民元建ての貿易決済の試験実施が拡大しその実績が積み上がるとともに、香港オフショア市場におけるディムサム債について日本企業による複数の発行例もみられている。それらオフショアで外国企業が取得した人民元の中国境内投資についても関連規則(商務部「クロスボーダー人民元直接投資関連問題に関する通知」(商資函[2011]第889号)等)が公表され、早速許認可実務が始まっている。同制度の動向や実務上の注意点を紹介するとともに、今後中国国内で直接資金調達を行うことの可能性についても触れる。 最後に、中国企業との資本提携に基づく中国市場への進出について、講師の実務上の経験も踏まえて注意点を述べることとする。 |
| 開催日時 | 2012-03-13(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 国際保険規制の最新動向と保険会社オペレーショナルリスク管理態勢高度化 ~先進的プラクティスと計量化態勢の構築実務~ |
| 講師 | <Ernst&Young> 新日本有限責任監査法人 金融アドバイザリー部 エグゼクティブ・ディレクター 出塚 亨一 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,900円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-03-12(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関におけるスマートフォンとSNSの活用戦略 ~マルチチャネル環境におけるクロス・メディア戦略の実現~ |
| 講師 | 株式会社日立コンサルティング 金融本部 シニア・ディレクター 長 稔也 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,300円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-03-09(金) 13:30~16:00 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社のマーケティング戦略 ~ロイヤルティ・マーケティングの時代~ |
| 講師 | ベイン・アンド・カンパニー パートナー 金融プラクティスグループリーダー 長谷部 智也 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,100円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-03-08(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 会社法の改正と金融業界への影響 ~法制審議会・中間試案を踏まえた実務的解説~ |
| 講師 | 中央大学法科大学院 教 授 森・濱田松本法律事務所 客員弁護士 野村 修也 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,500円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-03-08(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ストレステスト実施の手法とインパクト計測の実務 欧州危機や金融規制強化の潮流を念頭に、実践的インパクト計測や実務動向等について事例を交えて解説 |
| 講師 | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ マネジャー 岡崎 貫治 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演はストレステストを巡る最新の実務動向を踏まえたうえ、その実施手法について、また、特にインパクト計測について事例を交え、実践的に解説するものである。 欧州ソブリン問題や金融規制強化の潮流が色濃く残るなか、引き続き2012年も銀行、保険会社、証券会社ほか金融機関、また、商社ほか事業法人にとってストレステストは経営面、実務面の極めて重い課題となろう。世界的金融危機がValue at Risk(VaR)やスコアリング・モデルなどの特定の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにしたが、近時、その反省も踏まえて、様々なストレス事象を包括的に取り込むことができる、ストレステストへの関心はますます高まっている。 本講演では、ストレスステストの最新実務動向及び実施手法の整理について述べたうえ、インパクト計測における実務上の課題を指摘し、どのように計測すべきなのかを事例を交えて考察する。今後の中長期にわたるストレステストの継続的な運用とリスク管理におけるコミュニケーションツールとなるよう、実務家の目線に配慮した解説を行うこととする。 |
| 開催日時 | 2012-03-07(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 企業不祥事対応とコンプライアンス確保の具体的方法 ~オリンパス事件等を題材にして~ |
| 講師 | サン綜合法律事務所 元東京地検特捜部長 大鶴 基成 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,300円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-03-07(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | M&Aファイナンスの実務と法的諸論点 最新の実務も踏まえて、ローン取引や担保取引の問題点など |
| 講師 | 東京青山・青木・狛法律事務所 谷笹 孝史 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | リーマンショック以降、我が国のM&A市場は縮小を余儀なくされていたが、近時M&A市場が急速に回復しつつあり、マネジメントバイアウト(MBO)や日本企業による海外企業のM&A(いわゆるIN-OUT案件)を中心として、案件数も増加している。M&A案件の増加により、M&Aファイナンスの利用も急速に増加しており、この傾向は今後も続くことが予想されている。一方、M&Aファイナンスは、一般的なローン取引には見られない様々な特徴を有しており、また、まさに日進月歩の分野であることから、常に最新の実務に触れていることが重要である。 そこで、本講演では、M&Aストラクチャーにつき簡単に確認したうえ、M&Aファイナンスに関する諸論点として、MBO、海外企業買収、フィーの問題や最新判例などをとりあげ、また、ローン取引・担保取引に関する問題点について、最新の実務を踏まえて解説を行うこととする。 |
| 開催日時 | 2012-03-06(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | Facebookのマーケティング活用 |
| 講師 | 株式会社野村総合研究所 システムコンサルティング事業本部 ビジネスオペレーションコンサルティング部 シニア研究員 山崎 秀夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,700円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-03-06(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険募集の委託・再委託に関する留意点と実務対応 「保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループ」報告書も踏まえて |
| 講師 | のぞみ総合法律事務所 吉田 桂公 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は、保険募集の委託・再委託に焦点を当て、関連法規制や実務上の課題に加え、最新の議論も交えて、留意点と実務対応に関する解説を行うものである。 従前、保険募集の再委託は、保険会社の監督が及びにくいとの懸念から規制がなされてきたが、平成23年6月から始まった金融審議会「保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループ」において、保険募集の再委託等に関する検討・審議がなされ、同年12月7日、同ワーキング・グループの報告書が公表された。この報告書の中では、同一グループの保険会社を再委託者とする保険募集について、一定の条件のもとで、再委託が許容されるとの検討結果がとりまとめられているが、それ以外の再委託については、未だ規制下にある。 保険の販売チャネルとしては、保険会社、保険代理店、保険仲立人があるが、「保険募集」の定義・範囲が必ずしも明確でないこともあり、それぞれの間の委託・再委託の適法性について疑義が生じることも少なくない。 本講演では、関連法規制、さらには、上記のワーキング・グループにおける議論も踏まえつつ、保険募集の委託・再委託に関する留意点と実務対応について検討する。 |
| 開催日時 | 2012-03-02(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】店頭デリバティブ取引の基礎と実務上の留意点 基本契約や担保契約のドキュメンテーションから近時の進展まで |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 仲田 信平 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講義は、店頭デリバティブ取引に係る実務の必須知識につき、豊富な経験を有する講師の立場から実務に即し、かつ、わかりやすく解説するものである。 店頭デリバティブ取引は、取引の期間中、常にその時価評価額が原資産の価格等に基づいて変化し、取引の相手方に対する信用リスクの管理についてもかかる観点からの対応が求められる点に特徴がある。 こうした特徴から、店頭デリバティブ取引に用いられる基本契約や担保契約は、ローン契約や抵当権設定契約といった他の金融取引において用いられる契約よりも技術的かつ複雑で、店頭デリバティブの業務に携わる実務家にとっては、店頭デリバティブ契約のドラフトや交渉において、「なぜ当該事項が問題となるのか」「契約上の当該規定がどのような意味を持つのか」「交渉にあたり特に留意すべき点は何か」といった疑問を感じるケースが多い。 そこで、本講義は、こうした「なぜ」に応えるため、店頭デリバティブ取引における「エクスポージャー(=時価評価額)」や「信用リスクの管理」の概念、さらに近時の店頭デリバティブ取引の早期終了のケースにおける処理の概要を簡潔に説明し、ともすれば技術的で無味乾燥と感じられるデリバティブ取引の基本契約及び担保契約の重要な規定につき、縦断的な視点を提供し、分かりやすく解説することを目的とする。 さらに、金融ADRに基づく店頭デリバティブ取引に関する紛争処理の状況、店頭デリバティブに係る清算機関の設置、さらにスタンダードCSAに関する状況等、実務家として理解しておくべき重要な近時の進展につき、紹介する。 |
| 開催日時 | 2012-03-01(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | モバイルテクノロジーの国内外最新導入事例 ~金融機関における活用のポイント~ |
| 講師 | プライスウォーターハウスクーパース株式会社 シニア マネージャー 西口 英俊 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,000円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-02-29(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 住宅ローン市場の最新動向と今後の展望 |
| 講師 | 住宅金融支援機構 住宅総合調査室 主席研究員 横谷 好 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,100円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-02-29(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 海外プロジェクトファイナンスの契約を巡る諸論点 重要性の高まるエネルギー関連案件等を念頭に、近時の実務を踏まえて |
| 講師 | レイサムアンドワトキンス外国法共同事業法律事務所 パートナー 小林 広樹 弁護士 レイサム アンド ワトキンス外国法共同事業法律事務所 パートナー 外国法事務弁護士(指定法・カリフォルニア州法、原資格国法・ハワイ州法) マイケル・ヨシイ 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 欧州金融危機の懸念の高まりと米国の景気低迷を背景に、世界貿易量の伸びは鈍化し始め、金融取引にも不透明感が漂うなか、プロジェクト開発の分野は引き続き活況を呈している。とりわけ、人口増加・経済成長の持続を受けて世界全体のエネルギー需要は今後30年で30%以上の増加が見込まれ、米国のシェールガス開発を含めた石油・天然ガスプロジェクトや、地熱・風力・太陽光など再生可能エネルギーのプロジェクト、途上国での電力開発プロジェクトといったエネルギー関連プロジェクトは、案件数・規模ともに拡大している。特に、東日本大震災と原子力発電所事故を経験した我が国にとって、天然ガスの確保は重要な課題となっており、日本企業による海外天然ガスプロジェクト開発やそのための権益取得の動きが急速に進んでいる。このように拡大するプロジェクト開発のための資金調達を、開発企業の信用力に依拠して行うことはますます困難になっている。 開発企業の信用力に依拠しない資金調達手法としてのプロジェクトファイナンスは、プロジェクトから発生するキャッシュフローに依拠し、プロジェクトに伴うリスクを関係当事者間で分配して負担する仕組みにその本質がある。エネルギー関連プロジェクト等の活況を含む最新の状況からプロジェクトファイナンスに対する期待感と重要度がますます高まるなか、その本質を的確に理解し、今後拡大する案件に臨んでいくことは引き続き焦眉の課題であるといえよう。 本講演においては、当分野における豊富な実績を有し、最前線の実務に関与する講師らの立場から、プロジェクトファイナンスを構成する諸契約の、かかるリスク分配のツールとしての機能を手掛かりに、近時の実務を踏まえて留意点等を解説する。 |
| 開催日時 | 2012-02-27(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | バーゼルIIIと最新デリバティブ市場動向 |
| 講師 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 カウンターパーティー・ポートフォリオ・マネジメント部長 富安 弘毅 氏 債券統括本部 ポートフォリオ戦略部 ヴァイスプレジデント 大石 佳敬 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,700円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-02-27(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社における外部委託・グループ内委託管理の重要ポイント |
| 講師 | 尾高・浅井国際法律事務所 浅井 弘章 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,500円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-02-24(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 近時の事案等にみる会計不正ほか企業不祥事の法規制上のリスクや対応 オリンパス、九州電力等の最近の企業不祥事事例を参考に |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 垰 尚義 弁護士 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 若林 剛 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 2011年は、オリンパス、九州電力等の企業不祥事が大きな問題となり、わが国企業及び市場に対する国際的信認をも揺るがしかねない事態へと拡大した。これら事案を含め、会計不祥事のほか、製品事故、インサイダ-取引等を含む企業不祥事は後を絶たず、一方で、会計不正を例にとれば開示書類の不提出や虚偽記載を原因とする開示規制違反などのリスクは増大し、法規制の厳格化等に伴う上場廃止、課徴金納付命令、損害賠償請求等に晒される懸念は高まっているといえる。 本講演では、先ず2011年12月6日に公表されたオリンパスの第三者委員会調査報告書のほか、九州電力、その他の事例について専門家としての講師らの立場から客観的かつ詳細な分析、検討を行うとともに、企業不祥事に対する法規制を確認し、不祥事が発生した企業に生じる事態とリスクについて、責任追及等の視点も交えて解説する。また、海外子会社の不祥事事案等も念頭に置き、不祥事の防止策や発生・発覚時の対応等にも言及する。 |
| 開催日時 | 2012-02-23(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 投資運用業、投資助言業者に対する規制・監督の動向と有効な対応策 各種ファンド運用業への検査、最新の監督規制の変更を含めて |
| 講師 | 東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 投資運用業、投資助言代理業を巡っては、最近の監督規制において注目すべき改正案が公表されたほか、私募ファンド運用会社に対する検査の動きがみられるなど、今後の業務運営にも相当の影響が考えられる。 本講演では、平成23事務年度金融商品取引業者等向け監督方針、平成23年度証券検査基本方針その他の最新の動向を踏まえ、投資運用業、投資助言業者に対する当局の姿勢、ポイントなどを確認しながら、各業態で重点的に対応すべき課題について実務対応の視点から解説する。 |
| 開催日時 | 2012-02-21(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 外部委託先管理を巡る近時の課題やその変化等と実務対応 リスクアセスメントやモニタリングを含む管理プロセスの重要性と対応策、情報管理からクラウドコンピューティングほか新たなトピックまで |
| 講師 | デロイトトーマツリスクサービス株式会社 執行役員 野見山 雅史 氏 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー 田宮 秀樹 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 金融庁発出の平成23検査事務年度検査基本方針においても、外部委託先管理については引き続き挙げられており、的確な業務遂行状況を検証することが明記されている。金融機関にとって、業務の外部委託は避けられないものになっているが、コスト削減などのメリットの享受が先行し、その裏側に潜む外部委託リスクや管理手法の整備への対応はいまだ十分とはいいがたい。 こうした近年の当局の姿勢の厳格化などの動向と相俟って、金融機関内部における問題意識も高まる一方で、最前線において実務を支援する講師らの実感からは、委託先選定時の評価等に留まらず、委託品質の管理を含むモニタリングあるいはリスクアセスメント等へも現実的な課題は変遷、拡大がみられている。クラウドコンピューティングなどの新たな潮流をも見据え、当局動向とともに最先端の実務動向を把握したうえで解決策を模索していくことが極めて重要であろう。 本講演では、実務上、課題の多い委託先管理プロセスや内部監査などをとりあげるとともに、顧客情報管理やその他の事務の外部委託のみならずクラウドを含むシステム業務委託に至るまで、各種のトピックについて現実的な解決策を解説することとする。 |
| 開催日時 | 2012-02-17(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 個人情報の漏えいと消費者集合訴訟リスク ~外部委託における情報漏えい防止体制の整備~ |
| 講師 | 小沢・秋山法律事務所 パートナー 香月 裕爾 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,600円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-02-16(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】【特別企画】信用リスク・市場リスク計測の基礎 ケーススタディ等を交え、幅広い業務部門において必須の知識を基礎から解説 |
| 講師 | 有限責任あずさ監査法人 金融事業部 金融アドバイザリー部 ディレクター 佐上 啓 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2012-02-15(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | セブンとイオンの金融戦略研究 ~選択したビジネスモデルの違いが戦略を決める~ |
| 講師 | 経営企画研究所 代表 丹羽 哲夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,800円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-02-14(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社等における苦情等への対応に係る実務上の留意点 当局対応等の重要性の高まりや金融ADR等の近時の状況を背景に、監督当局の真の着眼点の見極めや実践的対応策など |
| 講師 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー 錦野 裕宗 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 保険会社等の業務運営において、顧客からの相談・苦情・紛争等(苦情等)に対する迅速かつ適切な対応が重要とされていることは今や十分に周知されているものと思われるが、金融ADR制度の導入や、保険会社向けの総合的な監督指針が詳細となったことなども含め、近年、その重要性はますます高まっている。監督指針には詳細な留意点が示されており、さらに、平成23事務年度保険会社等向け監督方針及び検査基本方針に至るまで毎年、その検証を重視することが繰り返し宣言されている。しかし、忘れてはならないのは、苦情等に対する迅速かつ適切な対応の要請は、いわば古くて新しい課題であり、現在のように監督指針が詳細なものとなる前から、監督当局では様々な意味合いにおいて重要視されていたという点、及び、そのことの全てが現在の監督指針に具体的に記載されているものではないという点である。 本講演では、まず監督指針等の内容・ポイントについての知識を再確認のうえ、そこには必ずしも記載されていない苦情等に係る監督当局の着眼点や、それを踏まえた保険会社の態勢整備の在り方について検討を行う。 他方で留意すべきなのは、苦情等と一纏めにしても、そこには不合理で対応困難なものも含まれていること、そして、それに正に対応しなければならないのは、(必ずしも紛争解決のプロとは位置付けられない)保険会社等の実務家であるという点である。保険会社等における態勢整備を検討するうえで、そのような前線で保険会社を代表して対応にあたる実務家の悩みを理解・共有し、組織としての対応策を講ずることは極めて重要と考えられる。そのために、困難な苦情等の特徴、対応策等に対する認識と理解が必須かつ有益と思われるところ、講師の豊富な経験を踏まえ、これらについても具体的に述べる。 その他、具体的トラブル事例とその防止・解決方法も含め、実務的かつ実践的な解説を行うこととする。 |
| 開催日時 | 2012-02-13(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | クレジットカード会社のマーケティング革新 |
| 講師 | 株式会社エム・セオリー 代表取締役 栃本 克之 氏 ディレクター 横野 貴志 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,000円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-02-13(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 暴排条項・保険約款導入の法的課題と態勢整備 ~実効的排除のポイントと保険契約・監督上の留意点~ |
| 講師 | 本村 健 弁護士 岩田合同法律事務所 パートナー 鈴木 仁史 弁護士 鈴木総合法律事務所 代表パートナー 中原 健夫 弁護士 弁護士法人ほくと総合法律事務所 代表パートナー 関 秀忠 弁護士 弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー 倉橋 博文 弁護士 LM法律事務所(元金融庁検査局及び証券取引等監視委員会専門検査官) |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 36,300円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-02-10(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 海外向けリース取引の実務 ~ タイ・台湾編 ~ |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 パートナー 杉山 泰成 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,800円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-02-10(金) 9:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【特別企画】ファイナンスの総合解説 デット・ファイナンス、エクイティ・ファイナンス、アセット・ファイナンスその他応用型の基礎知識と実務への活用を包括的に解説 |
| 講師 | 株式会社yenbridge 代表取締役 公認会計士 税理士 山下 章太 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | ファイナンスの仕組みが複雑化、多様化し、最前線の実務に要求される知識は複合的な、かつ高度なものとなっている。事情としては金融機関においても、商社ほか事業法人においても同様であり、激変する経済環境下にあって、多様なファイナンス分野の包括的な理解は極めて重要な課題である。 しかしながら、ファイナンスの個々の実務領域がますます高度化し、かつ、細分化されるなか、未経験のファイナンス分野の知識習得、ファイナンス提案等への複合的な知識の活用、あるいは横断的な知識を要求される企画、審査、内部監査等の部門における対応は容易ではない。加えて、実務に即してファイナンス全般を体系的に学ぶための教育システムは十分とは言いがたい。 本企画はこうした問題意識に基づき、デット・ファイナンス、エクイティ・ファイナンスその他の各種ファイナンス分野について、短期集中の講義及びケーススタディを通じ、包括的に、かつ、実務に即して理解することを目的とする。 金融機関等における実務経験を通じ、広範なファイナンス分野に精通する講師の解説により、具体的な資金調達の例や数値計算例などのケースを交えて、実務への活用に直結する知識の習得を図るものである。 |
| 開催日時 | 2012-02-09(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険代理店規制・直接検査の最新動向と実務上の留意点 |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 足立 格 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 36,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-02-09(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 改正犯罪収益移転防止法及び米国FATCA法を巡る最新動向とマネー・ローンダリング対策に係る顧客管理実務 注目される犯収法政省令案や米国財務省規則案等の最新の動きや先進的取組み事例等を交えて |
| 講師 | あらた監査法人 リスク・コントロール・ソリューション部 マネージャー 白井 真人 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 改正犯罪収益移転防止法の2013年4月の施行まで約1年を残すのみとなり、その実務的な対応については重い課題として既に周知されているものと思われる。金融機関等は、改正法の「取引時確認等」や、それらの顧客情報を「最新の内容に保つための措置」などの追加要件に対し、政省令等を踏まえて確実に対応することはもとより、これらの顧客管理措置で取得した情報を、マネー・ローンダリング対策の強化に活用していくことが必要であり、対応を進めるにあたっては、そうした総合的な観点からの検討が必須である。喫緊の課題として認識されてはいるものの、政省令等の詳細ルールが(2011年12月12日現在)未確定のために本格的な準備作業への着手が難しい状況が続いてきており、今後、これらルールが明らかになった後に施行までの短期間での厳しい対応が要求されることも予想される。 また、多くの金融機関では、米国のFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にも対応を迫られているが、顧客管理実務の観点からは、ほぼ同時期の対応が必要となることから、該当する金融機関においては、これら二つの規制要件の関係を良く整理したうえで、並行して効率的に準備を進める必要がある。 本講演では、金融機関のマネー・ローンダリング対策に関する豊富な経験を有し、近時はFATCA対応支援サービスを担当する講師の立場から、求められる顧客管理実務の整備について最新の情報をもとに具体的に解説するとともに、国内外の先進的な取組みの事例をも交え、求められる体制の整備についても解説する。 なお、2011年12月12日現在、今後の実務対応に向け注目の集まる改正犯収法に係る政省令案は未公表であるが、11年末から12年初頭にかけて公表された場合には、また、12年夏に予定される米国内国歳入庁(IRS)及び財務省のFATCA最終規則公表に先立ち、11年内にも規則案の公表が見込まれるところ、講演当日までにこれらの新しい重大な動きがあった場合は、入手可能な最新の情報に基づいて反映することとする。 |
| 開催日時 | 2012-02-07(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険ERMにおけるオペレーショナルリスク管理の実務的対応 |
| 講師 | PwC Japan あらた監査法人 ディレクター 辻田 弘志 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,400円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-02-07(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 会社法改正の最新動向と今後の実務等への影響 平成23年12月14日に公表された中間試案、近時のガバナンスを巡る問題事例や議論を踏まえて |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー 三浦 亮太 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成22年2月に法制審議会会社法部会に諮問された会社法制の見直しについて、同部会における審議を経て、平成23年12月14日に、「会社法制の見直しに関する中間試案」が公表され、パブリック・コメントの手続に付された。 会社法制の見直しは、主に「企業統治の在り方」と「親子会社に関する規律」を柱として各論点が検討されている。前者には社外取締役の選任の義務付け、監査・監督委員会設置会社制度の新設、社外役員の要件の見直し等の論点が含まれ、後者には株主が子会社の役員を提訴することができる多重代表訴訟や、子会社の重要な意思決定に親会社の株主総会の承認を要すること等の論点が含まれ、改正の行方が実務に与える影響は大きい。 また、近時の上場会社における不祥事により、民主党でも資本市場・企業統治改革ワーキングチームが発足するなど、企業統治の在り方に注目が集まっている。 そこで、本講演では、近時の上場会社における不祥事事例を採り上げつつ、中間試案に掲げられた項目の内容と、当該項目に関するこれまでの法制審議会における議論の内容を解説する。 |
| 開催日時 | 2012-02-06(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険販売の今後の戦略とチャネル研究 |
| 講師 | インスプレス 代表 保険ジャーナリスト 石井 秀樹 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,400円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-02-03(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関のIFRS対応ポイントと韓国における対応事例 |
| 講師 | TIS株式会社 ITソリューションサービス本部 ITソリューションサービス企画部 グループマネージャー 中村 知人 氏 主査 木村 高宏 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-02-03(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】基本的事例から学ぶ不動産ファンドの知識と実務上の留意点 ファンドの組成・運用やファイナンスのための必須知識を基礎から解説 |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 池田 順一 弁護士 長島・大野・常松法律事務所 松本 岳人 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 不動産ファンドに係る取引については、複雑なスキームが採用されることも少なくないが、こうした応用レベルの取引も基礎的事項についての知識や理解の上に成り立っていることはいうまでもない。また、不動産ノンリコースローン等のデフォルト事例における権利実現やリストラクチャリングも、同様にこうした知識や理解が前提となる。 そこで、本講義では、不動産ファンドの組成や運用に関与する実務家、また、不動産ファンドに対してファイナンスを提供する金融機関の実務家を対象として、典型的なスキームをもとに、基本的な仕組み、金融商品取引法や資産の流動化に関する法律等の関連する規制内容、その他の実務上の問題点や留意点について基礎から掘り下げた解説を行う。また、近時の資産流動化法の改正の影響等についても適宜言及する。 |
| 開催日時 | 2012-02-02(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融業界のロイヤルティ・マーケティングと優良顧客へのアプローチ |
| 講師 | 株式会社 野村総合研究所 IT事業推進部 上級コンサルタント TrueNavi 事業推進責任者 中村 雅彦 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,600円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-02-01(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | リースビジネスの現状、多角化の検証、今後の展望 |
| 講師 | 株式会社日本格付研究所 金融格付部 チーフ・アナリスト 本多 史裕 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-01-31(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | インドにおけるM&Aを巡る最新の法制度改正と実務上の留意点 最新の法制度改正とその影響や実務動向など |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 吉峯 亮子 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は、インドにおける執務経験を有する講師により、インドの法制度に関し、主にM&A実務等の観点から最新の改正動向、さらには実務への影響等を解説するものである。 2011年8月、日印の包括的経済連携協定が発効し、わが国企業にとってインド市場の重要性は高まるばかりである。その法制度整備については比較的高い水準にあるものと評価されるが、個別の法令の内容を確認すると、まだその内容や解釈が明確ではない部分が多い。また、制度の改正が頻繁であり、M&A関連法制度を例にとっても、2011年6月の独占禁止法の企業結合規制の施行、同10月の公開買付規制の改正のほか、外資規制の半年に一度の見直しなど、目まぐるしい変化があり、関連法制度の正確な理解とキャッチアップが焦眉の課題であるといえよう。 本講演では、インドにおけるM&A関連法規制を体系的に、かつ、実情と最新の改正等の動きを踏まえて解説するとともに、実務の動向についても紹介する。また、インドにおける実際のM&Aにおいていかなる点に注意すべきか、リーガルチェックのポイントについて解説する。 |
| 開催日時 | 2012-01-27(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | サイバー攻撃や情報流出・情報漏洩によるリスクと具体的対応 サイバー攻撃等に対抗するために何をすべきか、リスクの理解と事前防止策を含む具体的対応施策 |
| 講師 | 新日本有限責任監査法人 常務理事 公認会計士 榊 正壽 氏 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社 取締役 公認会計士 鈴木 淳二 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 民間企業、公的機関において、サイバー攻撃や内部関係者による情報流出、情報漏えいが増加しており、ケースによっては事業継続を危うくする事態に至っている。 これは、ITをコア・コンピタンスとする企業等が増加し組織内ネットワークのインターネットへの接続が拡大する一方で、従来、ITセキュリティについては「性善説」で臨む傾向のあった日本企業・組織であるが、雇用の不安定性等によるモラルの低下により、その前提が崩れつつあることに起因している。 最近の事件発生事例を見ると、機器やソフトウェアを含むITリソースの統合的管理の脆弱性を原因としているものが多い。セキュリティの強化は業務の効率性と相反する性質を有するところもあり、その「落としどころ」をさぐるためには、ITのガバナンスのあり方を具体的に定義する必要がある。 本講演では、抽象論ではない具体的施策としての「ITガバナンス」の成功事例の紹介、事前防止を含めた具体的施策について紹介する。 |
| 開催日時 | 2012-01-25(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | メザニンファイナンスにおける実務上の留意点 LBOにおける具体的な事例や契約条項例を中心に |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 パートナー 掘越 秀郎 弁護士 西村あさひ法律事務所 西野 比呂子 弁護士 西村あさひ法律事務所 藤井 毅 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | メザニンファイナンスには、資金調達、投資機会の多様化、資本政策、議決権の希薄化防止による円滑な事業承継や株式非公開化のための手法として多方面でのニーズがある。現在、欧州危機等の不安定要素がありながらも日本経済は回復過程にある中、企業活動や投資活動の復調と促進のため、より多様な資金調達、投資機会及び資本政策のニーズが発生すると予想されるが、メザニンファイナンスは、これらのニーズを満たすための有用な手法であり、その特性や内容を把握し、案件に応じた商品設計のもと、これを活用していくことが期待される。 そこで、本講演では、メザニンファイナンスの特徴及び経済的効用とその活用例を概観するとともに、LBOにおける劣後ローン、優先株式及び新株予約権に関する具体的事例や契約条項例を中心に、各商品の構造、関係者との調整を含む契約条件のポイントの説明を行う。また、各種の法的規制を踏まえた、関係者のニーズに応じたメザニンファイナンスの手法選択と商品設計のプロセスについても検討する。 あわせて、近年におけるメザニンファイナンスのEXITの局面の増加を意識し、講師らの具体的な経験をもとに、メザニン投資家によるEXITの手法及び実務上のポイントについても解説を行う。 |
| 開催日時 | 2012-01-24(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融業界のリタイアメントマーケティング ~定量データに基づいた価値観や金融行動の分析~ |
| 講師 | 株式会社ニッセイ基礎研究所 生活研究部門研究員 久我 尚子 氏 生活研究部門研究員 井上 智紀 氏 保険研究部門研究員 村松 容子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,600円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-01-24(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社におけるストレステストと新たな潮流 経営戦略、保険ALM、資産運用リスク管理等を貫くツールとしての次世代ストレステスト |
| 講師 | あらた監査法人 リスク・コントロール・ソリューション部 シニアマネージャー 西原 立 氏 あらた監査法人 総合金融サービス推進本部 金融調査室 主任研究員 兼 リスク・コントロール・ソリューション部 シニアマネージャー 村永 淳 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 保険会社のストレステストは、ショック的なストレスイベントを想定するイベント・ドリブンのアプローチが標準的な実務として行われてきた。 一方、監督当局の間では、金融システムの安全性を確認する手法のひとつとして、金融機関に対して統一的な手法によるストレステストが実施されており、欧州保険・年金監督機構(EIOPA)は、2009年11月から2010年3月に実施された第1回に続き、2回目のストレステストの結果を2011年7月4日に公表した。 上記の監督当局によるストレステストに見られるように、現在の潮流としては、全てのリスクカテゴリーを同時に含み全社的に展開するフレームワークが進展しつつある。 この全社的・リスク横断的なストレステストは、とりもなおさず保険会社経営そのものであり、リスク許容限度の設定、保険ALM、資産運用リスク管理、また、事業計画・経営戦略といった多くの局面において、検討のための土台となる情報を提供する。ただし、経営への有効活用のためには、できるだけ多くの関係者にとって納得性の高い、現実的な分析フレームワークを構築し、具体的なアクションに繋げやすくすることが重要なポイントとなる。 欧州危機の深刻化や監督当局の動向などからストレステストに対する関心がますます高まるなか、本講演では、上記のポイントを踏まえ、先行する銀行業界の事例も参考にしながら、保険会社における次世代ストレステストのあり方について考察する。次世代ストレステストにおいてはフォワードルッキングなモデル(時系列モデル等)を用いることが重要であり、当該モデル関連の解説にも力を入れる。また、保険会社においては、膨大な保有契約を含む負債へのインパクトを、資産への影響と同時にどのように計測するかが重要なポイントとなる。当該テーマに活用可能な複製ポートフォリオ、最小二乗モンテカルロ、カーブ・フィッティング等の最新リスク計測手法についても説明することとする。 |
| 開催日時 | 2012-01-20(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関におけるシステムリスクと外部委託先管理 |
| 講師 | 有限責任 あずさ監査法人 IT監査部 パートナー 遠藤 誠 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,300円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-01-20(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 国際シンジケートローンの契約構成と実務上の留意点 ローン契約の主要条項と担保設定方式を中心に |
| 講師 | ホワイト&ケース法律事務所 ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業) パートナー 洞? 敏夫 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 近時、多くの日系企業が海外で活躍する中、金融機関等にとってクロスボーダーでのシンジケートローンの組成は、その業務展開において重要度を増している。また、日本国内に目を向けても、大型買収ファイナンス等において、多くの海外金融機関が参加する中で、国際標準でのシンジケートローンによる資金調達が行われていく場面も増えていくものと予想される。 本講演では、わが国におけるシンジケートローンの基本構造を踏まえた上で、その対比における国際標準でのシンジケートローンの特徴や、クロスボーダーで行われる場合に必要となる契約条項の説明を行い、さらに、有担保で行われる場合の留意点について解説をする。 |
| 開催日時 | 2012-01-19(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | スマートフォンで変わるカードビジネス |
| 講師 | 株式会社 野村総合研究所 金融・資産運用ソリューション事業本部 金融ソリューション事業二部 上級コンサルタント 宮居 雅宣 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,700円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-01-19(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 事業再生を巡る最新動向及び実務対応の現状と今後 私的整理及び法的整理への債権者の対応と対抗的手段 |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー 山崎 良太 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 近時、事業再生ADRやDIP型更生手続等の新しい事業再生手法が導入されたことにより、債務者にとっては事業再生のための選択肢が広がっている。メインバンクを中心とした金融機関債権者の意向をふまえて手法やスキームが選択されるのが一般的ではあるが、たとえば中・下位の金融機関債権者の立場からは必ずしも納得感のない手法やスキームが選択され、事案の解決に満足できないケースもあるほか、債権者として詐害的会社分割に対する提訴や破産申立等の断固たる対抗的手段をとらざるを得ない事案も増加している。 経営不振企業の再生は待ったなしである現在において、債権者として判断や対応に苦慮する私的整理・法的整理の事案に対し、対抗的措置を含めてどのように対応するべきか。 本講演では、近時の事業再生手法の最新動向及び特徴を主として債権者の立場から、また、メインバンク以外の立場からも概観し、「事業再生」と「債権回収」の狭間での債権者の対応と対抗的手段を整理するとともに、債権者にとっての今後の事業再生のあるべき姿について検討することとする。なお、東日本大震災で被災した企業の復興・再生に関連する制度対応等が取り沙汰されているところ(2011年11月4日現在)、講演時点までの新たな動きについては、必要に応じて反映させることとする。 |
| 開催日時 | 2012-01-18(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | IAIS改訂版保険コア・プリンシプルと欧州ソルベンシーⅡが保険会社の経営に与える影響 ~国際的な規制強化の潮流とそれを踏まえた経営管理について~ |
| 講師 | プロティビティLLC アソシエイト・ディレクター 谷口 清貴 氏 マネージャー 鈴木 紀勝 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,000円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-01-17(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 最新金融規制動向とストレステストによるリスク管理実務 ~バーゼルⅢ時代のストレステストは何をすべきか~ |
| 講師 | 株式会社日本総合研究所 理事 西口 健二 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,100円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-01-17(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】為替デリバティブ取引の仕組みと実務上の留意点 実際の事例も交えつつ、仕組みとプライシングやリスク等に関する必須知識を解説 |
| 講師 | 株式会社QUICK 金融市場情報スペシャリスト リサーチアンドプライシングテクノロジー株式会社(RPテック) 取締役 藤崎 達哉 氏 新日本有限責任監査法人 金融部 エグゼクティブ・ディレクター 公認会計士 経済学博士 安達 哲也 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講義では、為替デリバティブに関し、その取引市場の沿革、取引の仕組み、トレーディング上の留意点、プライシング及びリスク管理など、実務上の一連のイシューについて包括的に解説する。 為替デリバティブ取引は、輸出入における為替予約取引を用いる事業法人から複雑な取引スキームを駆使する金融機関まで、業種を問わず広く一般に利用されているにもかかわらず、その取引上の仕組みや抱えるポジションのリスクに対する理解は十分とはいいがたい。また、金融危機以降、OTCデリバティブ・ポジションに対する各国金融当局からのリスク管理上の指導が強化されたことに加え、バーゼル規制及びIFRS(国際財務報告基準)などの国際的規制からリスク管理面やディスクロージャー上の対応に関する厳しい要求があり、デリバティブのリスク特性に関する理解や、そのポジションに対するリスク管理の高度化は喫緊の課題となっている。 本講義は、当分野において長年の経験を有する講師らにより、各々の専門領域と豊富な実績に基づいて多角的かつ包括的に、また、実務に即してわかりやすく解説を行うものである。実際の事例も交え、取引の仕組みからプライシングまで、最新のトピックにも触れながら、為替デリバティブ取引に関する実務上の一連の流れをバランス良く解説していく。商品開発、リスク管理、開示対応または内部監査等の部門において知識を要する担当者及びその他為替デリバティブに携わる実務家を対象に、為替デリバティブ取引に関する必須の基礎知識の習得に資することを目的とする。 |
| 開催日時 | 2012-01-16(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険代理店等への直接検査と管理態勢整備の着眼点 ~最新の検査基本方針等を踏まえて~ |
| 講師 | 東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 36,000円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-01-16(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】プライベートエクイティファンドの基礎 契約交渉上の留意点や規定例、近時の実務の動向など |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 林 宏和 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講義は、ベンチャーキャピタルファンドやバイアウトファンドといった未公開株式を投資対象とするプライベートエクイティファンドについて、これから設立・運用に携わろうとする実務家や、一定の経験を有するも網羅的な知識の再確認を図る実務家、そのほか、業務上の要請等から関心を有する実務家を対象に、ファンドの運用者または投資家として知っておくべき基本的なリーガル・イシューを解説するものである。 本講義では、わが国におけるベンチャーキャピタルファンドやバイアウトファンドの多くにおいてビークルとして選択されている投資事業有限責任組合(LPS)を専ら念頭に置き、ファンドの性格や運用方法を決定する根本規範である組合契約にフォーカスして、組合契約に規定される内容とはどのようなものか、そして、組合契約締結に至る交渉過程においてどのような点に留意するべきなのかについて、豊富な経験を有する講師の立場から実務に即して解説する。 2011年に改訂された経済産業省の投資事業有限責任組合モデル契約の内容(改訂箇所の内容、改訂の背景)、改訂後の最近の実務の動向、また近時の金融危機が実務に与えた影響等も踏まえ、実務上用いられる具体的な契約規定例を参照する。また、金融商品取引法その他実務に必須の法的知識を提示するのみならず、ファンドの組成時における契約交渉の在り方等について具体的なイメージを喚起しつつ、解説を行うこととする。 |
| 開催日時 | 2012-01-13(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ソーシャルメディア対応のリスクマネジメント ~ネット炎上防止、風評監視についてのよくある誤解~ |
| 講師 | デロイトトーマツリスクサービス株式会社 公認内部監査人 シニアマネジャー 亀井 将博 氏 コンサルタント 和田 皇輝 氏 ビジネスアナリスト 大西 彩乃 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,900円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-01-13(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 外国籍ファンドのストラクチャーと税務 ~平成23年の金融商品取引法改正を含む~ |
| 講師 | 東京青山・青木・狛法律事務所 パートナー 小野 雄作 弁護士 戸村 健 税理士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,500円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-01-13(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関の顧客説明、相談・苦情処理を中心とする顧客サポート管理態勢に関する課題と対応 最新の監督・検査の着眼点を踏まえて |
| 講師 | 東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 金融機関の顧客説明、顧客サポート業務(相談・苦情処理等)の適切な遂行と態勢整備は、金融機関と顧客との接点に関する業務の中核として、監督当局の関心も極めて高いところである。 本講演は、最新の、平成23事務年度監督方針、検査基本方針、検査マニュアル、検査指摘事例、行政処分事例等の分析に基づき最新の監督当局の着眼点と的確な対応策について実務的に解説するものである。 |
| 開催日時 | 2012-01-12(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | トップライン増強を実現する消費者信用業界の事業戦略 |
| 講師 | 一般社団法人 金融財政事情研究会 月刊『消費者信用』編集長 浅見 淳 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,100円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2012-01-11(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関の内部監査におけるリスク評価と監査計画策定の最新実務及び高度化のポイント リスク・アセスメント、オフサイト・モニタリング、計画策定の実務やベスト・プラクティスの紹介 |
| 講師 | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー 石塚 岳 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 金融機関の内部監査部門にリスクベースの監査が求められるなか、その実現に向け、リスク・アセスメント手法、オフサイトでの被監査業務のリスク変化の把握力、リスクの種類・程度に応じ頻度・深度に配慮した内部監査計画策定といった項目について、たゆまぬ努力や工夫がなされてきた。 しかし、これらの項目のレベルについては、金融機関間での格差が広がってきているのも実態であり、先進的な金融機関の取組みのレベルを射程としつつ、さらなる高度化を図ることが引き続き大きな課題であるといえよう。 本講演では、新年度へ向けた内部監査計画の策定準備も念頭に、実務の最前線に立つ講師の立場から、リスク・アセスメント手法、オフサイト・モニタリング、内部監査計画に関する金融機関の最新の実務について、ベスト・プラクティスの紹介を交えて具体的に解説する。 |
| 開催日時 | 2011-12-20(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 無担保ローンビジネスの展開と戦略研究 |
| 講師 | 株式会社日本格付研究所 格付一部 チーフ・アナリスト 本多 史裕 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,900円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-12-19(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社の商品・販売チャネル政策の最新動向 |
| 講師 | ナカザキ・アンド・カンパニー 保険ジャーナリスト 中崎 章夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,700円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-12-19(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 国際保険規制の最新動向と統合リスク管理態勢高度化の方向性 ソルベンシー規制・会計制度の融合的管理、統合的な資本・リスク管理の論点など |
| 講師 | 新日本有限責任監査法人 金融アドバイザリー部 エグゼクティブ・ディレクター 出塚 亨一 氏 新日本有限責任監査法人 金融部 保険セクター シニア・パートナー 小澤 裕治 氏 新日本有限責任監査法人 金融アドバイザリー部 アクチュアリアルグループ エグゼクティブ・ディレクター 川崎 俊彦 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 国際金融市場の危機、あるいは、東日本大震災に見られたリスク管理・業務継続体制の再構築など、保険会社が置かれている業務環境は国際的視点及び国内的視点ともに大きな変革が求められる状況になってきている。 こうした状況の下、保険会社として、さまざまなリスクを統合的に管理するERM態勢を確立することは喫緊の課題であり、最低要件としてのソルベンシー規制(EUソルベンシーⅡ等)への対応に加え、会計制度としての国際財務報告基準(IFRS)を経営戦略として活用することが、これからのリーディングプラクティスとなろう。従って、「財務・会計戦略-リスク管理-資本管理」をバランスよくコントロールし、市場競争上優位な立場に立っていくことが、保険会社の最大の課題であると考えられる。 本講演では、保険会社向けのコンサルティング等において豊富な実績・経験を有する講師らの立場から、保険会社の置かれた業務環境と規制環境を再整理し、規制要件だけでなく本質的に意味のある内部管理上の取り組み課題と主要論点を明らかにしながら、経営管理上の全体最適であり、かつ、効率的な態勢整備のための実践アプローチを紹介する。内部モデルを巡る論点などを含め講師らの最先端の知見や取組みを踏まえて示唆するほか、2011年3月のEUソルベンシーⅡのQIS5の実施結果レポート公表、2011年11月予定のカンヌ・サミットの動向など、講演時点までの最新の状況を踏まえて解説するものである。 |
| 開催日時 | 2011-12-16(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融ビジネスの業務継続体制に対する検証及び監査 監督方針や検査基本方針などにみる要請の高まりを背景に、BCPの検証や監査における具体的留意点など |
| 講師 | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ パートナー 福島 雅宏 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は、東日本大震災を契機とした業務継続計画(BCP)の実効性の評価と見直しの機運の高まり、先般公表された平成23事務年度監督方針及び検査基本方針における業務継続体制検証の要請を踏まえ、BCPの検証や監査のあり方について考察し、実践に向けての視点を提供するものである。 東日本大震災から半年以上が経過し、各金融機関等においては、震災を踏まえたBCPの見直しの取組みが図られている。見直しにあたっては、初期段階での課題の適切な洗い出しが重要であり、その際には監査の手法を活用した検証が有効かつ効率的である。また、見直しの完了後に、その妥当性について自己点検を行うことや、内部監査・外部監査による検証を行うことも、ガバナンスの観点から重要である。 しかし、BCPに対する検証・監査については、現時点では一般に認知されたメソドロジーは確立されておらず、また、BCPのあり方そのものの見直し・改善が図られている現状においては、その検証・監査は容易ではない。 本講演では、BCPの検証・監査の目的や位置づけを明確にした上で、それに即したフレームワークの構築の考え方、具体的な検証ポイント、検証手法等について、講師の実務経験も踏まえて具体的に解説する。 |
| 開催日時 | 2011-12-15(木) 13:30~16:00 |
|---|---|
| セミナー名 | クレディセゾンの保険販売戦略 ~ライフネット生命との提携の真の狙い~ |
| 講師 | 株式会社クレディセゾン 取締役 カード事業部 カードファイナンス部 担当 松田 昭博 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,300円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-12-15(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | プロジェクトファイナンスの実務と改正PFI法が与える影響 これからの可能性と留意すべきリスクなど |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 勝山 輝一 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は、金融機関においてプロジェクトファイナンスに携わった経験を有する講師が、現在までのプロジェクトファイナンス実務の概要を説明したうえで、改正PFI法が実務に与える影響及び留意すべき点を中心に解説するものである。 本講演では、まずプロジェクトファイナンスの基本構造を踏まえたうえで、リスク分担やセキュリティパッケージの機能等について説明を行い、その留意点等について具体的に解説を行う。そのうえで、今後の実務において着目すべき新たな制度である「コンセッション方式PFI」について、かかる制度の具体的な内容、意義及び実務に与える影響を詳しく解説し、かつ、ファイナンスを提供する際に留意すべきリスク等を網羅的に解説する。 現在までに国内で行われてきたPFI・PPPはいわゆる「箱モノPFI」に代表される施設整備事業がその大半を占めており、そこで提供されるファイナンスは「プロジェクトファイナンス的」なものに過ぎず、金融機関がプロジェクトリスクをとることはほとんど無かった。しかし、2011年6月1日に公布され、公布の日から起算して6ヶ月以内に施行されることとされている改正PFI法によって新しく導入される「コンセッション方式PFI」においては、金融機関が提供するファイナンスの返済原資が、プロジェクト実施主体が徴収する利用料金に依存することとなるため、金融機関もプロジェクトリスクをとることとなる。これに伴い留意すべきリスクが大幅に変わることとなるうえに、セキュリティパッケージの組成についてもより慎重にならざるを得ない。 このように改正PFI法は大きな影響をプロジェクトファイナンス実務に与えるものであり、改正PFI法の施行時期にあたり大きな関心が寄せられるところ、本講演では、現在のプロジェクトファイナンスについて概観したうえで、かかる現在の実務と対比する形で改正PFI法が与える影響について解説していくこととする。 |
| 開催日時 | 2011-12-14(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 米国発:金融業界のモバイル&ソーシャルメディア戦略 ~先端金融事例研究と本邦金融ビジネスへの示唆~ |
| 講師 | グローバルリサーチ研究所 代表 青木 武 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,700円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-12-14(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関の外部委託先管理のポイント |
| 講師 | 尾高・浅井国際法律事務所 浅井 弘章 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,500円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-12-13(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】SPVの仕組み及びヴィークル選択の留意点と会計・税務の基礎 案件に応じた適切なヴィークル選択のために、各ヴィークルの会計・税務上の論点等について、事例を交えて実践的に解説 |
| 講師 | 太陽ASG有限責任監査法人 社員(パートナー) 公認会計士 税理士 青山学院大学会計専門職大学院 客員教授 大矢 昇太 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講義は、今後知識習得を目指す、若しくは、一定の経験を有するも体系的な知識の整理・再確認を図る実務家等を対象として、証券化やファンド組成の際に必要となる各種ヴィークル(SPV:Special Purpose Vehicle)の特徴や、会計・税務上の論点等について実践的に解説するものである。 わが国では現行法上、SPVとして、民法上の組合、商法上の匿名組合、株式投資等を主たる目的とした投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、信託法上の信託、投信法上の投資信託や投資法人(REIT)、会社法に基づく合同会社、資産流動化法に基づく特定目的会社などの様々なヴィークルが利用されている。 一方で、このようなヴィークルに内在する会計上・税務上の論点を網羅的に把握することは容易ではなく、不適切なヴィークル選択を行ってしまった場合には、想定外の税負担を受けてしまう、監査法人より倒産隔離について否定的意見を受けてしまう等々、後々不利益を甘受せざるを得なくなる可能性も拭い切れない。 本講義では、かようなヴィークルに関する諸論点を概観するとともに、具体的事例を用いて留意点を解説するとことで、案件に応じた適切なヴィークルの選択を行うための基礎・実務知識を習得することを目的とする。 |
| 開催日時 | 2011-12-12(月) 13:30~17:45 |
|---|---|
| セミナー名 | 【第3回 政策フォーラム】野田政権における今後の政策と金融ビジネス等への影響 これから重視される分野は何か?金融ビジネスはどうなるか? |
| 講師 | 参議院議員 民主党政策調査会副会長 財務金融部門座長・税制調査会副会長 参議院財政金融委員会筆頭理事 大久保 勉 氏 衆議院議員 前 内閣府大臣政務官 金融庁等を担当 衆議院予算委員会委員 和田 隆志 氏 ボックスグローバル・ジャパン株式会社 代表取締役社長 元 金融庁監督局保険課 総括課長補佐 野尻 明裕 氏 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 梅澤 拓 弁護士 プロモントリー・フィナンシャル・ジャパン 専務取締役 元 官邸総理補佐官秘書官 金融庁検査局総務課総括課長補佐 堀本 善雄 氏 BNPパリバ証券会社 投資調査本部長 中空 麻奈 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2011-12-09(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | モバイルマネーと決済サービス ~Google・Apple・Amazon・VISA・マスターカード・PayPal・電子マネー・M-PESAの今後の動向~ |
| 講師 | 山本国際コンサルタンツ代表 関東学院大学経済学部講師 山本 正行 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,800円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-12-09(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 情報漏洩を巡るリスクと対応策 調査手法と是正措置の実情、内部からの漏洩や外部からの不正アクセスの例などを交えて |
| 講師 | デロイトトーマツFAS株式会社 フォレンジックサービス シニアヴァイスプレジデント 公認会計士 松澤 公貴 氏 デロイトトーマツリスクサービス株式会社 マネジャー 白島 知英 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 機密情報の漏洩等は金融機関、企業等において後を絶たず、Webアプリケーションのセキュリティホールを突かれた不正アクセスや、企業の内部者による情報の持出しなど、情報漏洩手法は多種多様である。最近においても、グローバル企業を対象としたサイバー攻撃や金融機関からの大規模な情報流出等は記憶に新しく、大きな問題として取り沙汰されている。不幸にも情報漏洩が発生した場合、情報漏洩の調査、情報漏洩の公表、被害者への対応、再発防止策の策定等が求められ、組織としてその対応に追われることになる。 本講演は、情報漏洩調査を含む不正調査において豊富な実績を有する講師らの立場から、主として顧客情報やその他の機密情報の漏洩を念頭に、企業や金融機関等が晒されるリスク等につき、具体的に考察、検討するものである。情報漏洩を巡る最近の動向とともに、講師らの経験や事例も踏まえて調査手法について解説し、発覚時の対応さらには事前防止のための対応について、具体的かつ実務的な観点から説明することする。 |
| 開催日時 | 2011-12-08(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | リスク商品の販売に関する司法判断の事例分析 ~最近の裁判例を参考にした販売と勧誘に関するスタンダード~ |
| 講師 | 小沢・秋山法律事務所 パートナー 香月 裕爾 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,600円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-12-08(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ソーシャルメディアに潜む脅威 ~企業が不祥事リスクを最小化するための労務管理「10の鉄則」~ |
| 講師 | E&R総合法律会計事務所 四宮 隆史 弁護士 中村 穂積 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-12-07(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関の本社部門に対する内部監査の課題と対策 ~最近の監督・検査方針に基づく当局の関心を踏まえて~ |
| 講師 | 東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-12-07(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | アジアにおける企業不祥事対応のケーススタディ |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 渋谷 卓司 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,400円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-12-07(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】信用リスク評価モデルの基礎とリスク管理の課題 把握しておくべき重要なモデルの弱点及び高度化へ向けた対応なども含め、具体的に解説 |
| 講師 | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ パートナー 桑原 大祐 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講義においては、信用リスク管理において一般的なものとなった統計的スコアリングモデルについて基礎から説明するとともに、顕在化している課題や統計モデルの弱点などの必須知識を解説する。 統計的スコアリングモデルを用いて企業評価を行う信用格付制度は、特にバーゼルⅡの導入後、一般的となっており、モデル自体も数学的に高度なものへと進化が図られてきた。一方で、リスクの測定(Measurement)とモニタリング(Monitoring)を中心とした運営を行い、信用リスクを管理(Management)する枠組みは、統計的な“Measurement”を偏重するようになってしまったことなどから、うまく機能していないとも指摘される。さらに、金融危機においては、高度化した統計モデルの前提条件や弱点を経営陣が認識せずに意思決定を行ったことも反省点として挙がっている。 本講義では、高度化した統計モデルについて基礎から説明を行うこととする。対象として、必ずしも数学を得意としない実務家、あるいは、経営判断等の視点から知識習得が必須となる役職者等をも想定し、把握しておくべき重要なモデルの弱点や前提条件についても具体的に解説する。また、これらの弱点や前提条件を踏まえた信用リスク管理のあるべき姿について考察し、“Management”のPDCAを好回転させ、与信コストを削減させるための施策を検討する。 |
| 開催日時 | 2011-12-06(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理のポイントと実践研究 |
| 講師 | 日本リスク・データ・バンク株式会社 取締役常務執行役員 稲葉 大明 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-12-06(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 中国における融資実務と規制に係る留意点 主に中国現地法人への貸付を対象に、近年の法改正等も交えて融資やシンジケーション等に関する留意点を解説 |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 森口 聡 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 中国市場が極めて重要なウエイトを占めるなか、日系企業の中国現地法人における資金需要は引き続き根強く、また、レンダーサイドからみても国内マーケットの停滞に対して中国における融資の重要性は高まるばかりであるが、関連する法律制度及び法的規制の正確な理解とタイムリーな動向の把握は必ずしも容易ではなく、特有の実務上の留意点やリスクも多い。 本講演では中国法及び融資実務に精通する講師の立場から、主として日系企業の中国現地法人へ資金貸付を想定し、日本からの外貨貸付、中国内での人民元貸付の各々について解説を行うこととする。中国の融資に関する規制、シンジケーションに関する規制、担保に関する法制度、対抗要件具備方法などに関し、この数年における重要な法改正についても適宜触れながら、近時の状況も踏まえた的確な理解に裨益することを目的とする。 |
| 開催日時 | 2011-12-05(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融マーケティングにおけるWEB活用 |
| 講師 | 株式会社マーケティング・エクセレンス マネージング・ディレクター 戸谷 圭子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,000円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-11-30(水) 13:30~15:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【特別企画】平成23検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画の解説 策定の趣旨とポイント |
| 講師 | 金融庁 検査局総務課企画・情報分析室長 兼 監督局モニタリング支援室長 岡本 宜樹 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 金融庁では、検査運営の基本的枠組みや重点検証項目等を明確化すべく、平成23検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画を策定し、平成23年8月26日、公表した。 本講演では、策定の趣旨も踏まえつつ、検査基本方針のポイントや基本計画、その他金融庁としての考え方について解説を行う。 |
| 開催日時 | 2011-11-29(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 不動産ファイナンス等に関わる法制度動向と実務上の留意点 施行を控える改正資産流動化法と政府令を中心に、債権法改正など |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 本田 圭 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 2011年5月に成立し公布された「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律」により一部改正された資産の流動化に関する法律(資産流動化法、SPC法)は、8月30日に政令・府令案が公表され、現在、パブリックコメント手続きに付されており、2011年11月24日までに施行される(9月12日現在)。「従たる特定資産」の概念の導入、特定資産の追加取得に係る規定の整備、特定目的会社(TMK)による組合持分の取得の緩和など、SPC法及びTMKをさらに使いやすいものにすることを目的とする同改正によって、不動産ファイナンス等の実務は、スキームの構築やドキュメンテーション等において大きく影響を受けることになる。そのため、同改正の把握はこれら実務に関わる者にとって非常に重要と言える。 また、民法(債権法)の改正については、法制審議会民法(債権関係)部会から2011年5月に公表された「民法(債権関係)の改正に関する中間論点整理」(中間論点整理)のパブリックコメント手続きが8月1日に締め切られ、各種業界団体、大手法律事務所等の多数の団体からコメントが提出されている。中間論点整理を踏まえて一定の論点の絞り込みがなされており、不動産ファイナンス等と深く関わる点も存在するところ、今後予想されるパブコメ結果や同部会の議論の再開も注目される。 本講演は、上記SPC法改正の施行のタイミングに合わせ、講演当日までに公表が予定される政府令案のパブコメ結果を含め、同改正の詳細と不動産ファイナンス等の実務への影響について、TMKを含む不動産関連業務に精通する講師の立場から、実務に即して解説を行うものである。さらに、将来的に不動産ファイナンス等にも多大な影響を及ぼす債権法改正に係る重要論点、また、その他の法改正動向についても解説する。 |
| 開催日時 | 2011-11-28(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ソーシャルメディアの変革とマーケティング事例 |
| 講師 | 株式会社野村総合研究所 システムコンサルティング事業本部 ビジネスオペレーションコンサルティング部 シニア研究員 山崎 秀夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,500円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-11-25(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 未公開企業オーナーへのタックスプランニング ~オーナー株式とシンガポールの資産管理会社を中心に~ |
| 講師 | Taf management 中野 孝昭 税理士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,600円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-11-25(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | リスク性金融商品の勧誘・説明義務に関する最新の法令や裁判例等と有効な対策 法令等のルール、注視すべき裁判及び金融ADRの傾向と分析、苦情・紛争抑止のための態勢整備 |
| 講師 | 弁護士法人三宅法律事務所 パートナー 渡邉 雅之 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は、近時、リスク性金融商品の勧誘・説明義務が重大な課題となっているところ、最新の状況に鑑み、そのルールや裁判例等、また、実務上の有効な対策について解説を行うものである。 リスク性金融商品に関して例を挙げれば、近時、急激な円高のために為替デリバティブ取引により大きな損失が生じたことで、金融機関に対する苦情・金融ADRや裁判などの紛争が増えている。他方、高齢化に伴い、高齢者に対する金融商品の販売に関して、説明義務や適合性が問題となるケースが増えている。 これらの事象を踏まえて、従来の金融商品取引法上の勧誘・説明義務に関する規制が、本年4月に施行された法令・監督指針・自主規制規則の改正(合理的根拠適合性、勧誘基準、注意喚起文書)により強化されている。他方、訴訟や金融ADRでは、金融機関の側が一方的に負けてしまうケースが増えている。 本講演では、これら最新の法令等のルールと裁判や金融ADRの傾向等について解説、分析することとし、併せて、どうすれば、顧客からの苦情や訴え・金融ADRの申し立てを減らすことができるのかという点に焦点を当てて実務上の対応について提案する。 |
| 開催日時 | 2011-11-24(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 外国籍ファンド販売の実務、ゲートキーパー業務 |
| 講師 | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー 野崎 竜一 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,400円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-11-22(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | インドにおける金融・証券市場規制と留意点 金融ビジネス等における留意点を交えて |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 太田 穰 弁護士 長島・大野・常松法律事務所 山本 匡 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演はインド市場の急成長を背景に、特に金融ビジネスに焦点を当てて、語られる機会の少ないインド金融・証券市場に対する規制につき、金融実務及びインド関連案件に精通する講師らの立場から解説するものである。 欧米経済の停滞のなかインドが世界経済の牽引役となり、日本企業も製造業を中心とするインド進出が増加傾向にあることは周知のとおりである。ここに至り、継続する円高基調や東日本大震災後の経済環境から新興国を中心とする海外への進出が焦眉の課題であるなか、日本企業のM&Aを含む対インド投資はさらなる活発化が予想される。また、事業拡大のチャンスを有しながら資金力の乏しいインド企業の資金ニーズも強く、こうした状況から今後の金融ビジネスにとってインド市場のポテンシャルは極めて大きいものといえよう。 本講演では、投融資ほか金融ビジネスに関連して担保その他の実務に係る規制、また、証券関連法令や証券化・流動化の現状に至るまで、加えて、銀行、保険ほか金融機関の事業展開に関わる規制なども含め、講師らの最新の知見も交えて解説を行うこととする。 |
| 開催日時 | 2011-11-18(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 米国FATCA法を巡る動向と金融機関の対応 金融機関への広範な影響を念頭に、公表内容の解説と直近の動向アップデートなど |
| 講師 | 有限責任あずさ監査法人 金融アドバイザリー部 パートナー 山﨑 千春 氏 KPMG税理士法人 ファイナンシャルサービスグループ シニアマネジャー 丹生谷 佳子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)は、本邦を含む各国の金融機関に広範な影響を与えるものとして、その動向に強い関心が寄せられている。同法が2010年3月18日、米国で成立するに至り、また、米国内国歳入庁(IRS)は2011年7月14日のNotice2011-53まで、2010年以来、これまでに3回に亘りNoticeを公表しており(2011年9月9日現在)、これら多くの公表内容の網羅的、かつ、正確な理解が急がれるところである。 FATCAは、米国税法上の義務を非米国金融機関に求める、言わば域外適用であり、この点で、本邦のみならず各国のマネー・ローンダリング法、個人情報保護法等と齟齬が生じる可能性が高い。FATCAにより、税務に限らず顧客管理措置、対外決済、ITの見直しなど、マネー・ローンダリングほかコンプライアンス、マーケティング、情報システム、セキュリティほか各部門の組織横断的な対応、さらには、コスト・リスクを踏まえた経営レベルでの戦略的な判断が求められ、本邦金融機関においても具体的な取組みを模索する動きがみられつつある。 こうした状況にもかかわらず、FATCAの具体的な内容については依然として不透明な部分も多い。また、パススルーを初めとして、対応は困難、ないしは非現実的として多くの金融機関や各国業界団体が懸念を表明しているものも含まれる。FATCAにおける金融機関の定義は広く、銀行、証券、保険、ファンド業界その他の業態も含め、影響の有無・度合いについて引き続き注視が必要な状況である。 以上のようにFATCAを巡る状況が刻々と変化するところ、また、最終規則案が2011年末に公表されると見込まれるなか、本講演では、IRSの公表内容について改めて包括的に整理するとともに、直近の動向アップデート、さらには、今後注目すべきポイント、そして、金融機関がいかに対応すべきかの論点について考察する。なお、新たな内容の公表がなされた場合など、状況の変化がある場合は、講演時点の状況により可能な限り反映することとする。 |
| 開催日時 | 2011-11-17(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】【特別企画】英文契約の基礎 さまざまなビジネスの場面をイメージしつつ、具体的な英文の例示などを交えて |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 ニューヨーク州弁護士 松澤 香 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | クロスボーダー化の進展に伴い、英文契約を取り扱う機会は急速に増えているが、その知識を網羅的に、かつ、実務に即して学習する機会は少なく、また、英語となっただけで苦手意識を持たれることも多い。しかし、英文契約ならではの典型的な様式・表現や見落としやすいポイントを習得することで、その理解と活用の度合いは飛躍的に向上するものと思われる。 本講義は、英文契約に係る知識の習得または再確認、レベルアップを図る実務家や役職者を対象として、日々英文契約の作成・検討に関与する講師の経験に基づき、具体的なビジネスの場面に即した、かつ、効率的な知識習得を図ることを目的とするものである。英文契約の基本的な構造を分かり易く説明するとともに、英文契約の考え方や用語、表現についてサンプル文例等を交え、契約交渉等の具体的な場面をイメージしつつ解説する。 |
| 開催日時 | 2011-11-16(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【特別企画】これからの保険サービスと保険規制監督のあり方 価値協創サービスとしての保険 |
| 講師 | 慶應義塾大学 先導研究センター「環境共生・安全システムデザインの先導拠点」 特任教授 保井 俊之 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は、いわゆる価値協創型のビジネス・モデルの時代に迎えた今後の保険サービスと、保険規制監督のあり方について、講師の最近の著作とその後の新たな実証研究に基づき解説するものである。 先鋭的なグローバル企業が争うように、顧客が企業にサービスのあり方を提案し、顧客と企業がともに価値を創っていくビジネス・モデルを展開しつつある。このC2Bモデルとも価値協創型とも呼ばれるビジネス・モデルは、保険サービスをはじめとする金融サービスに最も適合的であると言われている。 本講演では先ず、サービス科学とシステムズ・アプローチに関する学術研究の最近の進展を踏まえ、価値協創時代の保険サービスはどのような変貌を遂げるべきなのか、講師による実証研究のデータの紹介を交えながら、平易に説明する。 その上で、今後の保険行政はどのような方向性となるのか、1900年以来の日本の保険行政の歴史を俯瞰しつつ考察する。 さらに、価値協創時代の保険サービスの担い手はどのような点に配意しながら、自らのビジネス・モデル並びに保険規制監督との関係を構築すべきかを検討し、講師と出席者がともに講演並びに質疑応答を通じて、インタラクティブに認識を深めていくこととする。 (本講演は、講師は無報酬、開催に要する費用は実費にて開催致します) |
| 開催日時 | 2011-11-15(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 中国投資の多様なストラクチャーと最新動向 人民元ファンドその他の対中投資ストラクチャーの比較等と最新の規制及び実務の動向 |
| 講師 | 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 杉田 泰樹 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は人民元ファンドを用いた中国投資について、その多様な類型と各々の特色や留意点を、また、変化の著しい投資関連の規制及び実務に係る最新動向を交えて解説するものである。 中国における近年の外資規制強化に伴って、周知のとおり日本を含む外国投資家による従前のオフショアストラクチャーを用いての投資は難しくなってきており、人民元ファンドを用いた投資が注目を集めてきた。 人民元ファンドはオフショアファンドの問題点を克服し、中国人投資家によるオンショア投資を活かすためにも有効であると認識されているものの、一口で人民元ファンドといっても実態としては多様な仕組みがとられており、その規制態様も大きく異なる。また、各主要都市での制度運用が開始されている適格外国リミテッドパートナーシップ(QFLP)方式のほか、関連規制の緩和・強化等の変化も目まぐるしい。最近の経済環境下にあって引き続き中国が極めて重要な投資先であることは論を俟たないが、こうした多様な投資形態やその長所・短所ほか留意点の理解、激変する規制動向のフォローは大きな課題といえよう。 本講演では、北京における実務経験を有する講師の立場から、人民元ファンドへの参入形態についてスキーム例を交えて紹介し、その長所・短所等を考察するとともに、2011年1月より上海市で施行され、その後北京・天津・重慶の各主要都市でも実施されているQFLP制度の実務動向や、2011年9月1日施行の「外国投資家による国内企業の買収に係る安全審査制度実施についての規定」のほか、新たな外国投資家規制などの最新法制動向についても解説する。 |
| 開催日時 | 2011-11-11(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 銀行による保険窓販ビジネスと法規制 |
| 講師 | 弁護士法人ほくと総合法律事務所 代表パートナー 中原 健夫 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,500円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-11-11(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関を巡るシステム環境の変化と監督当局の動向を踏まえたシステムリスク管理上の留意点 ITの高度化や外部委託への移行の流れ、金融庁要請文書などの最近の動きを踏まえて |
| 講師 | プロモントリー・フィナンシャル・ジャパン ディレクター システム監査部長 元 日本銀行 金融機構局 企画役 江見 明弘 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 近年、インターネットバンキング、スマートフォンを活用したモバイルバンキングなどの顧客チャネルの多様化、システムの仮想化やクラウド・コンピューティングにみられるようなITの高度化に加え、システムの共同化やアウトソーシングの拡大などITの「開発・保有」から「外部委託・利用」への流れが主流となるなど、金融機関を取り巻くシステム環境は大きく変化しつつある。 こうした中、先般の大手金融機関の大規模システム障害を受け、2011年7月8日に金融庁より「金融機関におけるシステムリスクの総点検について」が発出され、各金融機関は、実効性のあるシステムリスク管理態構築が急務となっている。 本講演では、まず、最近の金融機関を取り巻くシステム環境の変化とそれに伴う課題について述べ、次に最近の金融機関におけるシステム障害の発生状況を概観し、最後に最近の大手金融機関のシステム障害とそれに伴い発出された「金融機関におけるシステムリスクの総点検について」を踏まえ、金融機関が実効性あるシステムリスク管理態勢を整備するうえでの留意点について解説する。 |
| 開催日時 | 2011-11-10(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | バーゼルⅢ-規制対応上の論点と影響度分析上の留意点 |
| 講師 | 有限責任あずさ監査法人 金融事業部 パートナー 大庭 寿和 氏 シニアマネジャー 福永 謙介 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,500円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-11-10(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 外国籍私募ファンドに係る法的問題の詳細検討及び最新動向 2011年金融商品取引法改正ほか法令・監督指針の最新動向も踏まえ、組成、販売勧誘及び顧客サービスに係る諸問題を解説 |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 清水 啓子 弁護士 長島・大野・常松法律事務所 鈴木 謙輔 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は、日本の投資家が投資する外国籍私募ファンドの組成、販売勧誘及び顧客サービスについて、近時の実務、法令等の最新動向も交えて実務上の法的問題を解説するものである。 外国籍ファンドはその形態により金融商品取引法上の業規制・開示規制が大きく異なるところ、リミテッド・パートナーシップから外国籍投資信託まで、実務上用いられるスキームごとに、関係当事者の実務上の役割も踏まえながら、金融商品取引法上の私募・業規制を中心に整理・分類して詳細に検討する。 また、2011年5月に成立・公布された金融商品取引法改正による適格投資家向け投資運用業の新設、英文開示の範囲拡大等、法令・監督指針に関する最新の動向も踏まえた分析を行うこととする。 |
| 開催日時 | 2011-11-08(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 自然災害リスクの計量化技術 |
| 講師 | AIR Worldwide マネージャー 藤村 和也 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,800円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-11-08(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 海外向けリース取引の実務 ~ インド・香港・シンガポール編 ~ |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 パートナー 杉山 泰成 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,300円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-11-08(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社による代理店管理と保険代理店の内部管理態勢の高度化 検査基本方針等を踏まえた実務的な検査対応について |
| 講師 | デロイトトーマツコンサルティング株式会社 執行役員 吉岡 巌 氏 デロイトトーマツリスクサービス株式会社 執行役員 野見山 雅史 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 昨年に引き続き、平成23検査事務年度検査基本方針においても、委託業者・代理業者に対する金融検査について明示的な記載がなされ、規制当局の保険代理店等への注目度が高まっていることが明らかとなっている。また、金融機関からの情報流出・情報漏えいが継続的に問題となるなか、去る2011年8月にも保険代理店を通じた顧客情報流出事件が明らかになったことは周知のとおりである。保険会社にとって、代理店チャネルは今後も重要な販売チャネルである以上、検査対応等の側面からも、代理店管理の高度化は焦眉の課題であるといえよう。 本講演では、保険会社に対する様々なコンサルティング実績を有する講師らの立場から、保険会社による保険代理店等の管理、および保険代理店等の内部管理態勢構築において、高度化にあたって着目すべき点を検討する。 |
| 開催日時 | 2011-11-07(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社のマーケティング革新 |
| 講師 | 株式会社ローランド・ベルガー 取締役 パートナー 米田 寿治 氏 プリンシパル 渡部 高士 氏 シニアプロジェクトマネージャー 栗原 勝芳 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,900円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-11-02(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 情報システムのリスクと危機管理 |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー 飯田 耕一郎 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,700円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-11-02(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ストレステストを巡る実務上の課題及び最新動向と今後の対応 金融規制を踏まえたあるべき姿、実践的ストレステストの具体的手法、実施における課題など |
| 講師 | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ マネジャー 岡崎 貫治 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 世界的金融危機はValue at Risk(VaR)やスコアリング・モデルなどを始めとする、特定の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにした。従来より、ストレステストはリスク管理の重要な手法として存在してきたが、こうした問題点を克服する手段として、様々なストレス事象を包括的に取り込み、さらにフォワードルッキングな視点に立ったストレステストは、国際的潮流として重要性が高まっている。フォワードルッキングなシナリオに基づくストレステストに関しては、バーゼル銀行監督委員会「健全なストレス・テスト実務及びその監督のための諸原則」や金融庁検査基本方針などからもその重要性が指摘されているところではあるが、現状、各金融機関の取組みにおいてはその内容ならびに進捗度、またレベル感には差異があることも事実であろう。こうした状況の下、引き続き着実な対応が求められており、より実効性のあるストレステスト高度化に向けた取組みは喫緊の課題である。 本講演では、世界的金融危機と、それに続く深刻な景気後退を経験した金融機関におけるストレステストの最新の実務動向と具体的手法を解説し、今後どのようにその高度化を図っていくべきなのかを検討する。 金融規制がイメージするストレステストを踏まえ、あるべきストレステストの姿を整理する。そのうえで、フォワードルッキングな視点に立った実践的ストレステストの具体的手法について解説を行うとともに、課題点についても考察を行う。また、ストレステストの業務への導入から継続的な運用に至る点についても事例を交えて考察する。 |
| 開催日時 | 2011-11-01(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | グローバル化をふまえた統合的な反社会的勢力排除の取組みポイント |
| 講師 | 株式会社エス・ピー・ネットワーク 総合研究室 リスクアナリスト 芳賀 恒人 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,300円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-10-31(月) 13:00~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 英文M&A契約作成・検証の基礎実務 ~ファイナンス契約を含めて~ |
| 講師 | TMI総合法律事務所 パートナー 日本国及びニューヨーク州 公認会計士/米国公認会計士 内海 英博 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 36,100円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-10-31(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | JAバンクの戦略研究 ~揺らぐ顧客基盤・ビジネスモデルと今後展開~ |
| 講師 | 経営企画研究所 代表 丹羽 哲夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,700円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-10-28(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険代理店における不祥事件対策 ~保険会社,保険代理店のそれぞれがやるべきこと~ |
| 講師 | のぞみ総合法律事務所 吉田 桂公 弁護士 番匠 史人 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 36,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-10-28(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 再生可能エネルギー買取制度の法的問題点とその対応 新法の公布と、期待される今後のビジネス展開の可能性及びリスクを念頭に |
| 講師 | TMI総合法律事務所 ニューヨーク州弁護士 深津 功二 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 政局面からも脚光を浴びた「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(再生可能エネルギー買取法)は2011年8月26日、参議院本会議にて可決・成立し、同8月30日、交付されるに至った。 同法に基づく再生可能エネルギー買取制度に関しては、再生可能エネルギーの利用促進と太陽、風力、バイオマスほか各種エネルギー関連ビジネスの市場拡大に向けて極めて大きな期待が寄せられており、具体的な取組みの検討の活発化にも注目が集まっている。 同制度を巡っては、買取価格はどうなるのか、そして、投資は回収できるか、そもそも普及が促進されるのか、といった点に関心が向けられている。一方で、買取価格以外の問題があまり注視されない状況にあるものの、発電設備の施工・運営、買取期間終了の一連のプロセスにおいて買取価格以外に多くの問題点が存在することは、経済産業省におけるさまざまな審議会・研究会での詳細な議論からも窺える。今後、同制度を利用したビジネスの立上げ・導入、あるいは、積極的な投融資の実行にあたり、採算性を含む可能性とリスクを把握するうえで、これらの問題点の理解とその対応の検討が必須のものとなるといえよう。 本講演では、金融分野及び環境法関連案件における経験を有する講師の立場から、同調査会における詳細な議論の内容も踏まえ、同制度に関する法的留意点に関し、技術的で理解の難しい部分も含めて解説することとする。なお、買取価格を含む同制度の詳細な内容として注目される政省令案やガイドラインが公表された場合など、講演時点の最新動向については、状況に応じて可能な限り反映することとする。 |
| 開催日時 | 2011-10-27(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】株式譲渡の基礎 株式譲渡契約書のサンプルを参照しつつ、各当事者からみた留意点などを解説 |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 パートナー ニューヨーク州弁護士 森本 大介 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 株式譲渡は企業買収やグループ再編のための手段として、極めて多くの案件において用いられており、これら案件に関与する実務家等にとってその知識は必須のものとなっている。 しかし、株式譲渡のプロセスにおいて対処しなければならない事項や、株式譲渡契約書において交渉しなければならない事項は多岐に渡り、これらの対応如何では後々トラブルに巻き込まれることも少なくない。このように多用され、多くの注意点が存在するにもかかわらず、株式譲渡に関する解説書等は少なく、経験に依存している部分が多いのも実情であり、その手法について体系的に学ぶ機会は限られている。 そこで本講義では、企業買収やグループ再編に関与する、または今後関与しようとする実務家や役職者を対象として、株式譲渡のプロセスにおける留意点を網羅的に解説する。さらに、株式譲渡契約書のサンプルを参照しつつ、売主及び買主のそれぞれの立場から規定すべき事項やそのポイントについて、講師の豊富な実績も踏まえ、実務に即して解説することとする。 |
| 開催日時 | 2011-10-26(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関における外部委託先管理の解決策 ~リスク管理の観点からの実務対応~ |
| 講師 | 有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー 田宮 秀樹 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,100円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-10-26(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | バーゼルⅢを巡る最新動向と影響及び今後の対応 自己資本規制と流動性規制等の経営及び実務へのインパクト、必要な対応とスケジュール |
| 講師 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 金融サービス事業部 シニア・マネージング・コンサルタント 八ツ井 博樹 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 2013年からバーゼルⅢの自己資本規制がスタートすることとなっており、各金融機関においては、新たな控除項目、CVA、大規模金融機関への相関係数の変更などによる普通株式等Tier1比率へのインパクトを試算し、これを契機に今後の経営戦略を見直しているケースもあるものと思われる。 また、2015年から新しいバーゼル規制となる流動性規制および2018年からスタートする安定調達比率についても、すでに今年から観察期間がスタートしており、今後、金融機関への影響や、実態的に求められる水準などの目線がクリアになってくるものと思われる。 さらに、今年7月にバーゼル銀行監督委員会と金融安定理事会(FSB)から公表されたとおり、G-SIFIs(またはG-SIBs)についても、新たな資本賦課として重く金融業界にのしかかる課題となることが見込まれている。 本講演では、先ずバーゼルⅢについて最新の公表内容までを網羅する形で解説する。さらに、バーゼルⅢが金融機関に及ぼすインパクトを定性的および定量的に明らかにしたうえ、必要な対応とそのスケジュール例を提示することとし、自己資本規制及び流動性規制等の影響とともに、注目の高まるソブリン・リスクとバーゼルⅢとの関わり等にも言及する。 |
| 開催日時 | 2011-10-25(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 映像配信ビジネス成功への道 |
| 講師 | NHK編成局 編成センター チーフ・ディレクター 鈴木 祐司 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,400円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-10-21(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】事例から学ぶ粉飾決算の手口やその発見・調査のポイント 複数業種の事例、財務諸表に対する注意点や発覚時の調査などを実態に即して具体的に解説 |
| 講師 | デロイトトーマツFAS株式会社 リオーガニゼーションサービス マネージングディレクター 公認会計士 石田 晃一 氏 デロイトトーマツFAS株式会社 フォレンジックサービス シニアヴァイスプレジデント 公認会計士 松澤 公貴 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 粉飾決算が債権者や投資家を含む財務諸表利用者の意思決定に対して甚大な悪影響を及ぼすことは論を俟たないが、過去の一部の破綻事例において粉飾決算が行われていたことは周知のとおりであり、企業再生等に携わる講師らの経験からも、経営不振企業の過去の業績、財務数値には、多様な手法により粉飾決算が実行されていた事例が数多く存在する。 粉飾決算については通常、上級管理者や経営者が関与して意図的に隠蔽を行うため、その発見には極めて大きな困難が伴うことが多い。一方で、ビジネスを正しく理解し経済実態を考慮したうえで、入手した財務数値に対して深度のある分析を実施していれば粉飾決算の多くは発見が可能であったことも事実である。先行きの不透明感の続く環境の下、粉飾決算の絡む事案が変わらず散見され、ますます巧妙化、複雑化も懸念されるなか、実態に基づく実効的な発見手法等の理解は、今後も実務上の焦眉の課題であるといえよう。 そこで、本講義では以上のような背景から、企業再生や不正調査における講師らの経験も踏まえ、粉飾決算に関して具体的に解説する。粉飾決算の手口に関し、現実に顕在化している類型と、各々のメカニズムを整理するとともに、複数類型の組合せによる複雑化などについても示唆することで、実情を俯瞰する。また、具体的に多様な業種をとりあげ、各業種に特有の粉飾パターンを解説したうえ、具体的な財務諸表等の数値例に基づき、実際に行われる粉飾やその発見のポイント等を詳説する。さらには、財務諸表等を通じた発見の後の調査手法についても言及する。 講師らの豊富な実績に基づく実態に即した解説を通じ、債権者、投資家等における実務のさらなる高度化に資することを目的とする。 |
| 開催日時 | 2011-10-19(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険窓販を巡る規制及び実務対応における留意点 最新の制度改正動向を踏まえ、典型的なトラブル事例等を交えて |
| 講師 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー 錦野 裕宗 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 銀行窓販が保険商品の販売において主要なチャネルのひとつとなった現在、保険商品を提供する保険会社にとって、また、販売勧誘を行う銀行等金融機関においても、当該チャネル特有の銀行窓販規制を適切に遵守することは勿論、顧客との実際のトラブルを可及的に防止・解決することは、ビジネスの成否に直結する極めて重要な課題といえよう。 本講演では先ず規制面に関し、本年7月6日に金融庁より「銀行等による保険募集に係る弊害防止措置等の見直しについて」が公表され、7月8日には当該制度改正に係る保険業法施行規則(案)等がパブリックコメントに付されたところ、当該改正のポイントである、①融資先募集規制等の規制対象の緩和、②弊害防止措置等の実効性確保のための措置の追加、を中心に、銀行窓販規制全般に対する注意点、実務上の留意点等について、ポイントを絞り具体的に解説することとする。 また、銀行窓販に典型的に見られるトラブル事例について、講師の経験等も踏まえ、それを類型化したうえで、トラブルの可及的防止・解決といった実務の要請に即した解説を行う。 銀行窓販規制の理解と最新動向の把握、また同時に、実務対応にも資する実践的な内容とすることを目指すものである。なお、上記のパブリックコメントの回答(8月15日現在未公表)がなされた場合など、講演時点の最新の状況については可能な限り反映することとする。 |
| 開催日時 | 2011-10-18(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 外国投資信託の設立・募集および関連する日本の課税関係 |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 竹野 康造 弁護士 小山 浩 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,400円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-10-18(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 新シニア層「アラダン」攻略のポイント ~高齢先進国・ニッポンの有望消費者をどう捉えるか~ |
| 講師 | 株式会社アサツー ディ・ケイ 価値創造プランニング本部 プランニングディレクター 新シニアライフデザイニング「アラ☆ダン研究所」研究員 稲葉 光亮 氏 価値創造プランニング本部 プランニングディレクター 新シニアライフデザイニング「アラ☆ダン研究所」研究員 末永 幸三 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 36,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-10-18(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 海外プロジェクトファイナンスの実践 リスク分析方法や具体的な組成方法を中心に |
| 講師 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 スペシャライズドレンディング・ジャパン本部長 井上 義明 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 商社や電力会社と銀行を中心に担われてきた日本のプロジェクトファイナンスであるが、日本企業の海外進出の深化とともに、多様な産業分野の海外事業の資金調達において、プロジェクトファイナンスの利用例は徐々に増加してきた。リーマン・ショックを契機とする世界的金融危機はプロジェクトファイナンス市場にも大きな影響を与え、参加銀行数の減少などを引き起こしたが、一方で案件は大型化しつつあり、これは融資金額の増大を招いており、なお予断を許さない状況が続いている。2011年以降を展望すれば、アジアにおける新規の発電所案件やエネルギー関連案件等の資金調達が注目されるほか、東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故が国内外のエネルギー政策、プロジェクトファイナンス市場にも影響を及ぼすことは必至であり、こうした状況にも注視が必要である。 本講演は、当分野において20年余の経験を有し、現役のプロジェクトファイナンス・バンカーによる稀少な解説書として『実践プロジェクトファイナンス』を上梓した講師の解説を通じ、以上のような環境を踏まえた実務の高度化に裨益することを目的とする。 海外プロジェクトファイナンスについて、その内容や特徴、沿革を概観したうえ、具体的なリスク分析の手法、ストラクチャリングの手法、キャッシュフロー分析の手法、プロジェクトファイナンス組成の手法などを詳説する。多様な案件所在国における、資源開発、プラント、発電、インフラ等の案件における講師の豊富な実績も踏まえ、実務の実情に即して具体的に解説するものである。 |
| 開催日時 | 2011-10-17(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ソブリンリスクへの対応とリスク管理の高度化 |
| 講師 | ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会社 ディレクター シニア・プロダクト・スペシャリスト 水野 裕二 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,100円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-10-14(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 住宅ローンの収益・リスク管理態勢と高度化への取組み 検査基本方針にみるリスク管理への要請の高まり等を念頭に |
| 講師 | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ ディレクター 岸本 浩一 氏 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー 藤谷 容生 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は、住宅ローンを巡る金融機関間の競争激化や、今般公表された平成23検査事務年度検査基本方針からも窺えるリスク管理等に対する要請の高まりなど、近時の環境を踏まえ、各種モデルに基づくリスク・収益管理に焦点を当てるものである。 民間金融機関の住宅ローン・ビジネスには相応の歴史があるものの、旧住宅金融公庫 (現独立行政法人住宅金融支援機構) が直接融資を大幅に縮小して以降は、法人融資が伸び悩む環境とも相俟って特筆すべき業容の拡大がなされてきた。 他方、貸付期間が超長期に亘ること、これに関連して所謂シーズニング効果(融資実行直後にデフォルトが少ない一方で後に徐々に増加する効果)や、期限前返済の発生、途上与信に必要となる情報の収集が困難であることなど、住宅ローンには法人融資とは著しく異なる特徴が多く内在している。さらには、金融機関間の競争環境が激化し、充分な収益が見込みにくいビジネスに変貌しつつあることも、近時、俄かに取り沙汰されている。このような特徴や近時の情勢については認識と関心が深まりつつあるものの、住宅ローンの特性を踏まえた収益・リスク管理態勢を整備しようとする取組みには、現在のところ各金融機関によって大きな差異があるのが実情であろう。 一部報道等から監督当局が民間金融機関の住宅ローン・ビジネスに対する注目の度合いを深めているとの兆しもみられていたところであるが、去る8月26日に金融庁から公表された平成23検査事務年度検査基本方針においては、住宅ローンのリスク管理態勢整備等について重点項目とする旨が明記された。ここに至り、収益・リスク管理態勢の整備、高度化は喫緊の課題になったものと言えよう。 本講演では、住宅ローンの特性を改めて概観するとともに、特性に即した収益・リスク管理手法の在り方について、実務の前線に立つ講師らの立場から具体的に解説する。特に、住宅ローンに関連する各種の数理モデルについて、金融数理技術を活用した構築・検証と、それらの具体的な活用方法に焦点を当てることとする。 |
| 開催日時 | 2011-10-13(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関におけるロイヤルティ顧客の維持・育成 ~横浜銀行の事例を踏まえて~ |
| 講師 | 株式会社浜銀総合研究所 情報戦略コンサルティング部 副主任研究員 秋場 良太 氏 情報戦略コンサルティング部 研究員 大井 麻琴 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,600円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-10-13(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 航空機ファイナンスの実務と法的留意点 ストラクチャードファイナンス取引を中心に、近時の動向等を交えつつ |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 パートナー 渋川 孝祐 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 航空機ファイナンスはかつての日本型レバレッジドリースの時代より数多く組成されている伝統的な金融取引分野ではあるものの、特殊な物件を対象とする専門性の高い分野であり、複雑なストラクチャーが組まれることも相俟って、一般の金融取引と比して、その認識や理解が十分なものであるとは言いがたい。他方、世界的金融危機以降の景気低迷、航空業界を巡る経営環境の激変などから、航空機ファイナンスを巡る環境にも変化が予想されるところ、複雑なストラクチャーや近時の動向を含む留意点に対して正確な理解を得ておくことは、今後の実務対応のうえで一層有効であるといえよう。 本講演は、航空機ファイナンスの法務と実務につき、ストラクチャードファイナンス取引を中心に解説するものである。ストラクチャリングについて、市場の実情を踏まえて説明したうえ、担保実務やドキュメンテーションの上での留意点について実務に即して解説する。 |
| 開催日時 | 2011-10-12(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | クレジットカード会社の収益力革新 |
| 講師 | アクセンチュア株式会社 金融サービス本部 経営コンサルティング統括 エグゼクティブパートナー 中野 将志 氏 金融サービス本部 戦略グループ シニア・マネジャー 粟倉 万統 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,600円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-10-12(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 債権法改正を巡る最新動向と金融機関の実務への影響 中間論点整理の公表を踏まえて銀行、保険会社、証券会社等への影響を解説 |
| 講師 | 弁護士法人三宅法律事務所 パートナー 渡邉 雅之 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成21年11月から法制審議会民法(債権関係)部会が開催され、民法(債権関係)の改正についての審議が行われているが、同部会は平成23年4月12日に「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」(中間論点整理)を決定し、5月10日に公表するに至った。中間論点整理は6月1日から8月1日までパブリック・コメントに付されており、また、今後見込まれる同部会の議論の再開も注目されるところである。(7月28日現在) 中間論点整理の公表により、これまでの議論の内容が整理されたことで、将来的な実務への影響に対しては、いよいよ具体的な関心が高まってきており、また、今後の中間試案のとりまとめ、さらには法案の提出等に向けた動向にも引き続き注視が必要である。 本講演では、債権法改正に関し、特に金融機関(銀行、信託、生損保、証券等)への影響に絞り、債権譲渡、約款その他の実務への影響について解説するものである。 |
| 開催日時 | 2011-10-11(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険代理店等に対する当局検査と適切な管理態勢の構築 ~監督・検査方針等を踏まえて~ |
| 講師 | 東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,800円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-10-07(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社のオペレーション改革 ~財務的成果の飛躍的創出~ |
| 講師 | ベイン・アンド・カンパニー パートナー 金融プラクティスグループリーダー 長谷部 智也 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,400円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-10-07(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | メザニンファイナンスを含む買収ファイナンスの諸論点と最新実務 交渉上のポイントほか実務的論点を詳説、最先端の米国のプラクティスも踏まえて |
| 講師 | スキャデン・アープス法律事務所 金川 創 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 世界的金融危機後、ミドルマーケットを中心に徐々に回復してきた買収ファイナンス市場であるが、東日本大震災の影響もあり、この流れも、一時期スローダウンした模様である。しかしながら、震災後の混乱期脱出を機に、2011年下期以降、中長期的には、再び回復基調を辿ることが予想される。 かかる中、買収ファイナンスの組成実務においては、日本を取り巻く昨今の経済状況を踏まえ、関係者間の利害調整等の複雑さが以前にも増して増加することが予想される。また、リーマンショック後の経験を踏まえ、将来のリストラクチャリングの可能性をも視野にいれる必要性が高まっており、マーケット復活後、実務面での新たなイシューとして、その対応方法が新たに検討される可能性も高い。一方、米国においては、買収ファイナンス市場が2010年以降急速に回復するなか、リーマンショック後の多数の経験に基づく新たなプラクティスやメカニズムが、大型案件を中心に開発され、ミドルマーケットにおいてもホットイシューとして浸透しつつある。従って、マーケット回復後の日本の買収ファイナンス実務を考えるにあたっても、特に、国外からのスポンサーやレンダーが参加する案件へ関与する場合、米国の最先端の実務知識は大いに参考となるものといえる。 本講演では以上のような背景から、買収ファイナンスにおいて、スポンサーサイド、レンダーサイド双方にとって交渉上重要なポイントとなりうる重要論点(特に、関係者間の利害調整の複雑さから高度なビジネス判断を要求される事項)を中心に、米国の最新実務動向も踏まえて解説する。特に、コミットメント・レター発行段階における融資実行の前提条件設定方法、メザニンファイナンスにおけるシニア・メズ・エクイティの利害調整、将来のリストラクチャリングの可能性を見据えた新たな条項の創設等に焦点を当てて詳説する。また、米国の最新実務動向の紹介においては、日本企業による米国上場企業の買収に際して実際に邦銀により供与された買収ファイナンスの特色への言及に加え、実際に公開されている最新のLBOファイナンス契約の条項をサンプルとした日本の買収ファイナス実務への応用可能性についても言及する。 買収ファイナンス分野において豊富な実績・知見を有する講師の経験も踏まえ、実務に即して具体的に解説を行うものである。 |
| 開催日時 | 2011-10-06(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | クロスボーダーM&Aのリスク・デューデリジェンス ~表明保証条項交渉上の注意点と表明保証保険の戦略的活用~ |
| 講師 | TMI総合法律事務所 淵邊 善彦 弁護士 マーシュブローカージャパン株式会社 バイスプレジデント 北代 泰久 氏 マネージングディレクター 木埜山 浩 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,000円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-10-06(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】多様な金融商品の時価評価 取引事例を用いた評価プロセス等を実務に即して解説 |
| 講師 | 有限責任あずさ監査法人 金融事業部 金融アドバイザリー部 ディレクター 佐上 啓 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講義は、金融商品の時価算定に関し、実際の商品を念頭に置いた評価について実務に即して解説することを目的とする。 金融商品の時価算定には現在、様々な評価モデルが存在し、なかでもブラック・ショールズモデルは、①原資産が多様であること、②わかりやすく解析解も多く存在すること、③市場においてもボラティリティがクォートされていること、等から実務的に広く用いられている。反面、このように汎用性はあるものの、モデルとしての制約も多く存在する。 本講義では、金融商品に係る実務に精通する講師の立場から、こうした実務面での特徴も踏まえつつ、様々な原資産(株価、為替、金利)の場合におけるブラック・ショールズモデルについて紹介したうえ、それらモデルを用いた評価手法について、実際の商品を用いた評価のプロセスを実務に即して解説することとする。 |
| 開催日時 | 2011-10-04(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険業界の構造変化とチャネル変貌 ~2011年度生保決算から見えてきたもの~ |
| 講師 | インスプレス 代表 保険ジャーナリスト 石井 秀樹 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-09-29(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 集合訴訟導入についての最新動向と分析 |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 カウンセル 石井 輝久 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,000円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-09-28(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | バーゼルⅢ導入に向けた銀行の投資・調達行動の変化 ~バーゼルⅢの国内適用とG-SIBsの動向も踏まえて~ |
| 講師 | 株式会社大和総研 金融・公共コンサルティング部 シニアアナリスト 菅野 泰夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,800円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-09-27(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 再生可能エネルギー事業と省エネルギー事業における制度・法律・スキーム・戦略 |
| 講師 | ランドブレイン株式会社 環境・社会システムグループ 主任 平崎 崇史 氏 株式会社スマートエナジー カーボンマネジメント部 シニアコンサルタント 丹羽 弘善 氏 高橋&デイビス法律事務所・外国法共同事業 弁護士 北村 一誠 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-09-27(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【特別企画】内部監査態勢高度化・効率化の最新実務 リスクアセスメント、オフサイトモニタリング等の最新動向、個別監査の高度化・効率化、最近の監査トピックについてベストプラクティスやケーススタディを交えつつ具体的に解説 |
| 講師 | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー 石塚 岳 氏 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー 長岡 茂 氏 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ マネジャー 小西 博和 氏 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアスタッフ 改発 恭子 氏 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ スタッフ 清水 さやか 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2011-09-21(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | クロスボーダーM&Aの具体的手法と留意点 加速する海外進出や法制度等の近時の動向を踏まえ、アジア進出における実務対応を中心に |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 パートナー ニューヨーク州弁護士 森本 大介 弁護士 西村あさひ法律事務所 ニューヨーク州弁護士 佐藤 正孝 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | グローバル化の進展とともに、日本企業による海外進出は増加の一途を辿っており、特に近時の円高により割安感が出てきた海外企業の買収案件は増加している。 特に近時目覚ましいのが日本企業によるアジアでのM&Aであり、直近の1年以内だけでも保険会社によるインド企業買収、製紙メーカーによるマレーシア企業買収、飲料メーカーによるベトナム企業の買収などが公表されている。円高基調に加え、東日本大震災が引き起こした調達網の寸断や電力不足等の深刻な危惧からのリスク分散、国内市場の低迷に伴う海外市場開拓等の要請から海外進出は焦眉の課題であり、アジア企業の買収もさらに加速していくものと考えられる。 しかしながら、クロスボーダーM&Aでは、当該国の外資規制や独占禁止法規制等様々な法制度に留意する必要があり、また、いざ紛争になった場合、紛争処理条項如何では希望する効果が得られないこともある。このように、クロスボーダーM&Aにおいては、国内M&Aとは異なる様々な留意点が存在する。 本講演では、クロスボーダーM&Aの実務に関し、特に日本企業が中国、ベトナム、インド、インドネシア、タイなどのアジアに進出する際の留意点を中心に解説する。特に留意すべき外資規制、独占禁止法規制、証券取引法規制等につき、アジア諸国各々により異なる特色や、当該国に特有の注意事項を踏まえて具体的に説明するとともに、2011年7月1日に一部改正法が施行された「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」の下での自社株対価TOBを利用した海外企業買収など、最近のトピックにも言及する。アジア進出案件を含む国内外のM&Aにおいて豊富な実績を有する講師らの立場から、近時の事案における経験等も念頭に置きつつ、最先端の実務に即して解説するものである。 |
| 開催日時 | 2011-09-16(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 損害保険大手3グループの戦略研究 ~統合マネジメントとマーケティングが決め手~ |
| 講師 | 経営企画研究所 代表 丹羽 哲夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,100円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-09-16(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】基礎から学ぶデリバティブ契約と交渉のポイント ドキュメンテーション等のポイント、その背景にある法的論点を交えて |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー ニューヨーク州弁護士 江平 享 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | デリバティブの契約書は、相当程度標準化が進んでいるものの、取引内容の複雑さや契約書の難解さから、その内容を正確に理解し、適切に交渉することは必ずしも容易ではない。また、標準化されているが故に、日常業務においては背景にある法理論や各契約条項の意図が意識されにくく、これらについて今一度正確な理解を得ておくことは有益であると思われる。 そこで、本講義においては、デリバティブの経験が必ずしも豊富でない実務家及び役職者や、基礎知識を体系的に整理・再確認したい実務家及び役職者を主な対象として、デリバティブ契約の基本的な内容とともに、実務に役立つ交渉のポイントについて解説する。その際、背景にある重要な法的論点については掘り下げた検討を行うこととし、また、デリバティブ契約に関する近時の議論や、近年仕組みが大きく変わったクレジットデリバティブのほか個別の取引類型についても適宜とり上げる。 |
| 開催日時 | 2011-09-15(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 日本におけるイスラム債の活用に向けた最新の法改正 イスラム金融の国内における発展を視野に、発行促進が期待されるスクークの仕組みや法的留意点などを解説 |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 月岡 崇 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | イスラム金融に対して非イスラム諸国も含むアジア、欧州等において積極的な取組みがなされ、イスラム債(スクーク)を含む取引が活発に行われている。わが国においても2008年の銀行法改正等から期待が寄せられていたものの、スクークに関する税務その他の問題が明確でなかったこと、金融危機による影響などから諸外国と比較して出遅れの感があり、一方で、最近になってわが国金融機関によるスクーク発行の事案等の各種の取組みもみられるほか、新たな資金調達手段等としてのイスラム金融への関心は高まってきている。 こうした状況のなか、2011年5月に、「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立・公布された。この法改正の内容は、イスラム金融に関する所要の税制措置を求めた平成23年度税制改正要望をうけて、資産の流動化に関する法律(いわゆる資産流動化法)や租税特別措置法の改正を行うことにより、資産流動化の応用スキームとして、特定目的信託の仕組みを利用したイスラム債(スクーク)の発行を促進するための改正を含んでいる。この法改正により、改正資産流動化法上の特定目的信託から生じる特定社債的受益権を用いたスクークの税務上の扱いについては通常の社債と同等となった。当該部分の改正法は2011年11月までに施行されることが予定されており、この法改正により、日本においても資金調達のためにスクークが活用されることが期待される。 本講演では、イスラム金融や、その一形態であるスクークの基本的な仕組みについて概観した後、上記改正法により日本で発行しうる特定目的信託を活用したスクークの仕組み及び法的な留意点を検討する。なお、改正法に纏わる政令や規則(2011年7月13日現在未公表)など、新たな動きがあった場合には、講演時点で入手可能な最新の情報に基づき、可能な範囲で言及することとする。 |
| 開催日時 | 2011-09-14(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 外国籍私募ファンドの法務と税務 ~種々のファンド形態に対応した論点の整理と検討~ |
| 講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 森下 国彦 弁護士 手塚 崇史 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,900円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-09-13(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ライフプラザホールディングスにおける銀行窓販戦略 |
| 講師 | 株式会社ライフプラザホールディングス 代表取締役社長 今野 則夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,700円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-09-13(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融ビジネスにおける事業継続マネジメント 進化するBCPとBCM、東日本大震災の教訓も踏まえて |
| 講師 | 有限責任あずさ監査法人 ビジネス・アドバイザリー事業部 シニアマネジャー 小林 到 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 東日本大震災から数カ月を経過し、停電リスク対応を含め当面の対応は一巡したと思われる。今、金融機関等に要求されるのは、課題の総括だけではなく、更に一歩進めた具体的なBCP(事業継続計画)の改善であり、BCM(事業継続マネジメント)態勢の再構築である。 つまり、地震、停電、感染症といったリスクが発現する度に、情緒的に反応するという行動パターンから脱却し、BCM態勢の評価軸を明確に定め、継続的に体質を強化することでBCPの実効性を高めることこそが求められている。 BCPの論点としては、在宅勤務、バックアップシステム、バックアップオフィス等の個別施策の検討だけでなく、「重要業務」、「リスクシナリオ」等のBCPの根幹に関わる項目についても再検討が不可欠であろう。 また、リスクシナリオに強く依存した旧来型のBCPを作り続け、いたずらに文書量を増やすのではなく、「リソース被害」や「業務停止時間」といった共通項に着目し、複数あるBCPを構造化することで、メインテナンス性と実効性の双方を向上させる取組みが求められている。 BCMの重要論点としては、テスト・訓練がある。リスクシナリオはあくまでの仮置きの想定に過ぎず、実際に発現するリスク事象は想定外となるのが必然であろう。BCPを構造化し、テスト・訓練で検証を行い、BCP自体の成熟度と組織の習熟度を向上させる取組みこそが「有事において使えるBCP」の鍵を握るのである。 本講演では、金融機関等のBCPとBCMに関して豊富な経験を有する講師の立場から、東日本大震災の教訓を踏まえ、重要業務の選定アプローチ、個別方策の課題と具体的な改善策、BCPの実効性に対する評価、テスト・訓練の具体的な実施方法等の論点につき、参考事例や監督指針・ガイドライン等との関係を交えつつ、BCPの改善及びBCM態勢の再構築について実務に即し、具体的に説明する。 |
| 開催日時 | 2011-09-12(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険募集を巡る取引法・監督法上の諸規制の最新動向と実務対応のポイント 銀行窓販に係る規制改正案の公表も含め、関係する諸規制を包括的に考慮して検討 |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 足立 格 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は、保険会社はもとより保険募集人にとってなお最大の課題のひとつである「保険募集」に焦点を当てて、取引法及び監督法における諸規制につき、普遍的な論点から最新の議論に至るまでを取り上げたうえで、実務対応におけるポイントを解説するものである。 「保険募集」に関しては、そのものの意義が抽象的で「保険募集」に該当しない単なる広告・宣伝等との区別が不明瞭であるうえ、「保険募集」を行うに際しては、取引法・監督法上の様々な規制が網の目のように張りめぐらされているといっても過言ではない。とりわけ銀行窓販規制については、その内容が複雑であり、捕捉範囲を正確に捉えることが難しい。こうした事情から、銀行窓販を含め、「保険募集」を巡る各規制について、その最新動向と実務対応上のポイントを分析・整理しておくことは、なお有益かつ有用であろう。 本講演では先ず、取引法上の規制に関し、説明義務・情報提供義務・助言義務や、保険会社の賠償責任、代理店業務委託契約の解約・更新拒絶等について、保険業法上の規定、さらには、債権法改正に向けた最新の議論を含む留意事項を取り上げる。 一方、平成19年12月の銀行窓販の全面解禁から3年余を経過したところ、金融庁から平成23年7月6日、「銀行等による保険募集に係る弊害防止措置等の見直しについて」が、また、同7月8日には「『保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)』等の公表について」が公表されるに至り、パブリックコメント手続きに付されている(7月19日現在)。この保険窓販に係る規制の改正案の内容や、今後の実務等への影響について考察するとともに、平成23年4月以降の検査に適用されている改定検査マニュアルのうち保険募集管理態勢に関する部分にも着目して解説を行う。 なお、講演当日までに上記改正案に係るパブリックコメント結果の公表などの新たな動きがあった場合は、パブリックコメント手続きに対する金融庁の考え方等について、講演時点の状況に応じ、可能な範囲で言及することとする。 |
| 開催日時 | 2011-09-09(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 海外向けリース取引の実務 ~ 中国・ベトナム編 ~ |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 パートナー 杉山 泰成 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 36,000円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-09-09(金) 13:15~16:45 |
|---|---|
| セミナー名 | 信託受益権の売買等に関する実務と法的諸問題 信託に関する基礎知識から金融商品取引法・監督指針等への実務対応、最新動向まで |
| 講師 | 東京青山・青木・狛法律事務所 谷笹 孝史 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 現在、「信託」の制度は証券化・流動化取引を始めとする多くの取引に利用されており、金融機関に加えて、不動産会社など金融機関以外の会社も、信託受益権の売買等に関与する機会が増大している。信託受益権の売買等は金融商品取引法に基づく規制を受けるため、信託受益権の売買等に関与する者は、かかる規制への対応が不可欠となっているが、金融商品取引法制は、政令・内閣府令が複雑に入り組んでおり、また法令のみならずガイドラインやパブリックコメントへの回答等にも注意を払う必要があることから、その規制内容を完全に理解することは容易ではない。また、信託受益権の売買等に関与するためには、金融商品取引法のみならず、「信託」の制度そのもの及び信託法を含む信託関連法制についての理解も不可欠である。 そこで、本講演では、まず、「信託」の制度及び信託関連法制についての基本的な理解を確認する。その上で、信託受益権の売買等に関する金融商品取引法に基づく規制について、金融商品取引法施行後に積み重ねられた実務を踏まえて、留意すべきポイント等をできる限り簡潔に解説する。また、近時の金融商品取引法の改正等、最新の動向についても言及することとする。 |
| 開催日時 | 2011-09-08(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | バーゼルⅢの下における資本調達手段 コンティンジェント・キャピタルの仕組み、問題点等 |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 パートナー 斎藤 創 弁護士 西村あさひ法律事務所 芝 章浩 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は、バーゼルⅢにおける自己資本規制を概観したうえで、新たな資本の定義とその日本法上の意義を分析し、これを踏まえた今後の金融機関等の資本調達手段としてAdditional Tier 1商品及びTier 2商品(主としてコンティンジェント・キャピタル商品)について解説するものである。 バーゼルⅢに関し、2010年12月のバーゼル銀行監督委員会(バーゼル委)による最終文書(バーゼルⅢテキスト)の公表以降、バーゼル委の種々の公表文書によりルールが補足され、明確化されているところである。また、直近では2011年6月に中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ(GHOS)がグローバルにシステム上重要な銀行(G-SIBs)に関する措置について合意に至り、一方で、わが国でもバーゼルⅢの国内実施のための金融庁告示改正案が早ければ2011年内にも公表されることが見込まれている。(7月15日現在) バーゼルⅢにおける自己資本規制、なかでも所要自己資本比率と資本の定義の見直しは、各金融機関等の今後の資本政策等に既に大きな影響を与えつつある。このうち、新たな資本の定義においては、Additional Tier 1とTier 2の定義が特に複雑であり、今後の当局対応や商品設計を考えるうえで正確な理解が不可欠である。特に2011年1月の公表文書により元本削減条項または普通株転換条項が原則として必要とされ、今までにない資本調達、商品が必要とされており、また、GHOSやバーゼル委としても高い損失吸収力の要件を満たすためにコンティンジェント・キャピタルの使用を提唱し、これに係る見直しを継続することとしている。 以上のような状況を踏まえ、本講演では、バーゼル規制対応等のファイナンスに精通する講師らの立場から、コンティンジェント・キャピタルに関し、仕組みや問題点について既存の発行事例等も交え、法的側面から検討する。さらに、既存のTier 1商品及びTier 2商品の取扱いについても言及する。なお、今後(2011年7月15日以降)、コンティンジェント・キャピタルの重要なファクターであるトリガー条項に関する規制のほか、バーゼル規制等を巡る新たな動きがあった場合は、講演時点の状況により可能な範囲で反映させることとする。 |
| 開催日時 | 2011-09-07(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 米国発:最新金融ビジネスモデル ~先端金融事例研究と本邦金融ビジネスへの示唆~ |
| 講師 | グローバルリサーチ研究所 代表 青木 武 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,700円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-09-07(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 国際プロジェクトファイナンスの諸論点と新たな展開 クロスボーダーシンジケートローンの構造、パラレルデット方式を含む担保や保証を巡る留意点など |
| 講師 | ホワイト&ケース法律事務所 ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業) パートナー 洞? 敏夫 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 資源を海外に依拠し、産業の最先端での国際競争に経済の将来がかかるわが国にとって、国際プロジェクトファイナンスの意義は極めて大きいが、東日本大震災を経て今後のエネルギーの需給構造等における変化も取り沙汰され、また、資源やインフラその他の各分野の世界各地の案件において海外諸国との競争が激化するなかで、プロジェクトファイナンスの位置付けはさらに高まり、その実務面での対応もますます重要な、かつ、緊急の課題となるといえよう。 プロジェクトファイナンスの通常の資金調達手段であるシンジケートローンに関し、特にクロスボーダーのシンジケートローンにおいては担保の設定・管理等、複数の法制が関係する重要な諸論点がある。 本講演では、プロジェクトファイナンスの基本構造を踏まえた上で、リスク分担やローン契約の諸論点を説明し、プロジェクトファイナンスにおけるシンジケートローンのあり方、担保や保証を巡る留意点等について具体的に解説を行う。今後の実務対応のうえで着目すべき新たな視点として、クロスボーダーシンジケートローンの世界的なスタンダードであるLMA、APLAとの対比における日本型のシンジケートローンの特徴や、その今後の活用の可能性などに触れる。また、日本法上の手当てがなく、これまで論じられることが少なかったものの、欧米のプラクティスなどから注目を集めつつあるパラレルデット(連帯債権)方式にも言及する。多数の国際プロジェクトファイナンス案件の実績を有する講師の立場から、新興国等の案件における経験や実際の論点等も適宜念頭に置きつつ、実務に即して解説することとする。 |
| 開催日時 | 2011-09-06(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関の外部委託管理に関する態勢整備上の留意点 |
| 講師 | 東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,500円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-09-02(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融業界におけるコンシューマモバイルチャネルの活用戦略 ~銀行・証券・保険の事例を中心に~ |
| 講師 | 株式会社 野村総合研究所 情報技術本部 イノベーション開発部 上級研究員 藤吉 栄二 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,900円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-09-02(金) 9:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【特別企画】IFRSを巡る最新動向と実務への影響 リスク管理を中心に |
| 講師 | 新日本有限責任監査法人 金融部 パートナー 公認会計士 永野 隆一 氏 新日本有限責任監査法人 金融アドバイザリー部 プリンシパル 和合谷 與志雄 氏 新日本有限責任監査法人 金融部 エグゼクティブ・ディレクター 公認会計士 安達 哲也 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本企画は、国際財務報告基準(IFRS)を巡る最新の動きとともに、金融機関が直面している様々な国際的な規制環境(FSB、バーゼル銀行監督委員会、IOSCO)などが与える影響について、主として会計及びリスク管理の観点から考察するものである。 まず、主としてバーゼル銀行監督委員会による各種規制の概要及び導入スケジュールを概説し、それらが今後、銀行のバランスシートに与える影響や業務に与える影響を検討する。 また、IFRSにおける公正価値測定、金融商品の減損会計、ヘッジ会計等の取扱いと、リスク管理高度化、償却引当ほか実務に及ぼす影響について解説する。なお、国際会計基準審議会(IASB)による議論の進展、新たな基準等の公表など、最新の動きについては、講演時点の状況に応じ、可能な範囲で反映することとする。 |
| 開催日時 | 2011-09-01(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | サイバー攻撃の最新動向と企業が取るべき対策 ~頻発する情報流出事故・標的型攻撃にどう対処すべきか~ |
| 講師 | デロイトトーマツリスクサービス株式会社 パートナー 野見山 雅史 氏 シニアコンサルタント 岡林 正 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,500円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-08-31(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 社会保障・税共通番号制度におけるICカード活用の可能性 ~公共系ICカードの民間活用動向~ |
| 講師 | 株式会社電子決済研究所 代表取締役社長 多田羅 政和 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,100円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-08-30(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 犯罪収益移転防止法改正等を踏まえたマネー・ローンダリング対策の実務 リスクベース・アプローチによる顧客情報の取得・更新・活用のポイント等に焦点を当てて |
| 講師 | あらた監査法人 リスク・コントロール・ソリューション部 マネージャー 白井 真人 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 2011年4月28日に改正犯罪収益移転防止法が公布され、FATFの相互審査におけるわが国への厳しい評価等を契機とするこの法改正が、マネー・ローンダリング対策(AML)の実務にいよいよ影響を及ぼすこととなる。改正法では、金融機関等の特定事業者に対して、追加的な顧客情報の取得および更新など、いわゆる「ノウ・ユア・カスタマー(KYC)」全般の強化を求めている。その整備にあたっては、従来のような画一的な本人確認実務とは異なり、各金融機関等の実情に即した実務の構築が個別に必要となる点で、ハードルは極めて高い。KYCの変更は社内各部門の広範な業務・システムに対して影響が大きいことからも、規制の細則の公表後では十分な準備期間を確保できないおそれも指摘され、一部の金融機関では先行した取組みもみられるところ、早急に社内各部門を巻き込んだ検討に着手することが喫緊の課題である。 本講演では、AMLに関する豊富な実績を有する講師の立場から、他のKYC関連法規制も念頭に置きつつ、今般の改正法導入後を展望したリスクベース・アプローチによるKYCの実務、および求められる体制整備について、国内外の金融機関における先進的な取組みの事例をも交え、具体的に解説する。 |
| 開催日時 | 2011-08-29(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社、銀行等金融機関のための保険商品に係る銀行窓販規制の解説・実務対応 ~今般の弊害防止措置等の見直しを踏まえつつ、規制全般を再確認~ |
| 講師 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー 錦野 裕宗 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,300円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-08-26(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | “Twitter”国内でのビジネス活用事例と今後の展望 |
| 講師 | 株式会社CGMマーケティング 営業開発部 マネージャー 津田 一成 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,600円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-08-26(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品等の勧誘・販売活動に関する諸規制と的確な実務対応 最近の検査・監督の着眼点、規制対応の誤解、非対面販売における論点などを交えて |
| 講師 | 東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 投資家からの苦情を含む多様な情報提供を背景として、金融商品等の勧誘・販売活動に対する監督当局の関心は依然として高いものがある。顧客保護重視の監督方針の流れの中で、的確な勧誘・販売等の実務対応は不可欠のものといえよう。 そこで本講演では、最近の監督・検査や行政処分事例の分析を踏まえたうえ、規制対応の様々な誤解(勧誘の相手方、取扱い業務・商品、適合性規制・説明義務、顧客情報共有、インターネット・電話等の非対面販売などの論点)やそれらへの的確な対応を、実務的視点から解説する。 |
| 開催日時 | 2011-08-25(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 国際決済ブランドの最新動向と新しいスキームの展望 ~Visa,VisaEuropa,MasterCard,中国銀聯,SEPA、スマートフォン決済の現状と未来、わが国への影響~ |
| 講師 | ペイメントジャーナリスト 本田 元 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,300円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-08-25(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】多様なスキームから学ぶ不動産ファンドの基礎と実務上の留意点 |
| 講師 | TMI総合法律事務所 パートナー 成本 治男 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講義では不動産ファンドに焦点を当てて、今後、実務に携わろうとする実務家、及び、一定の実務経験を有し、網羅的な再確認を図る実務家を対象に解説を行う。 具体的なスキーム例をもとに、金融商品取引法に関する基本事項やその他の法規制のほか各スキームにおける実務上の留意点につき、また、組成、運用、Exitに至る各段階における留意事項などを解説する。さらに、ダブルTMKスキームなど、近時の法改正を踏まえた応用的なスキームについても紹介する。 金融危機から一定期間を経て、また、東日本大震災による直接的な影響も収束しつつあり、不動産ファンド投資やファンド向け融資等にもまた活発化の兆しがみられ、開発型案件への投融資やメザニン投資などに取り組む動きも現れてきている。 本講義は、このような多様な投資スキームや、今後注目すべき新たなスキームなどをもとに、講師の豊富な経験を踏まえ、実務に即して法律上の問題及び実務上の留意点を具体的に解説するものである。 |
| 開催日時 | 2011-08-24(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】企業価値評価と実務上の留意点 情報のレベルに応じた評価や評価レンジなどの現実的課題、ケーススタディを交えて実践的に解説 |
| 講師 | 株式会社マスターズ・トラスト会計社 ディレクター 塩澤 武 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | DCF法に代表される企業価値評価は実務の多くの場面において浸透しているが、近時の企業買収等の実情に鑑みても、価値評価を行っているつもりで実は意思決定に貢献していない評価が散見される。 真に実務において有効かつ的確な評価とは、評価手法に当てはめて得られた単一の結果を結論とするものではない。入手可能な公表情報に基づく予備的評価、さらに、デューデリジェンスを経た詳細な情報による、取引や交渉を見据えた評価など、M&A各フェーズにおいて可能な、また、必要とされる評価や、これにより得られる評価結果の意味合いは異なるものである。一般に、評価結果は一定のレンジをもって示されるのが通例であるが、これも社内説明や交渉に耐えうるレベルにまで試行錯誤と検討を重ねて昇華されるべきもので、単純に平均値等が採用されるものではなく、ステークホルダーに対する説明責任等の面から、レンジの意味合い等を正確に理解しておくことは重要である。 本講義は、DCF法に関する基本的理解を前提に、各種パラメータの意味やシミュレーションを通じたレンジの設定ほか、評価における留意点について数値例を含むケーススタディを通じ、実務に即した解説を行うものである。各フェーズにおける評価の位置付け、DCF法と他の手法との評価の比較と評価結果の決定、評価レンジの問題のほか、近時の実務においても関心の高い非流動性ディスカウント、買収プレミアム、合併によるダイリューション、さらには、評価結果の実践的な活用例として各種指標の企業買収後の投資管理への利用など、M&A等の第一線に立ち、企業価値評価に精通する講師により実践的に解説することとする。 |
| 開催日時 | 2011-08-19(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 海外進出の税務リスクマネジメント 近時の日本企業の戦略や東日本大震災後の環境からますます重要視される海外M&A等を念頭に |
| 講師 | 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース シニアマネージャー ドイツ税理士 天野 史子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 従来、日本企業の潤沢なキャッシュを反映し、その吐き出し口として海外M&Aが活発化してきた感があるが、最近の傾向として、より長期的な視野に基づく重点分野への選択的投資のひとつとしての日本企業による戦略的買収が増加しているように見受けられる。加えて、東日本大震災がサプライチェーンに深刻な打撃を及ぼすに至り、海外進出、海外M&Aはなお一層、重要な戦略的課題となるといえよう。 このような投資は、海外現地での長期的な活動を前提としているため、従来のようにタックスデューデリジェンスによる静的なタックスリスクの把握では不十分であり、よりダイナミックで長期にわたる継続的なタックスリスクの観察が必要となる。また、シナジーを最大化することが重要な戦略的買収ゆえに、既存の海外子会社との整理統合も重要な課題である。 本講演では、このような視点から、M&Aに始まる一連の海外投資に伴い発生する税務問題を鳥瞰的に取り上げる。 税務の主眼はコンプライアンスの担保であり、コンプライアンス違反によって生じるタックスリスクの最小化が最重要課題であるが、激化する国際競争の中で、それをさらに一歩進めた「実効税率マネジメント」が注目されている。連結ベースでの税負担を最小化する実効税率マネジメントの巧拙が、海外投資から生み出されるネットキャッシュを大きく左右し、コスト削減に大きな役割を果たす。一例を挙げれば、海外M&Aにより今後ますます日本本社は知的財産権の使用許諾により本社費用を賄わなければならないケースが増えると予測されるところ、配当源泉税と並んで使用料に対する源泉税は源泉地国によって大きく異なり、より有利なストラクチャーを組むことで税引前利益の二桁代の増加を達成することも可能である。こうした様々な実効税率マネジメントのためのアイディアに関し、応用可能な基本的な思考パターン、その際のリスクや留意点などについて具体的な例示も交えて解説する。 |
| 開催日時 | 2011-08-10(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | リース会社の内部格付制度に基づく信用リスク管理の高度化 |
| 講師 | 株式会社浜銀総合研究所 情報戦略コンサルティング部 副主任研究員 秋場 良太 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,400円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-08-10(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険業界の未来像 |
| 講師 | 保険ジャーナリスト 鬼塚 眞子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,700円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-08-08(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | クロスボーダーシンジケートローンにおける実務上の留意点 各種の取引類型を踏まえ、条項例などを交えて具体的に解説 |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 パートナー 掘越 秀郎 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | シンジケートローンの総取引額は、国内マーケットが停滞ぎみであるのに対し、2010年のグローバルマーケットにおいては増加に転じている。特に米国及びアジアでの伸び率が目覚ましく、日本の金融機関による海外案件への取り組みは今後増加すると予想される。また、海外での事業展開を進める日本企業にとっても、海外におけるシンジケートローンは有力な資金調達方法の一つであり、多様な金融機関との取引関係を構築・拡大するためのツールとも捉えられる。 日本企業と外国企業との間のクロスボーダーシンジケートローンに取り組む際には、国内シンジケートローンとは異なる実務慣行、外国法が絡んでくる契約書及び海外取引特有のリスクに関する理解が重要となる。 本講演では、このような近時の状況、及びクロスボーダーシンジケートローン特有の問題に鑑み、具体的な各種の取引類型を踏まえた上で、普遍的な論点から近時ますます重要性の高まる論点に至るまで、英文条項例なども交えて実務に即して解説する。 |
| 開催日時 | 2011-08-05(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 楽天とSBIの金融戦略研究 ~巨大なプラットフォームと異なるビジネスモデル~ |
| 講師 | 経営企画研究所 代表 丹羽 哲夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,400円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-08-04(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | IFRS導入による信用評価モデルへの影響 |
| 講師 | スタンダード&プアーズ リスクソリューション部 ディレクター 坪倉 省一 氏 リスクソリューション部 アソシエイト ディレクター 谷口 峰子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-08-04(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 情報流出・情報漏えいを巡る法的リスク ソニーの情報流出問題等を契機に、今後さらに重要性を増す顧客情報流出に係るリスクや対応策を具体的に考える |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 パートナー 梅林 啓 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | ソニーの情報流出問題は、流出件数の膨大さもさることながら、ネットワークを通じて世界中の顧客にサービスを提供するグローバル企業にとって、ハッカーによる外部からの攻撃によるものであったとは言え、顧客情報の流出が、いかに大きなインパクトを与えるかを、改めて認識させる事件であった。また、これまでも、三菱UFJ証券(当時)の顧客情報の持出・売却事件をはじめ、従業員による不正な情報の持出・漏えい事例は後を絶たない。 一方、情報の流出に悩まされるのは企業ばかりではない。昨年来大きく報道された、警視庁の内部資料とされる国際テロ捜査の協力者の情報がネット上に流出した事件、海上保安庁の職員が尖閣諸島沖で発生した中国漁船衝突事件の映像をYouTubeに公開した事件、ウィキリークスによって米国の軍事情報や外交情報等の機密文書が公開された事件などは、捜査機関や国家の保有する秘密情報ですら簡単に流出してしまうこと、一度流出すると取り返しのつかない深刻な問題を惹起することを印象づけた。 このような情報流出を起こした組織は、それが、組織内の人間による意図的な行為の場合であれ、外部の人間による不正な侵入行為による場合であれ、様々な刑事上、民事上の法律問題に直面するとともに、情報保有者としての信頼を失い、場合によっては、組織の根幹を揺るがしかねないリスクを背負うことになる。 本講演は、元東京地検特捜部検事であり、情報漏えい等を含む企業の危機管理分野において豊富な実績を有する講師の立場から、主として顧客情報ほか個人情報の流出を念頭に、企業が晒されるリスク等につき具体的に考察、検討するものである。 具体的な事例に言及しつつ、顧客情報が流出した企業の抱えるリスクについて、個人情報保護法上の問題、民事上の損害賠償責任、会社法上の責任を含む法的問題を様々な角度から客観的に分析するとともに、事後の対応策や今後の防衛策についても言及する。 |
| 開催日時 | 2011-08-01(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 外国籍ファンドの組成・販売実務と多様な販売チャネルへの対応 |
| 講師 | ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業) 三宅 章仁 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-07-29(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | モバイル金融・決済サービスの動向と今後の展望 |
| 講師 | 株式会社 NTTドコモ フロンティアサービス部 金融・コマース事業推進担当部長 江藤 俊弘 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,600円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-07-28(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | プロ投資家向けファンド業務と規制対応の留意点 ~適格機関投資家等特例業務を中心として~ |
| 講師 | 東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,800円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-07-28(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関における反社会的勢力対応の実務 ~全銀協の暴排条項改正と保険会社の反社排除態勢を中心として~ |
| 講師 | 鈴木総合法律事務所 鈴木 仁史 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,600円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-07-28(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 与信ポートフォリオ管理を巡る課題と新たな流れ 東日本大震災を踏まえた課題と今後の方向性、クレジットモニタリング手法の最近の高度化事例等を交えて |
| 講師 | NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社 取締役COO 杉本 好正 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 東日本大震災によって、国内企業はサプライチェーンの寸断等の多大なる被害を被っており、景気の先行きについて不透明感が強まっているところである。 金融機関の信用リスク管理について、今回の震災により明らかになったことは、調達→製造→販売を通じて相互に依存し合う企業の集中リスクに対する信用リスク管理体制が十分でなかったことである。また、震災前から指摘されていたもう一つの課題として、環境・エネルギー、医療介護などの成長分野、逆の衰退分野のクレジットモニタリングやデフォルト率の予測が実効的でないことが挙げられる。 こうした課題を克服するために、また、今後、震災(大災害)がもたらす信用リスクの変化を把握していくうえでも、従来の信用格付や業種分類ではない新たなクラスタベースのポートフォリオ管理手法を確立することが急務である。 本講演では、信用格付や業種による従来型の与信ポートフォリオ管理手法(リスク計量化、プライシング、与信方針など)の問題点・課題を整理するとともに、クレジットモニタリングや与信ポートフォリオ運営手法における最近の国内金融機関の先進的な取組事例を挙げて、今後の信用リスク管理部署に求められる新しい信用リスク管理のあり方について解説する。 |
| 開催日時 | 2011-07-27(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | クラウドサービスの法的留意点と大災害発生時に企業が取るべき対策 ~企業の不可抗力マネジメントとビジネスの継続~ |
| 講師 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 GTS事業 GPS事業部長 弁護士 名取 勝也 氏 ブレークモア法律事務所 パートナー 弁護士 平野 高志 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,000円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-07-27(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 債権法改正「中間的な論点整理」と金融実務・取引実務への影響 現在の実務の法律的な根拠を再確認するとともに、来るべき債権法改正に備える |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー ニューヨーク州弁護士 東京大学法学部非常勤講師 民法 青山 大樹 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 法制審議会民法(債権関係)部会が、2011年5月10日、「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」を公表した。これにより債権法改正の議論は一つの区切り目を迎え、今後は、いよいよ中間試案を経て法案の取りまとめへと向かうこととなる。 中間論点整理では、多くの重要論点について、実務に重大な影響のある改正案が検討の俎上に上っている。本講演は、法制審におけるこれまでの審議の内容を踏まえながら法改正の動向を検討するとともに、これらの法改正が実現した場合に現行の実務にどのような影響があるのかについて、中間論点整理の説明に留まらず金融実務等の具体的な場面に即して解説するものである。 法改正による実務への影響を検討することは、現在の実務がどのような法律的根拠によって立っているのかを再確認する好機でもある。そのような観点からも、中間論点整理の逐条解説に終始することなく、現行民法と実務との関係についても改めて確認することとする。 |
| 開催日時 | 2011-07-26(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】確率・統計の基礎と実務への活用 ケースを通じ、実務に必須の基礎知識を学ぶ |
| 講師 | 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ マネジャー 谷本 章浩 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講義は、実務における必須知識として確率・統計の基礎を解説するものである。 例えば数学モデル等を取り扱う場合など、実務において確率・統計の知識を要する場面は多くなっているが、その難解さが実務に対する理解の妨げになっている側面もある。一方で、金融機関ほか企業における意思決定やコミュニケーションとしては当然ながら、数式や理論よりも直観的にわかりやすい説明が重視されるのであり、また、一見「高度」と捉えられているモデル等に関しても、高校数学程度の知識習得をより確実にすることで、相当に理解が深まることが期待できる。 本講義では、以上のような問題意識に基づき、まず、平均、分散、共分散、正規分布など、日常的によく用いられる指標や概念を基礎から、わかりやすいケースを例として解説する。そのうえで、実務への応用例として統計モデルやリスク管理をとりあげる。金融機関における実務経験を有し、リスク管理等の実務の最前線に立つ講師により、学問よりも実務への活用の視点から理論を説明するとともに、数式等を用いつつもわかりやすい解説を試みるものである。 |
| 開催日時 | 2011-07-25(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | リース業界の現状と今後の展望 ~銀行本体の参入解禁のインパクトを踏まえて~ |
| 講師 | 株式会社日本格付研究所 格付一部 チーフ・アナリスト 本多 史裕 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,500円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-07-22(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】TOBの基本的要点と実務上の留意点 最適な取引スキームの採用等のために、公開買付けの複雑な規制内容を改めて理解する |
| 講師 | 西村あさひ法律事務所 石﨑 泰哲 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 1971年に日本に導入され、1990年の制度改正により概ね現在の制度設計が固まった公開買付制度は、その後様々な事例を踏まえ度重なる制度改正を経て、現在に至っており、複雑な規制形態となっている。 他方で、その間に日本においても上場会社を対象とするM&A取引やMBOが活発に行われ、また、件数こそ多くはないものの敵対的買収も行われるようになってきており、これらの取引を行うためには、公開買付制度の適用の有無は避けては通れない論点となっている。しかし、公開買付制度が一般に広く認知されるようにはなったものの、その制度の要点を正確に把握し、その上で最適な取引スキームを採用することは取引担当者にとって依然として容易ではなく、取引コストを要することで、取引の円滑化を阻害する要因の一つとなっている。 さらに、近時の金融商品取引法の改正による公開買付制度における開示違反についての課徴金制度の導入、各種法的解釈に関する金融庁の積極的態度等から、公開買付規制違反への具体的リスクは格段に高まってきており、かかる観点からも公開買付制度の理解の重要性が増してきているといえる。 以上を踏まえ、本講義は、公開買付制度の基礎的な要点を広く概観し、同制度の趣旨や複雑な規制内容の正確な理解と、実務への的確な活用に資することを目的とするものである。 |
| 開催日時 | 2011-07-20(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 大規模災害を念頭に置いた債権管理・回収の最新実務と事業再生・倒産実務の最新動向 東日本大震災を契機に、主に債権保全と再生企業への投融資等の観点から |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー 山崎 良太 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 東日本大震災の発生後、日本経済・日本企業は未曾有の震災に伴う未知の諸問題への対応を余儀なくされている。金融機関、企業として、被災した取引先・投融資先や、震災の影響で経営不振に陥った取引先・投融資先に対する債権保全の必要性はもちろんのこと、今回の震災を契機に大規模災害発生時に生じる法律上・実務上の諸問題を見据え、債権管理や担保管理を見直す必要性が生じている。 また、今後の景気回復のためには、喫緊の課題である被災企業の復興にとどまらず、中小企業金融円滑化法によりある意味で停滞している経営不振企業の事業再生を進めていく必要があり、事業再生マーケットはさらに拡大・活発化することが見込まれる。債権者・投資家の立場からは債権回収の極大化を図るとともに、再生企業へ投融資等を積極的に行っていくために、事業再生・倒産実務の現状と今後の動向を理解する必要がある。 本講演では、東日本大震災を契機として、主に債権保全と再生企業への投融資等の観点から、大規模災害発生を念頭に置いた債権管理・回収の最新実務と、事業再生・倒産実務の現状と今後の動向について解説する。 |
| 開催日時 | 2011-07-15(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | スマートマネービジネス ~電子マネーとネット送金の新展開~ |
| 講師 | 株式会社野村総合研究所 消費財・サービス産業コンサルティング部 上級コンサルタント, Ph.D. 安岡 寛道 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,300円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-07-15(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | クレジットデリバティブの実務 |
| 講師 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 CPM部 クレジットマネジメントグループ 上席調査役 岩井 弘一 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,900円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-07-15(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 日本企業による香港上場の実務 SBIホールディングスによる香港上場の事例も参考に、実務的課題や法的留意事項を解説 |
| 講師 | スキャデン・アープス法律事務所 金川 創 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 広大なアジアマーケットでの知名度向上を通じて、中国を中心としたアジアでのビジネスチャンス拡大を図るとともに、比較的良好な市場環境における資金調達の便も考慮して、ここ数年、世界中の企業が、香港証券取引所での上場を目指す流れが続いている。その結果、香港市場は2年連続でIPO調達額世界1位の座を獲得し、企業成長を支える潤沢なリスクマネーを呼び込む市場として注目されている。現に、2011年5月には、米サムソナイトが10~15億ドルの資金調達を目指し香港市場での新規株式公開(IPO)手続に着手し、さらに、イタリアのファッション企業プラダも香港での上場を予定していると報道されている。 他方、日本企業についても、2010年10月に日本が認定法域に認定された後、2011年4月には、SBIホールディングスによる日本企業初の上場(セカンダリー上場)も実現しており、日本企業による香港上場に向けた環境整備も進んできたといえる。こうした状況に鑑みれば、SBIホールディングスの事例を参考としてセカンダリー上場を検討する日本の上場企業のみならず、香港でのIPOを通じて、アジアでの知名度向上や事業拡張を戦略的目標とする非上場会社や、投資先企業のExit戦略の一つとして香港IPOを検討中のPEファンド等にとっても、2011年以降の新しい有力な選択肢として、香港上場に係る最新事情と法的留意点を含む実務知識の把握は喫緊の課題といえよう。 このような事情を踏まえ、本講演では、SBIホールディングスによる香港上場事例における開示情報を参考に、香港上場の実務とその課題等を説明するとともに、日本企業による香港市場でのIPO手続を現に支援している講師の経験と最新の知見も踏まえて、日本企業による香港市場を通じたIPO(2011年4月時点において先例なし)において法律上留意すべき事項等についても、さらに踏み込んだ解説を試みる。 |
| 開催日時 | 2011-07-14(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 平成23年度商品先物取引法関連法令を中心とする近時のコモディティ・デリバティブ取引規制と実務対応 国際的な議論の動向等を含めて |
| 講師 | シティユーワ法律事務所 五十嵐 佳奈子 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 2008年の資源価格高騰を契機としたコモディティ・デリバティブ取引の規制強化に向けた国際的な流れ等を踏まえ、2009年、「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、本年1月1日全面施行された。これによって、国内取引所取引、海外取引所取引、店頭取引におけるコモディティ・デリバティブ取引について、横断的な規制が実施され、具体的には、事前の許可届出制度、外務員制度、勧誘規制等が導入されるに至った。本年7月には、外務員制度等の経過措置期間も満了し、本格的な制度の実施を迎えるところである。 商品先物取引法の施行により、これまで、事前規制が存在しなかった多くの取引が規制対象となること、金融商品取引法と異なる規制内容であること、社内体制整備等の新たな実務対応に迫られること等から、新たに規制を受ける金融機関や商社など事業法人系の関係企業等においては、その対応に試行錯誤が伴っているものと思われる。資源価格の高騰に絡み、コモディティ・デリバティブ取引がますます注目されるなか、今後のビジネス拡大に大きく関係する外務員制度など、本年7月からの本格的な制度の実施を控え、政省令を含む当該法律の内容の正確な理解と、これを踏まえた対応が緊急の課題であるといえよう。 本講演では、経済産業省において当該法律、政省令の改正案の立案に関与した講師の立場から、上記各制度の整備が行われるに至った経緯や政省令の具体的規定を踏まえ、コモディティ・デリバティブ取引における法的留意点を解説する。また、現在、一部のコモディティ・デリバティブ取引についての取引情報蓄積機関の利用の義務付けが国際的に検討されており、今後、国内における取引の規制の強化の動向が注目されるところ、こうした動きにも言及する。 |
| 開催日時 | 2011-07-13(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | IFRS、バーゼルⅢを踏まえた金融機関の経営管理・ALM運営の実務上の論点 |
| 講師 | NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社 ディレクター 田幡 和寿 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,100円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-07-13(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 国内インフラ投資に係る法的諸問題と最新動向 改正PFI法とコンセッションスキームの活用などを交えて |
| 講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 髙橋 玲路 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は、PFI案件その他インフラ関連案件において多数の実績を有する講師の立場から、国内インフラ投資の実務や法的問題点について、最新トピックとして注目の集まるPFI法改正も踏まえ、ファイナンスにおける留意点等も交えて解説するものである。 2011年5月24日、通常国会において「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(改正PFI法)が可決成立し、独立採算型のインフラ事業について、新たなコンセッション(公共施設の所有権を国や自治体が保有したまま、運営権を民間に設定する)スキームが導入される見通しである。この新たなスキームの導入により、空港、上下水道、有料道路などの主要な経済インフラの事業に対する民間投資が促進されることが期待される。 わが国のPFIは今後10年間で10兆円規模の市場を目指すとされているが、中でもコンセッションスキームは重要な位置を占めるものと考えられる。事業リスクを取るインフラ事業において、コンセッションへのエクイティ投資を促すためには、わが国特有の法制度との関係で正確な制度理解をし、適切なストラクチャリングを行うことは必須である。 本講演では、わが国のインフラ事業に対する投資全般に通じる法律上の問題点等を、改正PFI法の内容をも踏まえて解説する。また、主要なセクターに関する注意点や活用法、今後想定される案件についても展望することとする。 |
| 開催日時 | 2011-07-12(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ペイメント・サービスのビジネスモデル革新 ~情報通信技術がもたらす新たな可能性~ |
| 講師 | 一般社団法人 金融財政事情研究会 月刊『消費者信用』編集長 浅見 淳 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,900円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-07-08(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 不動産ファンドのシンガポール証券取引所(SGX)上場戦略 |
| 講師 | 有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー 東野 淳二 氏 スタッフ 野本 和宏 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,300円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2011-07-07(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【金融実務基礎講座】不動産ファイナンスと不動産ファンドの基礎 ファイナンスやファンド組成の基礎としてスキーム構築、契約関係、評価、会計・税務等について事例を交えて解説 |
| 講師 | 株式会社yenbridge 代表取締役 公認会計士 税理士 山下 章太 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講義は、今後の知識習得を目指す、あるいは、一定の経験を有するも体系的な知識の整理・再確認を図る実務家及び役職者を対象に、不動産ファイナンスや不動産ファンド組成の実務に必須の基礎知識として、ファナンス・スキームの構築、ヴィークルの特性、契約、評価、会計・税務処理等について実践的に解説するものである。 不動産取引や不動産担保融資取引が伝統的な実務として広く一般に行われてきているにもかかわらず、多様化・複雑化した各種ファンドスキームを含めて、そのファイナンスの仕組み、リスク、会計・税務等に対する理解が十分ではないまま、融資等が実行されている実情もあると思われる。 一方で、IFRS導入に向けて、上場企業の場合は時価評価や開示が必要となり、適切な不動産戦略をとらなければ投資利益率の悪化を招く懸念がある。加えて、リーマン・ショック以降は不動産価格の下落が発生したことも鑑みれば、リスク等に対する十分な理解と詳細な検討がなお一層重要となるといえよう。 こうした状況に鑑みれば、不動産ファイナンスに関しては、より精緻な、かつ、正確な理解に基づく実務遂行が求められるところ、これまでに書籍等も刊行されているものの総論や過去案件の解説を中心とするものが多く、実務に利用可能な知識習得は必ずしも容易ではない。 本講義では、以上の問題意識に基づき、金融機関におけるファイナンス実務に加え、会計監査、不動産鑑定評価、不動産ファンド組成等のアドバイザリー等の豊富な経験を有する講師の立場から、実例も交え、実務に即して解説することとする。 |
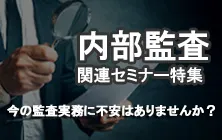
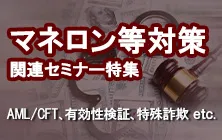
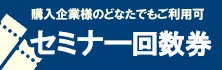
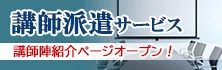
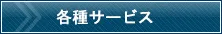
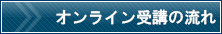

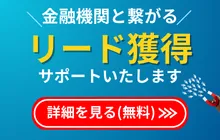
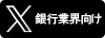


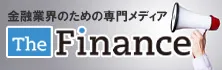
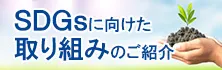
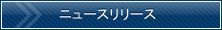
- 2025/12/17オフィス・カンファレンスルーム移転のお知らせ
- 2025/8/1創立20周年記念特設Webサイトオープン
- 2025/7/15株式会社グッドウェイとの業務提携について
- 2025/5/22申込規約改定のお知らせ
- 2025/3/19動画メディア「Finlink」オープン
- 2025/2/25動画メディア「PLACEY」オープン
- 2024/10/2「生成AIコース」開始
- 2024/7/12個人情報保護方針・Cookieポリシー改定のお知らせ
- 2024/4/23「(一社)金融データ活用推進協会」および「特定非営利活動法人金融IT協会」への加入のお知らせ
- 2024/4/3「LISTEN」に代表取締役社長小西のインタビューが掲載されました
- 2023/6/29セミナー累積開催数が5,000回を突破
- 2021/12/20「あしたのチーム HRアワード2021 優秀賞」を受賞
- 2021/9/1Webメディア「TheFinance」リニューアル
- 2021/8/6アクチュアリー試験対策講座の販売に関するお知らせ
- 2021/7/30受講票・請求書・領収証の送付方法変更のお知らせ
- 2021/5/13「講師派遣サービス」開始
- 2021/4/22 更新新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組み
- 2021/4/14「リバイバル配信セミナー」開始
© 1999-2026 Seminar Info Co.,Ltd. All rights reserved.