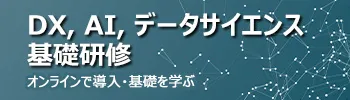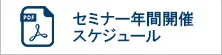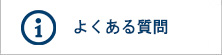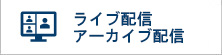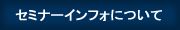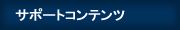|
|
 |
セミナー情報
SEMINAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報
過去に開催したセミナー5856 件中 4801 ~ 5000件を表示します |
| 開催日時 | 2007-05-10(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 最近の違反事例にみる広告表示の留意点 |
| 講師 | 川越法律事務所 弁護士 弁理士 高橋 善樹 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,700円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-05-10(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 事業承継対策の一環としてのM&A その実態と実務上の留意点、金融機関の収益源などとしての可能性を視野に |
| 講師 | 株式会社ストライク 代表取締役 荒井 邦彦 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 2006年の日本企業のM&A件数は史上最高となり、特に大型案件に高い関心が寄せられる一方で、今後の成長が見込まれる中小企業のM&Aも漸く注目を集めつつある。 事業承継が大きな課題となるなかで、その対策の一環としてM&Aが積極的に活用され始めており、中小企業のM&A市場にはさらなる成長が期待される。一方で、中小企業では所有と経営が一致していることの功罪があるほか、親族関係者が経営に介入しようとする思惑が働くなど独特の事情がある。 本講演は金融機関等の実務家を主な対象に、金融機関の今後の収益源などとして有望な中小企業のM&Aに焦点を当てるものである。その動向や特有の問題、税とスキームを中心とする留意点について、中小企業M&A仲介の先駆けとして市場の実情に精通する講師の豊富な経験をも踏まえ、実務に即して具体的に解説する。 |
| 開催日時 | 2007-05-09(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | かんぽ生命保険会社の戦略と銀行・保険会社への影響 |
| 講師 | 株式会社日本格付研究所 格付一部 金融グループ チーフアナリスト 格付企画部 ゼネラルマネジャー(兼) 水口 啓子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,000円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-05-09(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ロシアにおける未公開企業投資とM&Aの現状及び課題 マーケットの現状と法的スキームを中心に |
| 講師 | ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 UMJロシアファンドアドバイザー 大坪 祐介 氏 オリック・へリントン・アンド・サトクリフLLP オブ・カウンセル 外国法事務弁護士 セルゲイ・ミラノフ 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 自動車産業を中心とする大手日本企業のロシア進出が相次いでいる。 エネルギーをはじめとする天然資源に恵まれ、国内消費市場が急速な発展を遂げるロシア市場は、わが国の企業にとって新たな収益機会として注目が高まりつつある。 本邦企業がロシアに進出する際、従来はグリーンフィールドからビジネスを立ち上げることが一般的であったが、ロシア市場の成長スピードに追いつくためには現地企業への資本参加、あるいはM&Aは有力な選択肢の一つとなりうる。 本講演では第一部として大坪がロシア市場における未公開企業投資の現状を概観し、ロシア市場のポテンシャルを確認した後、業種別の特徴、欧米企業によるディールの実例等を踏まえ、日本企業へのインプリケーションを考察する。 第二部ではミラノフがM&A取引成功の要となる法務デュー・ディリジェンスを中心に、ロシアでのM&A取引に携わる実務家が最低限知っておくべき事項について解説することにより、取引を失敗に終わらせることのないよう速やかに手続を進める助けとなる指針を提供することを目的とする。 |
| 開催日時 | 2007-05-08(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 私募ファンドのストラクチャリングにおける金融商品取引法対応 |
| 講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 伊藤 哲哉 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,700円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-05-07(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 投信・投資顧問会社向け監督・検査の最新動向と対応策 ~金融商品取引法への最新対応を含めて~ |
| 講師 | KFi 株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,500円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-04-27(金) 13:30~16:00 |
|---|---|
| セミナー名 | 主要先進国の郵政事業体の最新動向とわが国郵政窓口サービスの展望 ~窓口機能を通じた各種金融・関連サービスのチャネル戦略の可能性~ |
| 講師 | 日本郵政公社 経営企画部門 郵政総合研究所 プロジェクト研究部長 大江 宏子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,500円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-04-26(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 電子決済スキームの最新動向と各社の戦略 |
| 講師 | 株式会社野村総合研究所 金融プロジェクト推進室 上級コンサルタント 宮居 雅宣 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-04-25(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 欧米保険会社の最新動向と戦略 |
| 講師 | アクセンチュア株式会社 金融サービス本部 戦略グループ シニア・マネジャー 飯田 健作 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,900円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-04-24(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 日本における事業の証券化とリーガル・フレームワーク 「倒産隔離」達成のためのスキームと具体的手法 |
| 講師 | 西村ときわ法律事務所 齋藤 崇 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 近年、日本においても資金調達手法として「事業の証券化」(Whole Business Securitization)が注目を集めており、事業の証券化の手法を用いた案件も徐々に登場するに至っている。 もっとも、事業の証券化におけるリーガル・フレームワーク、とりわけ、事業の証券化を行う際に実務上特に問題となることの多い「倒産隔離」(※)(ないしは「準倒産隔離」)達成のための法的手法については、これまで必ずしも十分な議論がなされきたとはいいがたいと思われる。 本講演では、まず、事業の証券化の特徴について概観した上で、事業の証券化において「倒産隔離」を達成するためのストラクチャーと具体的な手法について解説を行う。 ※ここでいう「倒産隔離」とは、通常の証券化・流動化における「対象資産の、オリジネーターの倒産からの隔離」のみならず、「(オリジネーターを含む)関係当事者の倒産による悪影響が投資家に及びにくいこと」というかなり広汎な意味を持つ用語として用いている。 |
| 開催日時 | 2007-04-23(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融検査マニュアル全面改訂のポイント |
| 講師 | 金融庁 検査局 総務課 調査室長 天谷 知子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 10,500円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-04-20(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 外国籍私募投信と金融商品取引法 ファンド・ビジネスに関する規制環境との変化と実務上の問題点 |
| 講師 | 三井法律事務所 パートナー 猪木 俊宏 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演では、本年施行される予定の金融商品取引法(投資サービス法)について、外国籍私募投信を中心とするファンド・ビジネスの実務に関連する点の解説を行い、また、外国籍私募投信について、実務上検討する必要のある法的問題をとりあげながら、基本的概念を整理する。さらに、ファンド・オブ・ファンズやヘッジ・ファンドへの投資に関する規制や仕組みなどについても検討を行う。 |
| 開催日時 | 2007-04-18(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 新BIS規制を巡る動向とクレジット投資への影響 |
| 講師 | JPモルガン証券株式会社 クレジット調査部長 中空 麻奈 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 新BIS規制の本格導入を控えて金融庁よりQ&A等が順次公表され、金融機関においてはその対応が急務となっている。 本講演は、現状の銀行の取組みをも踏まえて新BIS規制を巡る動向を解説するとともに、欧米銀行の現状も交え、クレジット投資への影響について考察するものである。 信用リスクについては、実際のプロダクトのリスクウェイトについての考え方を具体的に検討し、また、オペレーショナルリスクなどについては実際の銀行の事例を参考とする。これにより、現状の問題を整理し、新BIS規制導入によりクレジット市場にいかなる影響があるのかを考察する。同時に、欧米銀行における新BIS規制導入のインパクトを検討し、実際に新BIS規制導入がいかなる影響を及ぼしたのかを考慮する。 |
| 開催日時 | 2007-04-17(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | M&Aを成功に導くビジネスデューデリジェンス BDDとバリュエーションを一体として実施しているか? |
| 講師 | アビームM&Aコンサルティング株式会社 代表取締役 岡 俊子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | デューデリジェンス(DD)には、財務・法務・ビジネス・ITなど様々な分野のものがあり、M&Aのディール遂行には不可欠のプロセスである。 M&Aの成功は、DDの成否にかかっているといって過言ではない。 DDは、ポストM&Aを睨んで実施され、DDの結果がバリュエーションおよび契約に適切に反映されることが重要である。 ビジネスデューデリジェンス(BDD)の役割は、「これまでに生み出した価値」から「これからの価値を生むしくみ」を洞察することである。その結果に基づいて「企業が将来生み出す価値」=企業価値が定量化(バリュエーション)される。 本講演では、現在の「価値を生むしくみ」が今後どのように変化するか、それが事業計画にどのように反映されるか、買い手が新たな経営者として入ることにより事業がどのように改善するか、テコ入れ投資によるバリューアップの有無、事業統合によるシナジー効果の定量化など、BDDの具体的方法を実務の面から解説する。 |
| 開催日時 | 2007-04-13(金) 13:30~16:00 |
|---|---|
| セミナー名 | 電子登録債権ビジネスの可能性 海外の参考事例などを交えて |
| 講師 | 株式会社日本総合研究所 調査部 金融ビジネス調査グループ 主任研究員 野村 敦子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 現在わが国では、電子登録債権制度の創設に向け立法化が進められている。電子登録債権とは、権利の発生から移転、資金化、消滅にいたるまでのプロセスが電子化された新しい類型の金銭債権で、企業が保有する売掛金等の金銭債権や金融機関の保有する貸付債権を電子化して、インターネット等を通じて取引可能とすることが検討されている。これまでは目に見えない概念的な権利であった売掛債権等が電子債権として可視化され、債権の管理や譲渡についても電子的な手段を用いて容易かつ円滑に行うことが可能になり、ファイナンス手段として売掛債権等の活用が広がるとともに、これを活用した新しいビジネスも登場するものと考えられる。 本講演では、わが国の電子登録債権制度の概要について解説するとともに、海外での類似の制度や参考となる事例の紹介、電子登録債権の登場が金融ビジネスや企業に与える影響などについて展望する。 |
| 開催日時 | 2007-04-11(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 信託法・信託業法改正の最新動向と金融実務への影響 金融商品取引法による影響などを交えて |
| 講師 | 東京青山・青木・狛法律事務所 ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所 外国法共同事業 パートナー ニューヨーク州弁護士 元金融庁総務企画局企画課課長補佐 細川 昭子 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 昨年、①大正11年の制定以来82年ぶりの信託法全面改正及びこれに伴う信託業法の見直しを含む関係法の整備及び②金融取引を横断的に整備する金融商品取引法が成立し、本年夏~秋には施行される予定である。 新信託法及びこれに伴う信託業法等の整備法は、流動化・証券化をはじめとする信託を活用した金融実務に対し多岐にわたって重要な影響を与えるとともに、セキュリティトラスト、事業の信託など新たな信託の活用可能性を高めることが予想される。また、金融商品取引法案においても、信託受益権一般がみなし有価証券として取り扱われたことから、信託を活用した実務に様々な影響を及ぼすこととなる。また、今般の改正とともに、新たな信託税制・会計についても現在検討が進められているところである。 そこで、本講演においては、昨年末から講演当日までに公表された最新資料(信託法及び信託業法の施行令及び施行規則の改正案を含む。)に基づき、新信託法・信託業法・金融商品取引法との相互関係や新しい信託の活用可能性を分析しつつ、今後の信託を巡る金融実務への影響及び施行に向けての対応策を検討したい。 |
| 開催日時 | 2007-04-10(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 匿名組合・LLC・LLPの仕組み・活用と税務・会計 施行後の活用事例・税務上の取扱い・留意点・最新動向を総合的に解説 |
| 講師 | 新日本監査法人 データバンク室 公認会計士 太田 達也 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 近年、組合などの事業体を活用した事業投資が活発に行われており、かつ、注目されている。不動産の流動化スキームでは、匿名組合方式が多く用いられているし、そのほかにもベンチャー投資、レバレッジド・リース、投資ファンドなどに幅広く活用されている。 また、会社法では合同会社(LLC)という会社の内部関係が組合的規律であり、かつ出資者の責任が有限責任制である新しい会社類型が創設された。匿名組合出資を合同会社で受け入れるスキームが定着しつつある。 さらに、それとは別に、有限責任事業組合(LLP)が平成17年8月から施行され、共同事業や産学連携などへの活用がかなり進展している。 本講演では匿名組合、合同会社(LLC)および有限責任事業組合(LLP)について、その法的性格・仕組みと税務上の取扱い・留意点をよく整理したうえで、また、税制の最新動向をも踏まえて解説する。また、考えられる活用方法について、施行後の実際の活用事例を交えて詳しく解説する。 さらに、組合の連結範囲の取扱い強化や金融商品取引法の施行による影響などの最新の動向についても取り上げる。 |
| 開催日時 | 2007-04-09(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社向け監督・検査の着眼点と効果的な対応策 ~保険金支払い問題に関する最近の規制動向を含めて~ |
| 講師 | KFi 株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,200円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-04-09(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 信託受益権販売業の実務と法的諸問題 信託に関する基礎知識から証券化・資産流動化に関連する法的論点と実務対応、最新動向まで |
| 講師 | 東京青山・青木・狛法律事務所 谷笹 孝史 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成16年に改正・施行された信託業法により、信託受益権の販売につき新たに信託受益権販売業の登録が必要となった。この新たな規制により、実務上頻繁に行われている信託を利用した証券化・流動化取引その他の不動産取引の実務は大きな影響を受けており、また、これまで金融法に基づく規制とは関係が薄かった業態の会社による信託受益権販売業への参入も進んでいる。 信託受益権販売業を営む際には、「信託」という法制度や関係法令、信託業・信託受益権販売業等につき適用される規制などの知識が不可欠であるが、「信託」という制度自体が特殊なものであり、また適用される法律も多岐にわたり内容も複雑であることから、正確な知識の習得は必ずしも容易ではない。また、監督指針10-2-1の解釈を始めとして、証券化・流動化取引の実務上検討が必要な法的論点がいくつかある。さらに、平成18年12月8日に成立した信託法及び同年6月7日に成立した金融商品取引法の平成19年度内における施行が予定されており、これらの法律が、信託受益権の売買実務にさらなる大きな影響を与えることが予想される。 本講演では、まず、「信託」という特殊な法制度について概説し、その後、信託関係法令の概要及び信託業・信託受益権販売業につき適用される規制の内容について解説を行う。また、証券化・流動化取引において問題となる法的論点と実務対応について解説する。さらに、信託法及び金融商品取引法に関する最新の動向についても、信託受益権販売業の実務に与える今後の影響という点にポイントを絞って検討する。 |
| 開催日時 | 2007-04-06(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 来店型保険代理店の成功戦略 ~銀行保険窓販全面解禁への準備状況を含めて~ |
| 講師 | 株式会社オポチュニット 取締役営業部長 新村 純一 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,600円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-04-05(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 貸金業制度等の改革が消費者金融ビジネスに与える影響 |
| 講師 | 株式会社日本格付研究所 格付一部 チーフ・アナリスト 本多 史裕 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,400円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-04-05(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | クロスボーダーM&Aの税務上の留意点 三角合併の取り扱いを中心に |
| 講師 | 税理士法人トーマツ シニアマネジャー 税理士 橋本 純 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 2007年5月より、いよいよ合併等対価の柔軟化が解禁となる見込みである。 これにより、いわゆる三角合併が可能となり、国際的企業結合が促進されることになろう。 平成19年の税制改正は、この三角合併等について、一定の条件を満たした場合は課税の繰延を認める見込みであり、この内容について現時点で可能な限りの解説を行う。 上記以外に、アウトバウンド・ストラクチャー、インバウンド・ストラクチャーにおける主な税務上の留意点について、ポイントをあげて解説を行う。 |
| 開催日時 | 2007-04-03(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | アセット・マネージメント・ビジネスにおける金融商品取引法・改正投信法対応 |
| 講師 | 西村ときわ法律事務所 パートナー 伊東 啓 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,000円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-04-02(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 改訂金融検査マニュアルの実務対応 バーゼルⅡ対応を含めて |
| 講師 | 新日本監査法人 金融監査部 パートナー 公認会計士 茂木 哲也 氏 金融サービス部 シニアマネージャー 公認不正検査士 出塚 亨一 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,100円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-03-30(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 投資事業有限責任組合の実務と金融商品取引法対応 |
| 講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 伊藤 哲哉 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,400円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-03-29(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 巨大機関投資家の未来戦略 農林中央金庫の事例を中心に |
| 講師 | 経営企画研究所 代表 丹羽 哲夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,900円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-03-28(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 米国における確定拠出年金プランの新潮流 |
| 講師 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 マネージング・ディレクター 山本 誠一郎 氏 ディレクター 西野 正樹 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,900円(消費税・参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-03-27(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 電子マネー・ポイント等をめぐる法的問題と実務 |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 飯田 耕一郎 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,200円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-03-27(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | クロスボーダーのM&A 三角合併を中心に |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 税理士 ニューヨーク州弁護士 大石 篤史 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本年5月より、いよいよ三角合併法制が施行される。これまで最大の障害といわれていた組織再編税制についても、三角合併税制の導入により、問題がかなり解消される見込みである。実際に三角合併が利用されるケースも、十分に想定されるといえよう。 本講演では、まず三角合併の法制・税制を概説した上で、外国企業(又は日本企業)が実際に三角合併を用いて日本企業を買収する際のスキームと、その留意点を、可能な限り具体的に説明する。三角合併に先立ちTOBを行う場合も考えられるため、いわゆるエクスチェンジ・オファーを含めたTOBの留意点についても、併せて解説する。 また、クロスボーダーのM&Aに対する買収防衛のあり方や、金融商品取引法や外為法等の法規制についても、説明を加える。 |
| 開催日時 | 2007-03-15(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 平成19年6月総会の実務ポイント 会社法関係法令の全面適用を踏まえ、各種ひな型の解説とともに |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー 三浦 亮太 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成19年6月株主総会は、多くの3月決算の会社にとって、会社法・会社法施行規則に基づく事業報告・株主総会参考書類の作成を含め、会社法関係法令が全面的に適用される初の株主総会となる。また、関係書類作成等の検討が急務となっているところ、平成19年2月13日には日本経団連より「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」が公表された。 本講演では、平成18年株主総会を振り返りながら、運営等の実務ポイントを説明する。さらに、各種ひな型を踏まえながら、株主総会関係書類の作成の実務ポイントを説明する。 |
| 開催日時 | 2007-03-14(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関のこれからのCSR戦略 ブランド力強化などのために、ケーススタディを交えて |
| 講師 | 株式会社農林中金総合研究所 調査第二部 研究員 古江 晋也 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 金融機関は従来からメセナ活動をはじめとしたCSRを行ってきたが、これらは主に利益還元を念頭に置いたCSRであった。しかし近年では、社会貢献とビジネス双方の強化を図る「本業に組み込まれたCSR」を展開し、ブランド力やIRの強化など目的を明確化している金融機関が増加している。 本講演では、独自の調査結果をもとに、先進的な事例の解説等を交え、CSRの今日的なあり方について言及する。 |
| 開催日時 | 2007-03-12(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法が銀行・保険業務へ与える影響 |
| 講師 | KFi 株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,200円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-03-09(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 郵政ビジネスの新展開 ~ 社会ネットワーク分析の視点から ~ |
| 講師 | 日本郵政公社 郵政総合研究所 客員研究員 博士 (国際情報通信学) 大塚 時雄 氏 プロジェクト研究部長 博士 (国際情報通信学) 大江 宏子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,800円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-03-09(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 「企業通貨」を巡る最新動向と今後の展望 マイレージ、ポイント、電子マネーの現状とマーケティング及びアライアンス等のツールとしての可能性 |
| 講師 | 株式会社野村総合研究所 ソウル支店 アドバイザリーチーム グループマネージャ 上級コンサルタント 梶野 真弘 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 日本においてもポイントプログラムが定着してきたが、最近、電子マネーの出現により、ポイントプログラムと電子マネーが融合し始めた。また、通常、自社で閉じているポイントが、他社でも利用できるようになるなど、ポイント自体が流動性を帯びた使い方をされるようになってきた。野村総合研究所では、このような性格を持ったポイントプログラムを「企業通貨」と命名し、その定義や活用方法について調査・研究・提言を行っている。 本講演では、「企業通貨」を取り巻く環境や「企業通貨」市場の伸び、成功事例の紹介を通じて、実践的な「企業通貨」の戦略的活用方法について解説する。併せて、従来のポイントプログラム以外と併用すべき、新しい「第二のポイント」の提唱とその活用方法についても言及を行い、自社・他社も巻き込みながら、ダイナミックな顧客獲得・囲い込み方法について、解説を行う。 |
| 開催日時 | 2007-03-08(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 共済ビジネスの現状と今後の展望 |
| 講師 | インスプレス 代表 保険ジャーナリスト 石井 秀樹 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,700円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-03-08(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 新しい保険募集規制と保険金不払い問題への対応 顧客のニーズに合致した商品を販売するために |
| 講師 | あさひ・狛法律事務所 山本 啓太 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 今般、保険商品の販売勧誘ルールについて、重要事項説明の明確化(契約概要書面・注意喚起情報書面の導入)、保険商品が顧客のニーズに合致しているものかどうかを確認する書面(意向確認書面)の導入、比較情報の提供のあり方の見直しなど、今までの保険募集の方法を根本的に変更しなければならない制度が次々と導入されている。 そこで、本講演では、金融庁「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」に携わった経験のある講師が、新たな募集規制が導入された背景から規制の内容まで、具体的な解説を行う。 加えて、大きな社会問題となっている保険金等の不払いについても、その原因分析及び対応策を説明するとともに、検査重点事項とされている苦情等処理態勢について、苦情等を活用し、募集から保険金の支払いまでが適正に行われているかを把握するための仕組み等についても言及する。 |
| 開催日時 | 2007-03-07(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社におけるコンプライアンス |
| 講師 | 小笠原国際総合法律事務所 小笠原 耕司 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,600円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-03-07(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ABLの現在の動向及び課題と今後の展開 |
| 講師 | 日本政策投資銀行 企業ファイナンス部 調査役 松木 大 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成17年10月に動産譲渡登記制度が施行されてから1年が経過した。動産担保融資を含めたABL(アセット・ベースト・レンディング、流動性資産一体型担保融資)を取り巻く環境は、近時、法律の一定の整備、市場におけるプレーヤーの増加を受けて徐々に変化しており、漸く金融機関がABLに取り組む舞台装置が整備されつつある。しかしながら、一方で、黎明期であるがゆえに、制度上のみならず、実務上の課題も残されていることから、加速度的にABLが普及するまでには至っていない状態である。 本講演においては、ABLの概説に始まり、潜在的な市場規模、市場におけるプレーヤーとその特徴、融資実務上の主要論点、具体的な評価手法の事例、法的論点等の現在の動向・課題に適宜言及しつつ、これらの現状を踏まえた今後のABLの展望について解説を加える。 |
| 開催日時 | 2007-03-06(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 投信・投資顧問会社向け監督・検査の最新動向と対応策 金融商品取引法対応を含めて |
| 講師 | KFi 株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 証券取引等監視委員会への検査権限が移管されたが、その後も投信・投資顧問会社に対する厳しい監督措置が続いている。 そこで、投信・投資顧問会社に対する監督・検査姿勢、手法の変化を押さえた上、効率的・効果的な内部管理態勢整備のポイントについて解説する。 |
| 開催日時 | 2007-03-05(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 外国籍公募・私募投資信託に関する法的諸問題 ~金融商品取引法への対応も含めて~ |
| 講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 田中 収 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,100円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-03-01(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | M&Aに関連するインサイダー規制、金融商品取引法・取引所規則における開示規制 上場会社が関与するM&Aを念頭に、実務上の取扱い・注意点 |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 石塚 洋之 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 上場会社同士、または上場会社が当事者となるM&Aを行う場合、証券関連の法制度や証券取引所の規則等が複雑に絡み合い、当事者やアドバイザーにとって、やっかいな問題を提起することがある。近時、証券取引法が頻繁に改正され、金融商品取引法の施行も目前に迫っており、この段階で、現行ルールおよび今後施行されるルールについての知識を確認し、実務上の対応策について解説を行いたい。 本講演においては、まず、M&Aの取引において問題となるインサイダー取引規制について、具体的に事例を挙げて、法制度・違反した場合の罰則等を解説し、インサイダー取引規制に抵触しないのみならず、そのような疑念を懐かれないようにする方策について、適時開示の実務を踏まえて検討していく。また、資本提携の際に問題となる上場会社の有価証券届出制度について、解説し、金融商品取引法下での組織再編成についての届出制度についての解説も行う。最後に、M&A取引関係者が知っておかなければならない、改正後の大量保有報告制度での開示事項、強制公開買付制度について触れる。 |
| 開催日時 | 2007-02-28(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 私募ファンドの設定・運用における金融商品取引法対応 |
| 講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 伊藤 哲哉 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,100円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-02-27(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | EC企業による金融事業への傾斜 ~楽天とヤフーの競争が金融機関を巻き込む~ |
| 講師 | 経営企画研究所 代表 丹羽 哲夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,800円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-02-27(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | M&A取引における法務デューデリジェンスの実務 依頼者の立場から知っておくべき実務上のポイント |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 大久保 圭 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 近年M&A取引において法務デューデリジェンス(以下「法務DD」という。)が利用されることが一般的になっているが、法務DDを実施する目的や法務DDの結果の活用方法など法務DDの実務については、必ずしも十分に理解されていないことがある。これは法務DDの実務は各法律事務所のノウハウとして取り扱われ、これについて一般的に開示されることが少なかったことに起因するのであろう。 しかしながら、法務DDの結果は、M&A取引のストラクチャー検討や価格交渉を含むM&A取引のプロセス、さらにはM&A取引の実行の判断自体にも影響を及ぼしうる重要なものである。その意味で、法律事務所に法務DDを依頼する者の立場から見て、法務DD及びその結果を有効に活用するために、最低限知っておくべき法務DDの概要及び実務というものがあるのではないかと思われる。 本講演では、M&Aに携わる実務家が法務DDを依頼する際に最低限理解しておくべき法務DDの概要及び実務の知識について解説することにより、法務DD及びその結果を有効に活用するための基礎を提供することを目的とする。 |
| 開催日時 | 2007-02-26(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 新生銀行における日本版SOX対応プロジェクトの実動 ~ 取り組み事例に見るマネジメントの工夫 ~ |
| 講師 | 株式会社 新生銀行 CFO室 室長 兼 グループ財務プロジェクト部 バーゼルⅡ準備室長 吉田 美紀 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 32,500円(消費税、参考資料代含む) |
| 開催日時 | 2007-02-26(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 改訂金融検査マニュアル等を踏まえた内部管理態勢の実効的な見直し・強化 |
| 講師 | 新村総合法律事務所 行方 洋一 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 金融機関における内部管理態勢については、現行の金融検査マニュアル等を踏まえた体制整備が行われてきたところであるが、昨年12月26日に全編が公表され本年4月から適用となる改訂金融マニュアル(案)を踏まえた早急な見直し、また、業務の適正確保に係る内部統制システム構築の基本方針の決定等を義務化した昨年5月施行の会社法への対応、さらには、2008年4月から適用される金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に係る統制システムの構築作業など、金融機関における対応は、切迫かつ混迷しているように思われる。 そこで、本講演においては、金融機関および金融庁における実務経験を有する講師の立場から、金融機関における内部統制(内部管理)、および経営管理やリスク管理等の関連概念の整理をまず行い、次に、改訂金融検査マニュアル(案)をベースにした会社法等を含む一元的な内部統制システムの整備・確立に向けた方向性とこれを踏まえた現行システムの効果的・効率的な見直し・強化の着眼点を示したうえで、経営管理態勢、法令等遵守態勢および顧客保護等管理態勢において、その具体的内容を解説する。 |
| 開催日時 | 2007-02-23(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 医療法改正により医療法人制度はどう変わるか? 医療法施行規則、医療法施行令、厚生労働省告示を念頭に |
| 講師 | 東日本監査法人 会計士補 長 英一郎 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 医療法のうち医療法人制度は平成19年4月1日に施行される。改正医療法は拠出型医療法人を中心とする出資の払い戻しだけではなく、他にも重要な改正がなされている。例えば、監事の職務が明確化され、監事の責任が厳格となった。従来は名目的な監事を就任させれば済んでいたが、改正医療法施行後は責任を享受した監事の選任が必要である。また、医療法改正に伴う定款変更は、20年3月31日までに行わなければならない。所轄の都道府県からは定款変更につきどのような指導がなされるのだろうか。昨今は、特別な利益供与の禁止の是正を求めるケースもあり、その事前対応は不可欠である。 医療法人がこのような緊急の対応を迫られる一方で、金融機関を含む民間企業にとっても、監事の選任、定款変更、情報開示、附帯業務の拡大等に関しては、新たなビジネスチャンスを検討するうえで、また、融資先・取引先としての医療法人を理解するうえで極めて重要な意味をもつ。 本講演では改正医療法の施行を目前に控え、その概要を基礎に、医療法施行規則、医療法施行令、厚生労働省告示(平成18年11月16日現在未発出)の内容をも踏まえて、一人医師医療法人を含む全ての医療法人に影響を与える医療法人制度の改正について解説する。なお、政省令の内容等の最新情報については、講演当日までの状況に応じて可能な範囲で言及する。 |
| 開催日時 | 2007-02-22(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融ビジネスにおけるITを活用したマーケティング戦略 コスト削減から成長戦略に向けたIT投資へ、事例を交えて |
| 講師 | ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 プリンシパル 小塚 裕史 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | この数年来、IT投資はコスト削減が主目的に行われてきたが、景気の回復に伴い、成長戦略に向けたIT投資が積極的になされるようになってきている。金融ビジネスにおいても、それは例外ではなく、他社との差異化を図っていくためには、効率化の追求のみならず、新しい商品・サービスを投入していくことが必要となっており、そのためのシステム基盤の整備が急がれている。 例えば、銀行における投信・保険の窓販、新型の住宅ローン等による商品の追加、資産運用サービス、信託サービス、富裕層向けサービス等の新しい顧客サービスの追加により、販売方法が複雑となり、顧客管理も複雑なものになってきた。担当営業や窓口担当は、次々と新しい商品・サービスの販売方法を覚えなければならず、また、顧客の保有財産、保有商品の管理も複雑になりつつある。 さらに、コールセンター、インターネット、窓口業務、代理店営業など、販売チャネルが多様化するなかで、こういった一連の顧客情報をどのように管理し、それをどのように生かしてマーケティングへつなげて行くかが非常に重要となってきている。一方で、顧客向けへのマーケティング活動を活性化しすぎると、顧客からマイナスの評価を受けたり、情報セキュリティの問題が浮上することになってしまう。 本講演では、金融機関における商品・サービスの増加傾向、主要な成長戦略・マーケティング強化に向けたIT投資の事例を紹介し、金融機関が今後展開するマーケティング戦略と、ITをどのように活用するのか、について議論したい。 |
| 開催日時 | 2007-02-21(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | クレジット・デリバティブの最先端 市場動向から投資事例、規制を含む利用上の論点、今後の課題まで |
| 講師 | メリルリンチ日本証券株式会社 法人顧客グループ グローバル ストラクチャード クレジット プロダクツ ディレクター 矢島 剛 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 急速に拡大するクレジット・デリバティブ市場は、スワップ市場規模が約26兆ドル(2006年央)に達するなど、近年その成長が加速している。さらに金融機関や機関投資家にとっては、クレジット投資やヘッジの効率的なツールとして、ますますその重要性が高まっている。 本講演では、内外で関心の高まるクレジット・デリバティブ市場の最新動向について、市場の実態と、基本的取引から高度な商品に関する仕組みと特徴について、豊富な投資事例を交えて、平易に解説を行う。また、実務者にとって関心の高い、契約書のポイント、格付け、リスク管理、プライシング等、取引上の留意点を多様な観点から詳説する。さらに、新BIS規制後の投資家動向等について考察するとともに、クレジット・デリバティブ市場の課題、活用法について検討を加え、今後の展望を行う。 |
| 開催日時 | 2007-02-20(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 変額年金市場の現状とリタイアメント・マーケティング戦略 |
| 講師 | ハートフォード生命保険 代表取締役 セールス・マーケティング統括本部長 砂川 和彦 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,900円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-02-20(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 企業価値評価の実践 M&Aにおける価値算定及び買収価格交渉上のポイント、ケーススタディや最近の動きを交えて |
| 講師 | 株式会社KPMGFAS コーポレイトファイナンス部門ディレクター 谷口 進 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | M&Aが企業の戦略の一つとして一般化するにつれ、企業価値分析スキルも身に付けるべき一般スキルと言えるようになっている。 本講演では、M&A案件における企業価値評価実務に関して、特にDCF法に焦点を当て、価値算定のポイントおよび買収価格交渉上のポイントについて、ケーススタディを交えて解説する。また、企業評価実務における最近の動きについても説明する。 |
| 開催日時 | 2007-02-16(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ゴーイング・プライベートの法務と税務 TOB、キャッシュアウト・マージャー、LBO・MBO |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 税理士 ニューヨーク州弁護士 大石 篤史 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 近時、すかいらーく、キューサイ、東芝セラミックス、レックスホールディングスなど、ゴーイング・プライベート(株式の非公開化)を伴うMBOが増えている。 本講演では、ゴーイング・プライベートの実例を紹介しつつ、その手法としての公開買付け(TOB)やキャッシュアウト・マージャーについて、近時の法改正や実例を踏まえつつ、実務上の留意点を解説する。特に、新しい株式交換税制に対応するための各種ストラクチャーについて、時間を割いて説明する。 また、ゴーイング・プライベートを実施するためのLBOの手法(ローン・社債・種類株式等)や、MBOを行う際の実務上の留意点(経営陣のコンフリクトの問題等)についても解説を加える。 各取引に関する税務上の取扱いについても、随時言及する。 |
| 開催日時 | 2007-02-15(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 投資事業組合・信託・SPC・VC等の連結問題 新信託法を巡る最新の議論等を含めて |
| 講師 | 新日本監査法人 金融部 社員 公認会計士 橋上 徹 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 2006年は、ライブドアによる投資事業組合の問題からはじまり、通常国会で「金融商品取引法案」が成立・公布され、企業会計基準委員会から実務対応報告第20号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」の公表・中間決算からの適用、「信託法」(12月7日現在、臨時国会で成立見込み)、ベンチャーキャピタル条項への対応のための新連結基準の策定など、昨今の集団投資スキーム(ファンド)に代表される金融商品の多様化・複雑化に対応した、法や会計の整備が、急速に行われた年であった。 本講演は、2006年の上記の動きを振り返り、また、新たな流動化スキームとして注目される「自己信託」「事業信託」の会計・開示制度の動向について最新の情報を提供する。 |
| 開催日時 | 2007-02-09(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 機関投資家における分散投資の進化 時価配分からリスク配分への転換 |
| 講師 | ワトソンワイアット株式会社 コンサルタント 岡田 章昌 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 年金基金などの機関投資家における伝統的な資産運用では、株式や債券等複数の資産を投資対象として、一つの資産にリスクが偏らないように、時価金額(時価比率)を基準に分散投資が推進されてきた。 しかし、伝統的な分散投資では、ポートフォリオ全体での運用効率の追求が重視される一方で、個々の資産レベルでのリスク配分状況やリスクに対するリターンの見返りが明示的に意識されてこなかったことが実情といえる。この結果、十分に分散投資を推進していたつもりでも、株式等特定資産の影響を過大に受ける等意図せざるリスクの偏りが生じていることが多く、リスク配分の見直しによる運用効率の改善が課題となっている。 本講演では、ポートフォリオ全体の総リスク量の配分を基準にポートフォリオの運用効率を追求する「リスク・バジェティング」の考え方を紹介し、リスク配分を重視した分散投資戦略の実践方法を解説する。 |
| 開催日時 | 2007-02-08(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険の銀行窓販ビジネスと法規制 全面解禁に向けた法規制のポイント解説 |
| 講師 | あさひ・狛法律事務所 中原 健夫 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,300円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-02-08(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | シンジケートローンに関する法的論点と実務対応 ドキュメンテーション上の注意点、各種フィーの取扱など法的論点から、電子登録債権法制など最新動向まで |
| 講師 | 東京青山・青木法律事務所 谷笹 孝史 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | シンジケートローン市場は現在急速に拡大しており、国内企業の資金調達手段のひとつとして完全に定着したといえよう。しかしながら、アレンジャー・エージェントの法的責任、各種フィーの取扱(コミットメントライン法の解釈など)、ローン債権譲渡に伴う担保権移転手続など、実務上留意すべき論点が多数残されている。また、近時、アセットファイナンス、プロジェクト・ファイナンス、買収ファイナンスなどにおいてもシンジケートローンの手法が広く活用されており、また、担保付シンジケートローンの利用も広まってきているが、これらは伝統的な「運転資金のための無担保シンジケートローン」とは異なる特徴を有しており、契約書のドラフティングに際しても格別の注意が必要となる。 本講演では、シンジケートローンの概要・特徴等についてごく簡単に説明した後、JSLAベース契約書のドラフティングに際しての留意点、担保付シンジケートローンの特徴など、並びに、シンジケートローンに関する法的論点について解説する。また、電子登録債権法制、セキュリティ・トラスト、株券ペーパレス化など、シンジケートローンの実務に重大な影響を及ぼすこととなる最新の動向についても時間の許す限り説明を加えたい。 |
| 開催日時 | 2007-02-07(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | M&A、組織再編等における会社法の活用 種類株式、新株予約権等の具体的活用場面と論点整理 |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 前法務省民事局付 岩崎 友彦 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 「100年ぶりの改正」と言われた会社法も、急速に実務に浸透し、もはや施行に伴う実務上の変更への対応の時期は過ぎ、より積極的に会社法を活用することが求められている。株式や新株予約権の概念の整理や設計の柔軟化は、実務における会社法の活用を促し、また、企業結合・事業分離の会計基準の整備や、株式交換の税制改正などの周辺環境の変化も相まって、状況は刻一刻と変化している。 本講演は、法務省の担当官として会社法の立案作業を経験し、弁護士としてM&A等の実務に携わる講師の立場から、会社法下における各制度の実務への活用に関して解説を行うものである。上記のような状況を踏まえ、実務上想定される多くの場面を紹介したうえで、その背景と法的解説、さらに実務上の論点整理を行うことで、会社法を有効なツールとして活用するための方策を提示することを目的とする。 |
| 開催日時 | 2007-02-06(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険来店型店舗の増加と既存代理店への影響 |
| 講師 | 経営企画研究所 代表 丹羽 哲夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,700円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-02-06(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 新信託法とセキュリティ・トラスト 担保権信託の利用が想定される典型事例を踏まえて |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 水野 大 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 今国会において成立が見込まれている(11月17日現在)新信託法においては、担保権を被担保債権と切り離して信託するセキュリティ・トラストの適法性が明確化される予定である。 本講演では、セキュリティ・トラストに関する基本的内容を、セキュリティ・トラストの利用が見込まれる典型事例(債権者が単数又は複数のローンにおいて不動産抵当又は債権質を担保とする場合)を踏まえて説明する。また、セキュリティ・トラストについては新信託法制定によってその適法性が明確になってもなお実体法・手続法上、検討を要する事項が残っていることから、その点についても解説を行う。 |
| 開催日時 | 2007-02-05(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査」に向けて 「実施基準」公開草案と企業が対応すべき課題 |
| 講師 | 監査法人トーマツ シニアマネジャー 公認会計士 小池 聖一・パウロ 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成17年12月8日に金融庁企業会計審議会内部統制部会から公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準案」を適用するための「実施基準」の公開草案も平成18年11月21日に公表された。 しかしながら、当該草案には「監査人との協議」が必要な旨が記載されており、「実施基準」が確定してもなお、個々の監査人が適切な判断を行うためには日本公認会計士協会からの実務指針やQ&Aといった詳細な方針が定まるまでは、全体像は明らかにはならないと考えられる。そのような環境下でも、金融商品取引法では平成20年4月1日以降に開始する事業年度から内部統制報告書の提出を求めており、提出企業にとっては一刻も早い対応が必要となっている。 本講演では所謂"日本版SOX"への対応はあくまで内部統制の一部に対する評価・監査の要求であり、それがそのまま内部統制の整備・運用状況に対する十分条件にはならないという視点を維持しつつ、企業に現在着手が求められているであろう事項について解説する。 |
| 開催日時 | 2007-02-02(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法・金融検査マニュアルの改訂が金融検査に与える影響 |
| 講師 | 新村総合法律事務所 増田 英次 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,500円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-02-02(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | バイアウトファンドの実態と動向 内部経験者がその機能と最近の活動について詳説 |
| 講師 | ストラテジック キャピタル パートナーズ株式会社 マネージングディレクター CFO 水島 正 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 経営陣による企業買収(MBO)にとって、バイアウトファンドはなくてはならぬ存在である。昨年から今年にかけて、上場企業のMBOが起こった。ワールド、ポッカコーポレーション、すかいらーく、東芝セラミックス、そして、レックス・ホールディングス。MBOにより非上場化される上場企業が相次いでいる。 「経営者による」買収とは言うものの、買い手は実はファンドである。このようなディールの全貌について内部者が説明する機会は少なく、活動内容はベールに包まれた部分がある。 本講演では、既に、または今後ファンド投資を行う投資家、ファンド組成を検討している投資家や事業法人の実務家、MBOを志している経営者を対象に、大手バイアウトファンドのCFOとして経験豊富であり、現在は自身が、中堅中小企業を対象としたバイアウトファンドを運営している講師が、その希少な経験に基づいてファンドの投資活動の現状、市場環境の状況、ファンドビジネスの理想と現実について詳説するものである。 |
| 開催日時 | 2007-02-01(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 外国籍私募投信の最新法務 ~金融商品取引法・改正投信法への対応を含めて~ |
| 講師 | 東京青山・青木法律事務所 パートナー 小野 雄作 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,300円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-02-01(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法の下での投信投資顧問会社の法務 |
| 講師 | クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 宮川 賢司 弁護士 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 和田 圭介 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 2006年6月7日に証券取引法の一部を改正する法律案が国会で成立した。この法律は、証券取引法を金融商品取引法として全面的に改正し、投資顧問業法や金融先物取引法等を廃止して、金融商品取引法に統合し、投資信託及び投資法人に関する法律など多数の関係法令を改正するものである。 本講演では、金融商品取引法がいわゆるアセットマネジメントビジネス(投資顧問・投資一任業務及び投資信託委託業務)に与える影響を、①ライセンス規制、②行為規制、③開示規制に分けて解説をする。また、近時の投信投資顧問会社に対する行政処分などを検討したうえで、今後のコンプライアンス実務における留意事項についても検討を加える。 なお、講演当日までに金融商品取引法に関する政省令案の公表などがあった場合には、それらについても可能な限り言及する予定である。 |
| 開催日時 | 2007-01-31(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融業界におけるブランディングの本質と女性ターゲット攻略 |
| 講師 | 株式会社博報堂 ブランドソリューションマーケティングセンター ビジネス推進部部長 兼 シニアコンサルタント 博報堂買物研究所 シニアコンサルタント 岩崎 拓 氏 株式会社博報堂 博報堂買物研究所 研究員 牛田 奈緒子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | ブランドおよびブランド戦略は、マーケティングの世界で急速に拡大しているが、各種書籍では、ブランドについて多様な定義がなされており、誤解を生みやすい。博報堂は、ブランドを「企業(商品)と顧客の間に形成された長期的な絆」と定義している。広告だけでなく、商品、お店、店員、記事情報、ネットでの評判など、あらゆるものが、顧客との絆で重要になる。ブランド戦略は単なるイメージ戦略ではなく、多くの企業が全社横断型の活動でブランディングに取り組んでいる。 今まで、金融業界においては、商品・サービス自体に大きな違いは(仮にあっても)顧客には認識されにくく、店舗の立地や規模といったインフラ的要素の優劣で選択がなされていた。このような中でブランドは、基本的には企業グループや地域名等をベースした「のれん」イメージがあり、その微差競争で済んでいた。しかし、生活者の金融意識変化、経営環境等の変化の中で、顧客の心を捉えられなくなってきており、ブランディングは次のステップに進もうとしている。 今後はブランドの巧拙を分けるのは、ブランドの実践力であると考えられる。そこでのキーは、どう生活者の行動を喚起し、継続的な行動につなげていき、その中で関係を深めていくかという「行動」の視点が重要になって来る。情報やチャネルの環境変化の中、生活者の「行動」は大きく変化しているが、それを牽引しているのは女性である。ターゲットとしては勿論、ブランド選択への影響を与えるターゲットとしても女性を捉えることが重要課題となっている。本講演では、ブランド戦略の概論から、実際の実務の事例の説明に続き、女性の買物行動の特性やマーケティング事例、金融意識や行動の違いを中心に紹介した後、金融業界における今後のブランディングへの示唆までを提示する。 |
| 開催日時 | 2007-01-30(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 投資運用業における金融商品取引法対応 |
| 講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 伊藤 哲哉 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,000円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-01-29(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 会社法・金融商品取引法に基づく新しいM&A法制 |
| 講師 | 中央大学法科大学院 教授 森・濱田松本法律事務所 客員弁護士 野村 修也 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,800円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-01-29(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 信託受益権販売業の実務と法的諸問題 信託に関する基礎知識から証券化・資産流動化に関連する法的論点と実務対応、最新動向まで |
| 講師 | 東京青山・青木法律事務所 谷笹 孝史 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成16年に改正・施行された信託業法により、信託受益権の販売につき新たに信託受益権販売業の登録が必要となった。この新たな規制により、実務上頻繁に行われている信託を利用した証券化・流動化取引その他の不動産取引の実務は大きな影響を受けており、また、これまで金融法に基づく規制とは関係が薄かった業態の会社も含め、信託受益権販売業の登録者は500を超えるに至っている(平成18年10月10日現在)。 信託受益権販売業を営む際には、「信託」という法制度や関係法令、信託業・信託受益権販売業等につき適用される規制などの知識が不可欠であるが、「信託」という制度自体が特殊なものであり、また適用される法律も多岐にわたり内容も複雑であることから、正確な知識の習得は必ずしも容易ではない。また、監督指針10-2-1の解釈を始めとして、証券化・流動化取引の実務上検討が必要な法的論点がいくつかある。さらに、平成18年3月13日に国会に提出され同年12月8日に成立した信託法及び同日に国会に提出され同年6月7日に成立した金融商品取引法の平成19年夏における施行が予定されており、これらの法律が、信託受益権の売買実務にさらなる大きな影響を与えることが予想される。 本講演では、まず、「信託」という特殊な法制度について概説し、その後、信託関係法令の概要及び信託業・信託受益権販売業につき適用される規制の内容について解説を行う。また、証券化・流動化取引において問題となる法的論点と実務対応について解説する。さらに、信託法及び金融商品取引法に関する最新の動向についても、信託受益権販売業の実務に与える今後の影響という点にポイントを絞って検討する。 |
| 開催日時 | 2007-01-26(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法と証券化・流動化の実務 |
| 講師 | 三井法律事務所 猪木 俊宏 弁護士 パートナー 松島 基之 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,000円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-01-26(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 欧米主要金融機関のアジア戦略 アジア業務の再構築に取り組むわが国金融機関への示唆 |
| 講師 | 株式会社日本総合研究所 調査部 環太平洋戦略研究センター 上席主任研究員 国際関係論博士 高安 健一 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 邦銀が国際業務の再拡大を進めるなか、その重要な取り組みのひとつとしてアジア戦略の強化が挙げられるが、個人向け貸出、資産運用、富裕層ビジネスなどの各分野において欧米金融機関に押され気味であるのが実情である。 邦銀がアジア戦略を再構築するにあたり、国際金融市場で起きている変化、アジア金融市場の構造変化、そして勢力を急拡大している欧米有力金融機関のアジア戦略の3つは、必須の分析項目である。 本講演では、これら3つの要因について、欧米金融機関の取り組み事例を含め、基本的なファクト・ファインディング、統計整理、事例研究を行ったうえで、わが国金融機関の選択肢について述べる。 |
| 開催日時 | 2007-01-25(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | イーバンク銀行の新商品戦略 ~決済ビジネス分野の開拓~ |
| 講師 | イーバンク銀行株式会社 デビットカード事業構築プロジェクトプロジェクトマネジャー 井上 大輔 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,500円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2007-01-25(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ヘッジファンドの最新動向 戦略、仕組みと資金フロー |
| 講師 | マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 マネージング・ディレクター 白木 信一郎 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 近年、ヘッジファンド投資が普及するにつれて、世界の多くの機関投資家はそのポートフォリオの一部として投資を定着化させてきた。日本でも多様な投資家層にヘッジファド関連商品が提供され始めている。これまで銀行をはじめとする金融機関だけに限定されていた投資が、ここ数年の間に、年金基金、個人富裕者層、さらには一般の個人投資家層にまで裾野を広げてきた。 これら多様な投資家層への商品提供を行っているのは、主に信託銀行、国内外の証券会社、プライベート・バンク等であったが、最近では、銀行の窓口販売、オンライン証券会社を通じた商品も提供され始めている。 日本におけるヘッジファンド投資が本格化したのはおよそ10年ほど前であり、それ以来、ヘッジファンド投資戦略の多様化と共にストラクチャーも多様化してきた。日本の投資家にとって最もなじみのある投資対象はケイマン国籍の外国投資信託であることに変わりはないが、それ以外にも広範な選択肢が増えてきている。更に、元本保証商品、国内投資信託等の商品が増加しており、日本からの投資資金の経路が多様化しているといえる。一方で、景気の上昇局面に入ったとみられる日本の市場に対する投資も急増している模様である。これまでドメスティック・バイアスの強かった米国の100兆円規模の運用会社が2003年以降徐々に日本に対するアロケーションを増加させているのに加え、日本・アジアのみを対象としたヘッジファンド運用会社が日々新たに設定されている。これらの新たな運用会社は、日本国内のみならず、香港、シンガポール等に拠点を置くことが多く、MAS(Monetary Authority of Singapore)などもこれを後押ししている。 本講演では、ヘッジファンドの戦略およびストラクチャーの概要、ヘッジファンドが拠点を置くオフショア・センターの比較を行い、さらにヘッジファンドに対する資金フロー状況、日本の投資家の投資状況を考察する。最後に、日本市場に対するヘッジファンド関連の最近の投資事情をみることとする。 |
| 開催日時 | 2007-01-24(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 医療機関の買収とファイナンスに関する法的問題点 |
| 講師 | 西村ときわ法律事務所 パートナー 杉山 泰成 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 医療機関のM&Aを行う場合、取得の対象として、医療法人の社員持分を取得する方法に加え、医療機関の医療事業又は保有資産を取得する方法等が考えられる。しかし、医療法に基づく特殊な規制と医療法人の非営利性・公益法人性の要請から、医療機関のM&Aについては、支配権の取得方法や利益配当などの面で、一般の企業のM&Aとは別途の考察が必要となる。 本講演では、医療法人の基本的性格及び法令・指導上の諸規制に触れつつ、M&A戦略を検討する際の選択肢とそのメリット・デメリット及びストラクチャー組成上の注意点について概説する。また、LBO/MBO類似の形態が採用される場合にも配慮して、買収資金のファイナンスの種類(デット・エクイティ)における条件設定や担保取得における留意点についても説明する。 |
| 開催日時 | 2007-01-23(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 新しい公開買付制度のポイントとM&Aの実務 新TOBルールとその問題点及びMBOを中心とした実務への影響、図解やケーススタディを交えて |
| 講師 | 東京青山・青木法律事務所 ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所 外国法共同事業 パートナー ニューヨーク州弁護士 関口 智弘 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 改正証券取引法(金融商品取引法)では、新しい公開買付制度が盛り込まれており、これらの制度は平成18年内に施行される。この新しい公開買付制度では、従来の制度とは抜本的に異なるルールが導入されており、中には非常に複雑な規制も含まれている。上場会社の買収を検討する場合は、こうした新しい制度についてポイントを理解する必要がある。 そこで、本講演では、新しい公開買付制度の概要とその問題点について、図表を交えながら、重要なポイントを分かりやすく解説する。 また、昨今、上場会社を対象としたMBO(マネジメント・バイアウト)が注目されているが、新しい公開買付制度が上場会社を対象とするMBOに対してどのような影響を及ぼすのか、分析を試みる。さらに、新しい公開買付制度が今後のM&Aの実務にどのような影響を及ぼすか、弁護士の視点から検討を加える。 なお、実務動向、政省令の動向などの情勢の変化については、講演当日までの状況により必要に応じて言及する。 |
| 開催日時 | 2007-01-22(月) 13:30~15:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【特別企画】保険検査マニュアルの解説 内部管理、法令等遵守、保険募集管理、顧客保護等管理を中心として |
| 講師 | 金融庁 検査局 総務課 専門検査官 弁護士 梅澤 拓 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 金融庁は、2006年6月30日付で「保険会社に係る検査マニュアル」(保険検査マニュアル)を改訂した。保険検査マニュアルは、保険会社に対する金融庁検査の着眼点を示しており、検査の実態を知る手がかりとなるものである。 本企画では、改訂に携わった担当官の視点から、内部管理、法令等遵守、保険募集管理、顧客保護等管理の各態勢のチェックリストを中心にその内容を概説するとともに、今後の検査への影響などのマニュアルに関わる論点について解説する。 |
| 開催日時 | 2007-01-19(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 「新富裕層」マーケティングの課題と最新実践手法 新富裕層達の構図とライフスタイルを理解することが成功のカギ |
| 講師 | 株式会社ネットマイニング・ジャパン 代表取締役社長 株式会社エルドラド&パートナーズ 代表取締役会長兼CEO 鶴岡 謙吾 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | バブル夜明け前と言われる2007年を迎え、マスコミでは「新富裕層」というキーワードが踊っている。旧来型富裕層とは異なる価値観、消費特性を持つ新富裕層達は、金融関係、百貨店、老舗国内ホテル等の富裕層ビジネスを長年、展開してきた企業でさえ、囲い込めていないのが実情である。また、新富裕層の中には旧来型富裕層予備軍的な特徴を持つタイプがいる反面、どんなにリッチになっても決して旧来型富裕層の住む世界に足を踏み入れないタイプも存在し、新富裕層という一言で括ることはマーケティング戦略上、大きな誤りを犯す危険性を含んでいる。 本講演では、証券会社、投資信託会社、クレジットカード会社、不動産、リゾート会員権販売、教育出版サービス、流通・小売業など数多くの業界、企業の富裕層マーケティング、新富裕層マーケティングを支援してきた知見と新富裕層達の人的ネットワークの中心にいる講師の経験をもとに、マスコミでは紹介されることのない新富裕層の実態と、彼等・彼女達をターゲットにしたビジネスを展開するときに不可欠な視点を、実例に基づき解説する。 |
| 開催日時 | 2007-01-18(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ドコモの「おサイフケータイ」とケータイクレジット「iD」 最新の業界動向を交えて |
| 講師 | 株式会社NTTドコモ プロダクト&サービス本部 マルチメディアサービス部 iDビジネス戦略担当課長 江藤 俊弘 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 2004年7月より展開する「おサイフケータイ」は、今年度中に2,000万契約を突破する見通しとなり、携帯電話は"生活インフラ"という新たな成長局面を迎えている。 この市場環境の中で、2005年12月にドコモが満を持してケータイクレジット「iD」を開始、2006年4月にサービス開始したDCMXと併せて、クレジット業界に新風を巻き起こしている。本講演では、ドコモが「iD」事業に取り組むこととなった背景、そして現状と今後について、最新の業界動向にも触れながら解説していきたい。 |
| 開催日時 | 2007-01-16(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | コマーシャル・デューデリジェンス ターゲットの事業性と将来収益力を重視した調査分析の活用 |
| 講師 | 株式会社KPMG FAS シニアマネージャー 関口 美奈 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 日本のM&A市場は、「再生」や「救済」といった後ろ向きのイメージが強かったM&Aの時代を終え、これとは対照的な成長戦略の一貫としての前向きのM&Aの時代に突入した。多くの企業は、将来成長の糧となる経営資源の効率的且つ効果的な獲得を目的としたM&Aを模索している。これに伴い、買い手による投資判断基準は、純資産ベースから収益力ベースへと変化してきていることが伺える。従来から割引キャッシュフロー方式が採用される等、投資判断基準としての対象会社の将来収益力の重要性は認識されてきたが、対象会社が提示する将来プロジェクションの信憑性について買い手が客観的に調査分析し、独自の見解を形成した上で投資判断を行うことの重要性は従来になく増している。 将来プロジェクションは多角的に分析されるが、その中でも最も重要であるものの分析が難しいのが売上高予測の分析といえる。本講演では、ターゲットが提示する将来プロジェクション、特に売上高予測について、買い手が客観的な見解を形成するための調査である「コマーシャル・デューデリジェンス」のフレームワーク、情報ソースならびに分析アプローチを紹介する。また、コマーシャル・デューデリジェンスの具体的な効用について事例を含めて解説する。 |
| 開催日時 | 2007-01-12(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融サービス・ビジネスモデルの融合 |
| 講師 | ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 ディレクター・オブ・ストラテジー 金融サービスグループのリーダー 岸本 義之 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 金融機関はこれまで、業態別規制の範囲内で横並びの事業展開を行なってきたが、そのために、独自のビジネスモデルを追求するということはほとんどなかった。しかし、金融の中で業態別規制はほぼ緩和され、投信窓販、保険窓販、などの形で融合が起きてきている。 一方、証券仲介業、銀行代理店、信託代理店など、新たな提携関係を可能にする規制枠組みが実現してきている。これまでのように単一金融機関の中で業務が全て完結するというスタイルではなく、顧客獲得・応対をする組織と、商品供給をする組織とが別会社であっても構わないという、製販分離のビジネスモデルが可能になるのである。 これを契機に、小売業や通信業などの他業界でも、金融サービスの取り組みに意欲を示す企業が出てきている。セブン銀行やイオン銀行の構想、ドコモの電子マネーなど、新たなビジネスモデルを構築しようという動きが活発化している。 本講演では、既存の枠組みを超えた金融サービス・ビジネスモデルの融合に関して、どのような顧客ニーズを念頭に、どのような提供価値を、どのような組合せで提供していくことが可能なのかを議論したい。 |
| 開催日時 | 2006-12-22(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | リース業界の最新動向と業界再編をふまえた今後の展望 |
| 講師 | 株式会社日本格付研究所 格付一部 チーフ・アナリスト 本多 史裕 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,600円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2006-12-21(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 電子マネー・モバイル決済・ギフトカードなどリアル系電子決済スキームの最新動向と展望 |
| 講師 | 株式会社野村総合研究所 金融プロジェクト推進室 上級コンサルタント 宮居 雅宣 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,200円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2006-12-19(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 投信・投資顧問会社向け監督・検査の最新動向と対応策 ~金融商品取引法対応を含めて~ |
| 講師 | KFi 株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,000円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2006-12-18(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法・改正金融商品販売法に対応したコンプライアンス |
| 講師 | 小笠原国際総合法律事務所 小笠原 耕司 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,900円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2006-12-15(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ファンド・ビジネスと金融商品取引法 |
| 講師 | 三井法律事務所 猪木 俊宏 弁護士 パートナー 熊谷 真喜 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,100円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2006-12-15(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | COSOフレームワークに準拠した不正防止プログラムの導入と不正発見手法 米国における導入事例等を含む |
| 講師 | デロイトトーマツFAS株式会社 パートナー 公認会計士 公認不正検査士 霞 晴久 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 企業不正事件に関する報道は、連日新聞紙上を賑わしている。一方、2009年3月期より適用が予定されている経営者による内部統制評価と外部監査(いわゆる日本版SOX)の準備に余念が無い日本の上場会社にとって、不正の発見・防止を目指した内部統制の構築は喫緊の課題といえる。 しかしながら、現在進められている準備活動の実態は、内部統制記述書等の作成に力点が置かれ過ぎており、多分に形式的で、不正の発見・防止に向けた必要かつ十分な「不正防止プログラム」を設計・導入することに、ほとんど関心が払われていないように見受けられる。形式を整えるのはもちろん重要だが、有効な制度として社内に定着させるためには、制度に「魂」を吹き込む必要があろう。効果的な「不正防止プログラム」を導入することで、会社の内部統制がより充実するのは間違いない。 本講演では、不正問題を定義し、不正の発生事例をアンケート調査結果を基に解明しつつ、不正の動機について解明し、効果的な「不正防止プログラム」設計の考え方、米国における導入事例を検討する。さらに、不正問題が起きてしまった場合、内部監査部門等が実施すべき、不正の類型ごとの調査手続きについて解説する。 |
| 開催日時 | 2006-12-14(木) 13:30~15:00 |
|---|---|
| セミナー名 | 改訂保険検査マニュアルについて |
| 講師 | 金融庁 検査局 総務課 専門検査官 梅澤 拓 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 10,500円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2006-12-14(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | これからの金融機関の消費者ローン戦略 貸金業法改正、銀行本体のクレジットカードの発行等、激変する業務環境にどのように対応するか |
| 講師 | 株式会社日本総合研究所 調査部 金融ビジネス調査グループ 主任研究員 藤田 哲雄 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | リテール分野での収益力強化が課題とされるなかで、金融機関は消費者金融会社との提携などによって、消費者ローン市場への本格的な参入を模索している。 しかしながら、最近の債権回収業務における不祥事、グレーゾーン金利問題、過払い金返還訴訟の多発などによって、消費者金融会社の業務環境は不透明さを増しているほか、銀行本体によるクレジットカード発行が解禁されたこともあり、金融機関の消費者信用業務戦略を抜本的に見直す機運が高まっていると思われる。 本講演では、これらの環境変化要因を整理したうえで、金融機関の今後の消費者ローン市場を予測し、有効な業務戦略を検討したい。 |
| 開催日時 | 2006-12-13(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法におけるファンド規制と実務上の留意点・問題点 |
| 講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 花水 康 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 2006年6月7日に成立した「証券取引法等の一部を改正する法律」により、証券取引法は来年夏頃に金融商品取引法に改組されることが予定されている。金融商品取引法では、包括的な「有価証券」として、いわゆる「集団投資スキーム持分」が新たに創設されるとともに、その自己募集・投資運用について業規制・行為規制が適用されることになる。これらの一連の規制の導入により、プライベート・エクイティ・ファンド、ベンチャー・キャピタル・ファンド、不動産ファンドといった各種ファンドの実務にも影響が生じることが予想される。 本講演では、金融商品取引法の立法作業に従事した講師が、金融商品取引法のうち特にファンド(集団投資スキーム)に適用される各種規制について、証券取引法のもとにおける現行の規制と適宜比較しながら、その内容を解説するとともに、金融商品取引法の施行に向けて実務上の留意点や今後の見通しについても解説する。 なお、政令・内閣府令の動向等については、講演当日までの状況に応じて可能な範囲で言及する予定である。 |
| 開催日時 | 2006-12-12(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険販売の来店型チャネル戦略 |
| 講師 | インスプレス 代表 保険ジャーナリスト 石井 秀樹 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-12-11(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 生命保険会社に規制環境の変化がもたらす事業機会とリスク ~海外事情を踏まえた格付けアナリストの視点~ |
| 講師 | 株式会社日本格付研究所 格付一部 金融グループ チーフアナリスト 格付企画部 ゼネラルマネジャー(兼) 水口 啓子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,400円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2006-12-08(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | グループ内再編の会計実務 会計制度の理解と実務上の留意事項 |
| 講師 | 佐藤信祐事務所 所長 公認会計士 税理士 佐藤 信祐 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | さまざまな法制度の整備により、企業価値向上を目的としたグループ経営のためのグループ再編が活発化している。 会計面に関しては、「企業結合に係る会計基準」、「事業分離等に関する会計基準」、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」がそれぞれ公表され、組織再編における会計上の取扱いが明らかになった。 企業結合会計の導入というとパーチェス法と持分プーリング法の比較のみが注目されるが、子会社やその他のグループ会社との組織再編についても抜本的な改正がされている。 グループ内再編における会計上の取扱いについては、「共通支配下の取引等」として定められており、持分プーリング法に準じた会計処理を採用すべきであることが明らかにされているが、純粋な持分プーリング法による会計処理方法とは異なる部分も多く、かつ、会計基準、適用指針に難解な部分が多いため、実務上、かなり間違いが多い内容となっている。 そのため、本講演においては、企業結合会計基準、事業分離等会計基準のうち、グループ内再編における会計処理、すなわち、「共通支配下の取引等」に焦点を当てて解説を行う。 |
| 開催日時 | 2006-12-06(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社向け監督・検査対応のポイント ~保険金等支払い管理体制を含めて~ |
| 講師 | KFi 株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,500円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2006-12-06(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法等と企業内容の開示 四半期開示、財務報告に係る内部統制、確認書等の制度内容と具体的実務対応、米国SOX法との対比も踏まえて |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 ニューヨーク州弁護士 鈴木 克昌 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 金融商品取引法の施行により平成20年度より導入される四半期開示、財務報告に係る内部統制、確認書の各制度により、企業内容の開示は新たな局面を迎える。また近時の有価証券報告書の虚偽記載事件(西武鉄道、カネボウ、ライブドア等)及びインサイダー取引事件により、企業内容の開示に係る法的リスクが現実的なものとして認識されるとともに、企業内容の開示に対する社会的関心も高まっている。 本講演では、まず会社法、金融商品取引法、証券取引所規則による企業内容の開示の制度内容と内部統制、インサイダー取引、相場操縦、継続開示報告書の虚偽記載等との関係を有機的に整理する。次に企業内容の開示の中核をなす金融商品取引法に基づく開示・内部統制について、現行の証券取引法及び会社法並びに先行する米国のSarbanes Oxley Actとの対比を踏まえ、実務上問題となる点を検討する。さらに、MD&AやRisk Factorsを中心とする企業内容の継続開示の具体的な記載方法についても、実例に基づき検討する。 |
| 開催日時 | 2006-12-05(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険ニューチャネルの台頭と今後の課題 ~保険ショップブームの光と影~ |
| 講師 | ナカザキ・アンド・カンパニー 保険ジャーナリスト 中崎 章夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,700円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2006-12-05(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 会社法の下での種類株式の活用 ケーススタディを交えて |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 三浦 亮太 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成13年11月商法改正及び平成14年商法改正により種類株式に関する規制は緩和され、多様化した種類株式は上場・非上場会社を問わず広く利用されるに至っている。また、平成18年5月1日に施行された会社法においては、種類株式の内容に関する概念の整理がなされるとともに、種類株式の内容を検討するにあたって影響を与える周辺概念の変更もなされている。 本講演では、会社法のもとでの種類株式の設計、発行手続のほか、種類株主総会の要否や実務対応を含め、具体的な事例に基づくケーススタディを含めて検討する。 |
| 開催日時 | 2006-12-04(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 信託受益権販売業の実務と法的諸問題 信託に関する基礎知識から証券化・資産流動化に関連する法的論点と実務対応、最新動向まで |
| 講師 | 東京青山・青木法律事務所 谷笹 孝史 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成16年に改正・施行された信託業法により、信託受益権の販売につき新たに信託受益権販売業の登録が必要となった。この新たな規制により、実務上頻繁に行われている信託を利用した証券化・流動化取引その他の不動産取引の実務は大きな影響を受けており、また、これまで金融法に基づく規制とは関係が薄かった業態の会社も含め、信託受益権販売業の登録者は500を超えるに至っている(平成18年10月10日現在)。 信託受益権販売業を営む際には、「信託」という法制度や関係法令、信託業・信託受益権販売業等につき適用される規制などの知識が不可欠であるが、「信託」という制度自体が特殊なものであり、また適用される法律も多岐にわたり内容も複雑であることから、正確な知識の習得は必ずしも容易ではない。また、監督指針10-2-1の解釈を始めとして、証券化・流動化取引の実務上検討が必要な法的論点がいくつかある。さらに、平成18年3月13日に国会に提出された信託法案(平成18年10月19日現在未成立)及び同日に国会に提出され同年6月7日に成立した金融商品取引法の来夏における施行が予定されており、これらの法律が、信託受益権の売買実務にさらなる大きな影響を与えることが予想される。 本講演では、まず、「信託」という特殊な法制度について概説し、その後、信託関係法令の概要及び信託業・信託受益権販売業につき適用される規制の内容について解説を行う。また、証券化・流動化取引において問題となる法的論点と実務対応について解説する。さらに、信託法案及び金融商品取引法に関する最新の動向についても、信託受益権販売業の実務に与える今後の影響という点にポイントを絞って検討する。 |
| 開催日時 | 2006-12-01(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 第2次新規参入銀行の戦略シナリオ ~収益源の取り込みと固定客化~ |
| 講師 | 経営企画研究所 代表 丹羽 哲夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,000円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2006-11-30(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 郵政公社の新事業戦略 ~マーケティング分析の視点から~ |
| 講師 | 日本郵政公社 郵政総合研究所 プロジェクト研究部長 大江 宏子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 35,300円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2006-11-30(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社のコンプライアンス実務 行政処分事例、具体的事例、今後の留意点等を交えて |
| 講師 | 小笠原国際総合法律事務所 代表弁護士 小笠原 耕司 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 相次ぐ金融不祥事による金融庁による行政処分事例が後を絶たず、また、判例も消費者保護の流れのなかで金融業界に厳しい裁判所の判断が相次いでいる。 最近の保険会社を巡る事例をみるまでもなく、企業にとって不祥事は命取りであり、存続そのものを危うくするものである。 会社法の内部統制構築義務や、日本版SOX法、個人情報保護法、そしてさらには、より消費者保護色を強め、横断的に定められた金融商品取引法等のコンプライアンス実務をめぐる法改正・新法の制定もめまぐるしい。また、金融庁・保険協会等のガイドライン・保険会社に係わる検査マニュアル・保険会社向けの総合的な監督指針等の制定・改正も毎年の様に行われている。 本講演は、実務に即して、保険の販売勧誘・募集における説明義務や行為規制をはじめ、保険会社において法令遵守体制を具体的にどのように構築していけばよいかについて、最新判例・法律・そして行政の動向を踏まえて解説するものである。 |
| 開催日時 | 2006-11-29(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 新しい女性生活者・消費者像と金融機関のマーケティング ~女性の階層化と消費探求プロジェクト~ |
| 講師 | 株式会社 読売広告社 マーケティング局 第3MD部 マーケティング・ディレクター 平田 みどり 氏 第2MD部 マーケティング・プランナー 中山 舞 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 33,500円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2006-11-29(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 地方財政を巡る最新動向および地方債市場のリスクと今後の方向性 欧米諸国の制度、破綻事例等を交えて |
| 講師 | JPモルガン証券株式会社 クレジット調査部長 中空 麻奈 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 夕張市の財政破綻宣言後、地方自治体の破綻に向けて懸念が広がっている。しかしながら、こうした地方自治体の財政破綻問題が根本的に解決されることは難しい。そのため、地方自治体に対して、債券投資や融資という形で関わる場合のリスクは大きくなる一方であることが予想される。その反面、リスクを的確に把握することで地方債投資等において新たな機会の可能性も考えられる。 本講演では、こうした地方自治体関連のリスクの取り方について、考えていくこととする。まず、問題点の背景と現状を整理する。次いで、話題の地方自治体における破綻法制については、欧米諸国における破綻事例などを紹介することによって、日本の地方自治制度の考え方を浮き彫りにする。本講演はこうした考察を通じ、地方債や地方自治体の状況や環境の変化を踏まえて、「取れるリスク」と「取れないリスク」を明確に区別していくことを目的とするものである。 |
| 開催日時 | 2006-11-24(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法と投資運用業 |
| 講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 伊藤 哲哉 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,300円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2006-11-22(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法と外国籍私募投信 ~ファンド・ビジネスに関する規制環境との変化と実務上の問題点~ |
| 講師 | 三井法律事務所 猪木 俊宏 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | お一人様につき 34,800円(消費税、参考資料含む) |
| 開催日時 | 2006-11-22(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関における法令等遵守態勢の留意点及び改善・強化のポイント なぜ重大な法令違反等が発生し、長期間看過されてしまっているのか、行政処分事例の分析等を交えた実践的解説 |
| 講師 | 新村総合法律事務所 行方 洋一 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 金融機関における法令等遵守態勢については、自己責任原則のもと、各社による不断な取り組みはもちろん、当局による検査等により、一定水準の態勢が整備されていると思われる。しかしながら、行政処分事例や公表された検査指摘事項にも見られるように、依然として、遵守態勢の不備等に起因する重大な法令違反等が発生しており、また、違反等が長期間看過され、自主的改善に至っていないケースが多数認められている。 そこで、本講演では、金融機関及び当局における実務経験を有する講師の立場から、金融検査評定制度や監督指針の内容等も踏まえ、法令等遵守態勢及び個別・具体的な管理態勢の留意点等、また、行政処分事例の分析等を通じて、違反等の発生要因や背景及び態勢見直し・強化のポイントについて、実践的に解説を行う。 |
| 開催日時 | 2006-11-17(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 内部統制構築の具体的手順・手法と内部統制プロジェクトにおける組織運営 失敗に陥りやすい事例を交えて |
| 講師 | KPMGビジネスアシュアランス株式会社 シニアマネージャー デイヴィソン 貴子 氏 KPMGビジネスアシュアランス株式会社 マネージャー 稲木 淳子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | Ⅰ.内部統制構築の具体的手順・手法 昨今、相次ぐ企業不祥事及び昨今の急速な企業経営環境の変化を受けて、内部統制の議論が活発に行われるようになり、議論の活発化と共に、内部統制を巡る法規制の整備が様々な国で進められている。米国では、財務報告に係る内部統制の強化のため2001年に米国企業改革法(SOX)が制定され、また日本においては金融商品取引法が成立し、いわゆる日本版SOXへの対応が必要となってきた。本講演では日本版SOXに焦点を絞り、日本版SOXにおける内部統制のフレームワーク、財務報告に係る内部統制を構築するための具体的な手順・手法、多くの企業に共通する内部統制構築上の問題点および法規制対応上の課題等を解説する。 Ⅱ.内部統制プロジェクトにおける組織運営 財務報告に係る内部統制の整備は、各社ともプロジェクト・チームを設置して進められているが、プロジェクトを成功に導く重要な鍵は、プロジェクト事務局やプロジェクトコアメンバーのプレイング・マネージャーとしての組織運営力である。企業が本格的に取り組まざるを得ない課題である内部統制整備に対して、法規制に難なく対応しようとするのか、この機会を利用して組織運営力を積極的に磨こうとするのか、企業の力量が試されることになる。失敗に陥りやすい事例を交えて、どのように内部統制プロジェクトを運営していくべきかを解説する。 |
| 開催日時 | 2006-11-15(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | メザニン・ファイナンスの実務 |
| 講師 | 日本政策投資銀行 企業ファイナンス部 調査役 新美 正彦 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 日本においてもバイアウトの案件が増加する中、メザニン・ファイナンスを活用するケースも徐々に出始めている。また一方で、企業の成長ステージに併せて優先株や劣後ローンを導入する事例も見られるようになってきた。 企業の資金調達手段として従来型の銀行借入に加えて、普通株式による増資や、買収ファイナンスとしてのエクイティが一般化してくれば、中間的なリスク・リターンに位置づけられるメザニン・ファイナンスが普及してくるのは当然の帰結とも言える。 本講演では、エクイティ投資やLBOローン等の経験も踏まえ、メザニン・ファイナンスの特徴やリスク・リターンの分析、留意事項等を実務的な観点から解説する。 |
| 開催日時 | 2006-11-14(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 株式交換・移転の会計・税務 企業買収における留意事項 |
| 講師 | 佐藤信祐事務所 所長 公認会計士 税理士 佐藤 信祐 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成18年4月1日から企業結合会計が施行されたことに伴い、企業買収を行った場合に、ほとんどのケースがパーチェス法に該当することになった。そのため、株式交換・移転により企業買収を行った場合には、一部の例外的ケースを除き、パーチェス法に該当することから、営業権の会計処理をどのように行うのかについて留意が必要になってくる。 また、平成18年度税制改正により、株式交換・移転制度の大幅な見直しが行われ、税制適格要件を満たさない株式交換・移転については、完全子法人において時価評価課税が課されることになった。 そのため、今後の実務においては、会計上は営業権の計上が必要になり、税務上は時価評価課税のリスクがあることから、株式交換・移転がやりにくくなると言われているため、株式交換・移転の会計処理、税務処理を理解することは、企業買収を行う上で非常に重要になってくる。 本講演では、株式交換・移転における会計処理、税務処理の解説と、実務上の留意事項についての解説を行う予定である。 |
| 開催日時 | 2006-11-09(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | LBOがもたらすマーケットインパクトとは 投資機会とリスクを含む今後の趨勢を考える、欧米における実例及びLBO市場の最新動向と日本市場への示唆 |
| 講師 | JPモルガン証券株式会社 クレジット調査部長 中空 麻奈 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 株主圧力の増大に伴い、企業は株主価値の増大を図る行動を重視し始めている。こうしたクレジットサイクルの流れの中、日本市場においても、M&A、MBO、LBOが散見され始めた。とりわけ、負債金額が大きくなるLBOは、クレジット市場への影響が大きい。 本講演では、こうした市場についての投資機会を考え、今後の日本市場におけるLBOの動向について予測していくことを目的とする。 ニーマンマーカス、アルバートソン、ソフトバンクなど、多くの具体事例を見ながら、格付け機関の判断スキームの概要を解説、LBOがCDSや株式市場などマーケットに与えた影響、投資家のステータスやコベナンツの変遷などについて、そのインパクトを考慮する。欧米のLBO市場の最新情報のアップデートも試みる。 |
| 開催日時 | 2006-11-08(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法とM&A取引 |
| 講師 | TMI総合法律事務所 パートナー 中川 秀宣 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 今国会において、金融商品取引法への改組を含めて現行の証券取引法を段階的に改正する法律が制定された。同改正は、今冬の施行を予定している公開買付制度の再構築、来春の施行を予定している株式交換制度への公募概念の適用等を含む。 来春には、会社法下で先送りされていた株式交換や合併等での対価の柔軟化の解禁が予定されており、当事者の多様化とM&A手法・手続の多様化・柔軟化を睨んでの規制の整備という側面も有する。 これらの改正が、非友好的買収に対する防衛策やM&A取引の実務に与える影響は大きい。規制の細部については政省令の発表と税務面の整備をまたなければならないが、本講演では、これらの法改正の内容とその影響について包括的な解説を行うものである。 |
| 開催日時 | 2006-11-07(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 戦略的デューデリジェンスの実務 その意義及び手法から、発見事項と事業価値評価・契約条件、M&A後の統合・経営まで、事例に基づく解説を交えて |
| 講師 | 株式会社 KPMG FAS 代表取締役パートナー 知野 雅彦 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | M&Aの成功のためには、静態的で過去的な「伝統的デューデリジェンス」とは一線を画す、動態的で将来に向かった「戦略的デューデリジェンス」が不可欠となる。「戦略的デューデリジェンス」は、事業価値評価、シナジー評価、M&A後の統合や経営(PMI、PMM)をにらんだ、M&Aを真の成功に導くためのデューデリジェンスである。 本講演では、そうした「戦略的デューデリジェンス」の手法について、ビジネス、財務などの各種デューデリジェンス、さらには、発見事項と事業価値評価・契約条件などに至るまで、できるだけ実務を即した形で、実例等をふんだんに交えながら解説する。 |
| 開催日時 | 2006-11-06(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法が金融検査に与える影響 |
| 講師 | 新村総合法律事務所 増田 英次 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-11-02(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 無担保個人向けローン事業の動向と製販分離 |
| 講師 | 株式会社日本格付研究所 格付一部 チーフ・アナリスト 本多 史裕 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-11-02(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ロシア投資・進出を巡る現状と今後の可能性 基礎知識から最新動向、実務上の留意事項まで |
| 講師 | 三菱商事株式会社 業務部 ロシア・CIS担当次長 酒井 明司 氏 みずほ総合研究所 政策調査部 主任研究員 金野 雄五 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | いわゆる"BRICs"への注目が集まるなか、中国、インドに続き、ロシアへの関心が高まりつつある。 ロシア市場が急激な成長を遂げる状況下で、欧米諸国に比較して日本企業の出遅れも指摘されている。また、ロシアを巡っては、ソ連崩壊、98年の金融危機などの経緯もあって、多くの「神話」や「誤解」、そして何より情報不足の問題があるのが現実である。 法制度や政治経済といった側面に加え、ロシア国内でも地域、産業分野、さらには個別企業の間で大きな違いがあることなど、ロシアならではの特殊事情があり、日本企業が急成長するロシア市場において成功を収めるためには、こうした現状を正確に把握することが第一の課題であるといえる。 加熱するロシアビジネスにおいて日本企業のチャンスはどこにあるのか?他のBRICs諸国と比較した場合の特色あるいは魅力は?ロシアビジネスにおける留意事項は? 本講演は、対ロシア投資あるいは事業進出に現在または今後関与する実務家を対象に、専門家の視点から、ロシアビジネスの基礎知識から最新動向、今後の可能性に至るまでを解説するものである。 第一部として金野が、豊富な調査・研究実績に基づき、法制度や労働事情等を初めとする基礎知識と対ロシア投資の状況等の最新動向を紹介する。そのうえで、対ロシア投資のメリットについて解説する。 第二部では酒井が、ガス・石油・石油化学分野を中心に長年にわたりロシアにおける実務に携わってきた立場から、期待される、あるいは注目される分野に関して産業分析の視点に基づき解説し、さらに、実務経験を踏まえてロシアビジネスにおける注意事項等について述べる。 |
| 開催日時 | 2006-11-01(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ケイマン諸島を利用したオフショア・ストラクチャーの最新動向 |
| 講師 | メープルズ・アンド・コールダー法律事務所 矢澤 豊 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-11-01(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | バイアウトファンドの戦略的活用と意義 バイアウトファンド運営の実際と最新動向、個別ケースにおける取組みの実態を交えて |
| 講師 | アドバンテッジパートナーズLLP パートナー 永露 英郎 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | バイアウトについては国内でも多くの実績が生まれ、定着した感があるが、その運営の実態について明らかにされる機会は少ない。 本講演では、バイアウトファンド市場の黎明期から数多くの案件に携わってきた講師の豊富な経験に基づき、その全体像を踏まえた最新の動向をとりあげる。 まず、バイアウトファンドの運営ストラクチャー等の基本的な仕組みを解説したうえで、その本質的な価値を理解する上で押さえておくべきポイントについて実務プロセスの各段階別に整理する。さらに、大きな注目を集めているポッカコーポレーションを初めとする主要なバイアウト事例を紹介し、具体的な取組みの実態について可能な限り言及しつつ、ファンドが企業の大株主になることの必然性、ならびに企業の価値向上に与えるインパクトについて検討する。 |
| 開催日時 | 2006-10-31(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 外国籍公募・私募投信の最新法務 ~金融商品取引法対応も含めて~ |
| 講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 田中 収 弁護士 杉 容子 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-10-31(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 上場会社100%子会社化の実務 これからのキャッシュスクイーズアウトや株対価TOBの手法を用いたM&A |
| 講師 | 西村ときわ法律事務所 野田 昌毅 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 上場会社の100%子会社化といっても、金銭を対価として交付するキャッシュスクイーズアウトもあれば、株式を対価として交付する100%子会社化もあり、ある会社を100%子会社化するための手法は多種多様である。 本講演では、会社法及び金融商品取引法の施行を踏まえて、上場会社を100%子会社化していく上で主として検討される手法のそれぞれについて、法的観点からの問題点及び留意点について解説する。 |
| 開催日時 | 2006-10-30(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 日本版SOX法・内部統制における構築・運用・文書化実務の実践 |
| 講師 | 株式会社Biz コンサルティング 代表取締役社長 佐々野 未知 公認会計士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-10-30(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険商品の販売勧誘に関する新しいルール |
| 講師 | 中央大学法科大学院 教授 森・濱田松本法律事務所 客員弁護士 野村 修也 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-10-30(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 信託受益権販売業の実務と法的諸問題 信託に関する基礎知識から証券化・資産流動化に関連する法的論点と実務対応、最新動向まで |
| 講師 | 東京青山・青木法律事務所 谷笹 孝史 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成16年に改正・施行された信託業法により、信託受益権の販売につき新たに信託受益権販売業の登録が必要となった。この新たな規制により、実務上頻繁に行われている信託を利用した証券化・流動化取引その他の不動産取引の実務は大きな影響を受けており、また、これまで金融法に基づく規制とは関係が薄かった業態の会社も含め、信託受益権販売業の登録者は450を超えるに至っている(平成18年6月10日現在)。 信託受益権販売業を営む際には、「信託」という法制度や関係法令、信託業・信託受益権販売業等につき適用される規制などの知識が不可欠であるが、「信託」という制度自体が特殊なものであり、また適用される法律も多岐にわたり内容も複雑であることから、正確な知識の習得は必ずしも容易ではない。また、監督指針10-2-1の解釈を始めとして、証券化・流動化取引の実務上検討が必要な法的論点がいくつかある。さらに、平成18年3月13日に国会に提出された信託法案及び同日に国会に提出され同年6月7日に成立した金融商品取引法の来夏における施行が予定されており、これらの法律が、信託受益権の売買実務にさらなる大きな影響を与えることが予想される。 本講演では、まず、「信託」という特殊な法制度について概説し、その後、信託関係法令の概要及び信託業・信託受益権販売業につき適用される規制の内容について解説を行う。また、証券化・流動化取引において問題となる法的論点と実務対応について解説する。さらに、信託法案及び金融商品取引法に関する最新の動向についても、信託受益権販売業の実務に与える今後の影響という点にポイントを絞って検討する。 |
| 開催日時 | 2006-10-27(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融規制の基礎概念と規制対応 最新動向を交えて |
| 講師 | KFi 株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | わが国金融機関においては各業法や政省令のほか、監督指針、事務ガイドライン、検査マニュアルなど、数多くの実質的規制が存在する。しかし、これらの規制体系などについて十分に理解されていないのが実情であろう。 本講演は、金融規制の基本概念や監督・検査の枠組みを改めて体系的に習得し、より適切な管理態勢の整備、規制対応に資することを目的として解説を加えるものである。 |
| 開催日時 | 2006-10-26(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 携帯電話金融ビジネスのインパクト |
| 講師 | 経営企画研究所 代表 丹羽 哲夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-10-25(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 新BIS規制と信用格付システムの今後の方向 |
| 講師 | アクセンチュア株式会社 金融サービス本部 プリンシパル 市瀬 国興 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-10-25(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 日本における事業の証券化 仕組みの類型化及びポイントの解説と問題点の検討 |
| 講師 | シティユーワ法律事務所 パートナー 後藤 出 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 英国を中心に行なわれてきた「事業の証券化(Whole Business Securitization)」の日本における実現可能性が話題になり始めて数年が経過した。その間に、徐々にではあるが案件が集積し、日本における事業の証券化の仕組みがようやく形をあらわしつつある。 いまや、事業の証券化は、英国との対比で日本における可能な仕組みを模索する段階から、日本において実施された仕組みの分析、検討を踏まえ、よりニーズに即した仕組みを考案していく段階に至ったといえよう。とはいえ、事業の証券化は、対象となる事業の特性に応じてオーダーメイドの仕組みで行なわれるためその仕組みは多様であり、また今までのところ公表事例は多くないことから、既存案件の分析は必ずしも容易ではない。 本講演は、そのような制約の中で、できるかぎりわかりやすく仕組みを類型化し、内在する問題点に検討を加えることを試みるものである。 |
| 開催日時 | 2006-10-24(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品を巡る会計の最近の動向と実務上の対応 |
| 講師 | 新日本監査法人 金融部 パートナー 公認会計士 茂木 哲也 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成18年3月30日に企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第12号「その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理」が公表され、平成18年4月27日には、日本公認会計士協会から「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)、「金融商品会計に関するQ&A」、「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」(会計制度委員会報告第4号)の改正が行なわれた。 これらの動きは、会社法による諸制度の変更や、金融商品を巡る最近の懸案事項等への対応を図るものであり、その内容について的確に把握しておく必要がある。 本講演では、金融商品に関する会計上の取扱いを中心に、最近の会計制度の動向を幅広くまとめ、併せて実務上の対応についての要検討事項をまとめていく。 |
| 開催日時 | 2006-10-19(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関のマーケティングの現状と今後の方向性 心理訴求による顧客獲得、事例を交えて |
| 講師 | 株式会社アサツーディ・ケイ 第6コミュニケーションプランニング局 ルーム長 橋本 之克 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | この10年間で日本における金融機関の広告費は2倍以上に増え、全体で3000億円を越えた。業界別広告費を比較すると金融は、食品、情報通信、自動車などの業界を上回り、化粧品トイレタリーに次ぐ2位の規模である。 これは、金融業界において一般顧客を獲得するための投資が活発に行なわれていること、言い換えれば、顧客獲得の競争が激化の一途をたどっていることの表れである。この競争を勝ち抜くためのヒントを求めて、ほぼ全ての金融機関がさまざまな形でマーケティング戦略やブランド戦略を策定し、実施している。 しかしながら従来からのマーケティングやブランドの手法は、消費財を中心に発達してきた。従って金融という独特の商品においてそのまま適用できるとは限らない。あまり認識されていないことであるが、金融のマーケティング戦略やブランド戦略においては、表面に現れにくく把握しづらい「金融(お金)に対する人間の心理」を把握することが重要である。中でも、不安、恥など「負の感情」をコントロールすることが戦略を成功に導くカギとなる。この認識が不足しているがゆえに、戦略を誤る例は巷にあふれている。 本講演では、金融商品特有の顧客意識、これを把握するための手法、さらに戦略構築に反映させるための方法などを、さまざまなデータや事例をもとに紹介する。 |
| 開催日時 | 2006-10-18(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | モバイルでの小額決済の現状と展開の方向性 |
| 講師 | 株式会社野村総合研究所 情報・通信コンサルティング二部 上級コンサルタント 森本 伊知郎 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 携帯電話に非接触ICカードFeliCaが搭載され、モバイルによる決済領域が注目を集めるようになった。特に小額決済を対象とした電子マネーの利用は、首都圏を中心として着実に伸びている。更に、モバイルでのクレジットカード実装も進み、モバイルでの決済が当たり前に扱われる時代の到来を予見させる。 一方で、電子マネーやモバイルクレジットを導入した小売店、加盟店は、ともすると導入効果が得られず、一部では撤退する動きも見え始めている。これは、決済というプラットフォームビジネスの導入に対しての考え方と、事業が呈するギャップに起因するものと考えられる。 本講演では、おサイフケータイの現状と動向を紹介するのに加え、おサイフケータイで実現されているサービス(現状では、決済や交通をはじめとした6つのカテゴリー。今後のフェーバ2による新たなサービス)の分析と事業組み立てへの鍵となることは何か、プラットフォームビジネスとは何者だったのかを事例を引用しながら紹介する。 |
| 開催日時 | 2006-10-17(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | M&A・組織再編における人事・労務の法的諸問題と留意点 |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー 髙谷 知佐子 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 人の集合体である企業のM&Aあるいは組織再編の成否の鍵を握るのは、M&A前後の人事・労務政策にある。いかにM&Aのプランがすばらしくても、M&A後に人がついていかなければ、そのM&Aは失敗したと評価されてしまう。 本講演では、M&Aのシナジー効果を最大にし、従業員のモチベーションを高く保つためには何をすべきか、また何をすべきではないか、M&Aにあたって人事制度を変更する場合の限界はどこにあるか、M&Aを実施する前に検討しておくべき人事・労務上のポイントは何かにつき、実例を踏まえて検討していく。 また、本講演では、M&Aに伴い見直しが必要となることが多い年金制度に関連する問題についても言及する。 |
| 開催日時 | 2006-10-13(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ストラクチャード・クレジット商品の新潮流・投資戦略とリスク管理 規制環境の変化がもたらす影響を交えて |
| 講師 | モルガン・スタンレー証券株式会社 債券調査本部長 クレジット・ストラテジスト 大橋 英敏 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | クレジット商品(社債、ローン、クレジット・デリバティブズ、証券化商品など)の新潮流の中でも、ストラクチャード・クレジット商品(トランチド・インデックス商品、CDO/CLOなど)は最も高い注目を集めている。運用フロント担当者だけではなく、リスク管理、コンプライアンス、バックオフィス担当者にとっても、これらの商品を理解することは、今後の収益拡大とそれに伴う運用戦略の拡大のために必要不可欠であろう。 本講演は、ストラクチャード・クレジット商品を紹介すると同時に、これらの商品への典型的な投資戦略として欧米ヘッジファンドが活用する手法を紹介し、当該商品に投資する金融機関・投資家が留意すべき点(リスク管理、コンプライアンス)を解説するものである。さらに、規制環境の変化として、新BIS規制等とそのインパクトについて併せて解説する。 |
| 開催日時 | 2006-10-12(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 会社法制定に伴う平成18年税制改正が組織再編成・M&Aにもたらす影響 種類株式、のれん、DESの取り扱いなど |
| 講師 | 税理士法人トーマツ シニアマネジャー 税理士 橋本 純 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成18年度の税制改正は、会社法の制定に伴う改正が多く行われた。特に組織再編成、M&Aに関する税務については、大きな影響が見られたところである。 本講演では、平成18年度税制改正のうち、組織再編成、M&Aに関連して、資本の部に影響を与える項目のうち、主に自己株式とのれんの取り扱いについて解説する。さらに、今後ますます多くの会社が導入をすると思われる種類株式の取り扱いに影響を与える改正についても言及する。また、従来、事業再生の場面において、債務免除益問題の対応として行われてきたデットエクイティスワップ(DES)の取り扱いも変更が加えられており、実務上影響があると思われる点についても触れる。 |
| 開催日時 | 2006-10-11(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 投資ファンドの活用と金融商品取引法・開示義務 |
| 講師 | 三井法律事務所 パートナー 猪木 俊宏 弁護士 三井法律事務所 熊谷 真喜 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 近年、様々な投資案件において各種の投資ファンドが用いられており、投資ファンドは投資を行うために不可欠の存在となっている。他方、投資ファンドの多様化、利用の拡大に伴い、各種法改正が行われており、投資ファンドをめぐる規制環境は大きく変化してきている。また、金融商品取引法が成立し、来年には同法の施行により再びファンドをめぐる規制環境が大きく変化することになる。組合型のファンドへの新規参入については、適格機関投資家等特例業務の範囲によっては想像以上に困難になる可能性も指摘されはじめている。 本講演では、実務的な観点から、各種の投資ファンドの活用方法を検討するとともに、投資ファンドに関する開示義務その他の規制の状況を整理し、金融商品取引法が投資ファンドをめぐる実務に与える影響について検討・解説する。 |
| 開催日時 | 2006-10-10(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 国際分散投資における為替管理戦略 |
| 講師 | ワトソンワイアット株式会社 コンサルタント 岡田 章昌 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-10-06(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | リテール金融マーケティング |
| 講師 | 株式会社マーケティング・エクセレンス マネージング・ディレクター 戸谷 圭子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-10-05(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法と私募ファンドの実務 |
| 講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 伊藤 哲哉 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-10-05(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 中国新会社法によって変わる中国現地法人のコーポレートガバナンス 新会社法施行後の実務を踏まえて、エクイティファイナンス、資本規制や投資規制の柔軟化に関する解説を含む |
| 講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 北京事務所 首席代表 森脇 章 弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ニューヨーク州弁護士 中川 裕茂 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は、2006年1月1日に大きな改正が行われた中国の会社法が、如何に現地の日系企業のコーポレートガバナンスに与え、如何なる対処を要求しているかを、実務的な視点から具体的に解説するものである。 これまでに、中国現地法人は外商投資企業としての特別な待遇が与えられ、コーポレートガバナンス上も純粋中国系企業とは大きく異なる取扱がなされてきた。今後は、外商投資企業としての特別な取扱が廃止され、純粋中国系企業と同じようなガバナンスを求められる方向性にあり、現地法人は、これまで特別扱いの上に成り立ってきた組織機構や資本政策などを大きく変革する時期にある。 純粋中国系企業と同じようなガバナンスとは何か。がんじがらめの法規制上、あきらめられていた資本政策を柔軟に操るためのポイントは何か。 施行後約10ヶ月を経て、ようやく各種通達と運用実務に若干の落ち着きが見られ、先例も蓄積されつつある。本講演では、中国業務を中心に携わる実務家のみならず、中国拠点の再編など「てこ入れ」に現在または今後関与する事業戦略・経営企画部門等の実務家を対象に、実例などを踏まえ、理論のみならず、実務家の観点からの解説を分かりやすく行う予定である。 |
| 開催日時 | 2006-10-03(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | バーゼルⅡが投資商品に与える影響 |
| 講師 | 小笠原国際総合法律事務所 小笠原 耕司 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-10-03(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 匿名組合・合同会社・有限責任事業組合の仕組み・活用と税務・会計 会社法、金融商品取引法の影響に関する解説を含む |
| 講師 | 新日本監査法人 データバンク室 公認会計士 太田 達也 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 近年、組合などの事業体を活用した事業投資が活発に行われており、かつ、注目されている。不動産の流動化スキームでは、匿名組合方式が主流となっているほか、ベンチャー投資、レバレッジド・リース、投資ファンドなどに幅広く活用されている。 また、会社法では合同会社(LLC)という会社の内部関係が組合的規律であり、かつ出資者の責任が有限責任制である新しい会社類型が創設された。さらに、それとは別に、有限責任事業組合(LLP)が平成17年8月から施行されており、徐々に活用が進みつつある。 本セミナーでは、匿名組合、合同会社(LLC)および有限責任事業組合(LLP)の仕組みと税務および会計の取扱いを踏まえたうえで、実際の活用例などを織り込みながら解説する。 また、金融商品取引法の施行による影響についても取り上げる。 |
| 開催日時 | 2006-10-02(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 中国における外資系保険事業と日系企業の保険ブローカー事業進出に係る実務 |
| 講師 | ニッセイ基礎研究所 保険研究部門 主任研究員 中国室長 沙 銀華 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-09-29(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 郵政新会社の金融拡大戦略がもたらすインパクト |
| 講師 | 経営企画研究所 代表 丹羽 哲夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-09-28(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 投信・投資顧問会社向け監督・検査の最新動向と対応策 ~金融商品取引法対応を含めて~ |
| 講師 | KFi 株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-09-28(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法等の改正と今後のMBO実務 ゴーイング・プライベートを中心に |
| 講師 | 東京青山・青木法律事務所 ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所 外国法共同事業 パートナー ニューヨーク州弁護士 関口 智弘 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 今年のすかいらーく、昨年のポッカ、ワールドなどで注目される上場会社のMBO(ゴーイング・プライベート)だが、上場会社を対象とした企業買収のルールであるTOB(公開買付け)に関する証券取引法の規制は、金融商品取引法となってモデルチェンジすることが予定されている。 金融商品取引法は、本年6月7日に国会で承認可決され、TOBに関する新しい法規制は、年内の施行が予定されている。そこで、今後、上場会社のMBOを検討するうえで、新しいTOBルールを検討することは必要不可欠となる。 本講演では、上場会社のMBOを企画・検討する実務家のために、金融商品取引法による新しいTOBに関する法規制を解説するとともに、今後のMBO実務にどのような影響を及ぼすかについて分析を試みる。 さらには、本年5月に施行された会社法や平成18年税制改正がゴーイング・プライベートの実務にもたらしたインパクトや、MBOに特有の論点である対象会社の取締役の法的責任論(利益相反、善管注意義務)についても、分かりやすく説明する。 なお、実務動向、政省令の動向などの情勢の変化については、講演当日までの状況により必要に応じて言及する。 |
| 開催日時 | 2006-09-27(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | クレジット・デリバティブ市場の最新動向と活用手法 基礎知識から、事例、証券化との融合、活用上の論点まで |
| 講師 | メリルリンチ日本証券株式会社 法人顧客グループ ジャパン クレジット マーケティング ディレクター 矢島 剛 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | クレジット・デリバティブ市場は、90年代の誕生以来急激かつ継続的に成長している。基本的取引であるデフォルト・スワップの市場規模は、約17兆ドルと前期比38%の増加(2005年下半期、ISDA)。拡大の要因には、原資産市場としての社債、貸出債権の市場にデリバティブ取引がもたらした高い柔軟性と取引利便性等が挙げられる。 本講演では、クレジット・デリバティブ市場の最新動向を明らかにし、実務上必要とされる基礎的知識と多様な取引スキーム、リスク管理・分析等についてわかりやすく解説する。また、クレジット・デリバティブの活用上の論点を様々な角度から検討する。 さらに、高度な仕組みを有するストラクチャード・クレジット等、最新の商品についても具体的事例を基に説明を加える。証券化スキームを活用したCDO(債務担保証券)に関しては、仕組み、格付け、特徴等、詳細な解説を行う。 |
| 開催日時 | 2006-09-26(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 電子金融サービス法務の最新知識 |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 飯田 耕一郎 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-09-26(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関の内部統制強化のための取組み バーゼルⅡや法改正等を背景とする当局・規制対応と真に有効な内部統制構築のために、事例及びリスク管理・コンプライアンスモデルの解説を交えて |
| 講師 | PwCアドバイザリー株式会社 パートナー 原 誠一 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 新会社法、バーゼルⅡ、財務報告に係る内部統制の評価など、様々な法規制により、内部統制の構築が求められる一方で、相次ぐ不祥事とそれに伴う当局による行政処分が多発している。 そのような金融機関においては必ずしも、内部統制を実現する組織・体制が存在していないわけではなく、内部統制の目的達成上の主要機能であるリスク管理機能、コンプライアンス機能、内部監査機能は存在していたにも拘らず有効に機能していなかったことに問題が起因している例も多い。 本講演では、形式的、範囲が限定された規制対応目的のみならず、本来の意味での有効な内部統制の構築を実現する上での、金融機関における課題とあるべき対応について、「組織・体制」、「内部統制機能」、「実施」の3つの観点から、事例及びPwCの考えるリスク管理・コンプライアンスモデル(PwC GRCモデル)を交え解説する。 |
| 開催日時 | 2006-09-25(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険製販分離の進行と保険・共済の融合 |
| 講師 | インスプレス 代表 保険ジャーナリスト 石井 秀樹 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-09-22(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 日本版SOX法における内部監査の役割 先進的手法としてのCSAの解説を含む |
| 講師 | アイ・ビー・エム ビジネスコンサルティング サービス株式会社 マネージング・コンサルタント 近藤 利昭 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本年5月に施行された会社法、06年3月期以降金融機関において実質義務化された企業内容等の開示、財務諸表の適正性等に関する代表者確認書添付、6月法案が成立した金融商品取引法(投資サービス法)など"内部統制"システムの整備が喫緊の課題となっている。内部統制のひとつの構成要素に過ぎなかった"内部監査"は、いままで以上に重要な役割を担うこととなった。内部統制に対する聖域はもはや存在せず、日本版SOX法(J-SOX)では財務報告の信頼性を確保するために、内部監査部門の業務プロセスの有効性評価作業が重要な意味合いを持つ。 本講演では、まず内部統制の概念を改めて整理したうえで、内部統制に対する内部監査のアプローチを考察し、J-SOXにおける内部監査部門の役割、そして業務プロセスの有効性評価に応用できる自己評価活動(CSA)を幅広く解説する。 |
| 開催日時 | 2006-09-14(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 財務報告に係る内部統制の評価におけるIT内部統制の位置付けと対応のポイント COBITとIT統制目標の利用を含む |
| 講師 | 監査法人トーマツ エンタープライズリスクサービス部 社員 公認会計士 丸山 満彦 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 第164回通常国会において金融商品取引法が成立し、また、金融庁企業会計審議会内部統制部会から2005年12月に「財務報告に係る内部統制の評価及び監査のあり方について」(以下、「意見書」という。)が公表されたのに続き、実施基準が検討されるなど(2006年6月現在)、日本企業は財務報告に係る内部統制の評価と監査の制度への対応を迫られている。 意見書では「ITへの対応」が盛り込まれ、その重要性に注目が集まっているが、実務上の対応に関する指針は現在のところ明らかではない。 本講演は、いわゆるIT内部統制に対する的確な理解を図るとともに、今後の対応に向けた方向性を検討することを目的とするものである。第一に、財務報告に係る内部統制の内容について改めて整理したうえで、そのなかでのIT統制の位置付けを明らかにする。次いで、IT全般統制及びIT業務処理統制といったIT統制に纏わる概念や、その評価手順について解説する。併せて、IT内部統制の整備に向けた現時点における有力な手法として、ISACA(米国情報システムコントロール協会)によるCOBIT(Control Objectives for Information and related Technology)とIT統制目標(IT Control Objective for Sarbanes Oxley Act)の紹介を行う。 |
| 開催日時 | 2006-09-13(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法の資産流動化実務への影響 |
| 講師 | 西村ときわ法律事務所 有吉 尚哉 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成18年通常国会において、金融商品取引法が成立した。金融商品取引法は、金融制度の基本法である証券取引法を改組・拡大し、株式や社債といった伝統的な有価証券だけではなくそれ以外の金融商品も幅広く対象とすることで、金融商品の販売や資産の運用に関して横断的な投資者保護ルールを設けようとするものである。金融商品取引法の施行時期は来年の夏ころが見込まれているが、その施行後には資産流動化取引の実務に対しても大きな影響を与えることが予想される。 本講演では、金融商品取引法について概説を行うとともに、特に金融商品取引法が資産流動化取引の実務に対して及ぼすことが予想される影響について考察を行う。 |
| 開催日時 | 2006-09-11(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法とアセット・マネージメント |
| 講師 | 西村ときわ法律事務所 パートナー 伊東 啓 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-09-08(金) 13:30~16:00 |
|---|---|
| セミナー名 | 新BIS規制に対応した投資戦略 |
| 講師 | モルガン・スタンレー証券 債券調査本部長 クレジット・ストラテジスト 大橋 英敏 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-09-07(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 富裕層ラップ・マーケティング |
| 講師 | 株式会社野村総合研究所 システムデザインコンサルティング部 主任システムコンサルタント 河口 千代孝 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-09-07(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | グローバルな資金調達の手法と法的諸問題 シンジケート・ローン、プロジェクトファイナンス、証券化を中心に、英文契約書の作成方法や留意点を交えて |
| 講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 赤羽 貴 弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 出張 智己 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 世界には多くの法域が存在し、投資家保護のための金融規制はもとより、債権譲渡、担保、相殺等、重要な法分野で各国の取扱いは異なっている。国を跨いだ大規模な資金調達には大きな法的リスクが伴うため、契約書は膨大な量に及ぶ。国際金融は、その結果、非常に複雑で理解困難なもののように思える。 しかし、現実の法律実務は、すべて、契約法、担保法、倒産法の基本的な原理に従って動いており、一見複雑に思える取引も、簡単な基本概念に立ち戻って説明することが可能である。 本講演では、このような「簡単さ」を示すことを目的のひとつとしながら、典型的な資金調達方法のメカニズムを、具体的な事例に基づき解明する。また、国際的な資金調達に用いられる英文の契約書から重要な条項を抜粋し、その趣旨、目的、効果、及びその適用が争われた判例を解説するとともに、英文契約書の作成方法や留意点に言及する。 |
| 開催日時 | 2006-09-06(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | M&A契約の実務 |
| 講師 | 西村ときわ法律事務所 野田 昌毅 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 多くのM&A取引においては、まず取引を行なう可能性のある当事者同士で秘密保持契約を締結し、その後LOI/MOUを締結し、デューディリジェンスを経て最終契約の締結に至るというように、取引の様々な段階に応じて各種の契約を締結する必要がある。そして、これらの契約は、それぞれが全く別個の意義を有しているものであるため、契約ごとにそのポイントも大きく異なる。 本講演においては、M&A取引の各段階で締結される契約ごとに、なぜそのような契約を締結する必要があるのか、そしてそのような契約締結の必要性からそれぞれの契約にどのような内容を規定する必要があるのかを説明し、さらには具体的な条項の内容としてはどのような点がポイントになるのかを条項の具体例とともに解説する。この中では、M&A契約において従前から一般的に規定されていた条項のみならず、M&A契約中において最近規定されることが多くなってきている条項―例えば、契約の締結及び公表後であっても第三者から別個の提案が行われる事態を想定して契約中に規定されるようになってきているfiduciary out条項―についても解説する。また、M&A契約のポイントは、その取引形態が合併か株式譲渡なのか等、取引形態によって大きく異なってくるため、各取引形態ごとにポイントとなる事項についても言及する予定である。 |
| 開催日時 | 2006-09-05(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社向け監督システムと管理対応の急所 ~保険商品の販売・勧誘管理を含めて~ |
| 講師 | KFi 株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-09-04(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 銀行保険窓販全面解禁に向けた保険販売のパラダイム・シフト |
| 講師 | 株式会社オポチュニット 取締役営業部長 新村 純一 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-08-31(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法の実務対応 ~業規制、行為規制についての実務上の留意点~ |
| 講師 | TMI総合法律事務所 中西 健太郎 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-08-29(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法と不動産証券化の実務 |
| 講師 | 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 橋本 昌司 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-08-29(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 最近の法改正の動向と証券化ストラクチャー |
| 講師 | 三井住友銀行 アセットファイナンス営業部 上席推進役 藤瀬 裕司 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 証券化・流動化にかかわる法的環境は、大きく変動しつつある。昨年の通常国会において成立した会社法は、5月1日から施行されているが、これにより、合同会社の設立が可能になるとともに、有限会社法が廃止された。 また、今年の通常国会においては、証券化ストラクチャーに影響を及ぼす可能性がある一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と証券取引法等の一部を改正する法律が可決成立した。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律は、内閣官房行政改革推進事務局を中心に議論されてきた公益法人制度改革の一環として制定されたものである。同法が施行されると、倒産隔離手法として一般的に利用されている有限責任中間法人の設立・存続の根拠法である中間法人法は、廃止される。 一方、証券取引法等の一部を改正する法律は、投資性の強い金融商品を幅広く対象とする横断的な制度を整備することなどを目的とするものである。証券取引法の題名を「金融商品取引法」に改正するほか、集団投資スキームに関する包括的な定義規定を設ける、販売・勧誘、資産運用・助言及び資産管理を全て本来業務としたうえ業規制を整備する、プロか一般投資家かに応じて行為規制の適用を柔軟化する、などの規定を整備している。 本講演では、会社法、金融商品取引法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を中心に、必要に応じて信託法も含め、最近の法改正の概要と、これらの法改正が証券化ストラクチャーに及ぼす影響について、解説する。 |
| 開催日時 | 2006-08-28(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融業界のための“新富裕層”マーケティング ~ポピュリッチの構図と購買心理から見た金融機関の取るべき戦略~ |
| 講師 | 株式会社ネットマイニング・ジャパン 代表取締役社長 鶴岡 謙吾 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-08-24(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 信託受益権販売業の実務と法的諸問題 信託に関する基礎知識から証券化・資産流動化に関連する法的論点と実務対応、最新動向まで |
| 講師 | 東京青山・青木法律事務所 谷笹 孝史 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成16年に改正・施行された信託業法により、信託受益権の販売につき新たに信託受益権販売業の登録が必要となった。この新たな規制により、実務上頻繁に行われている信託を利用した証券化・流動化取引その他の不動産取引の実務は大きな影響を受けており、また、これまで金融法に基づく規制とは関係が薄かった業態の会社も含め、信託受益権販売業の登録者は450を超えるに至っている(平成18年6月10日現在)。 信託受益権販売業を営む際には、「信託」という法制度や関係法令、信託業・信託受益権販売業等につき適用される規制などの知識が不可欠であるが、「信託」という制度自体が特殊なものであり、また適用される法律も多岐にわたり内容も複雑であることから、正確な知識の習得は必ずしも容易ではない。また、監督指針10-2-1の解釈を始めとして、証券化・流動化取引の実務上検討が必要な法的論点がいくつかある。さらに、平成18年3月13日に国会に提出された信託法案及び同日に国会に提出され同年6月7日に成立した金融商品取引法の来夏における施行が予定されており、これらの法律が、信託受益権の売買実務にさらなる大きな影響を与えることが予想される。 本講演では、まず、「信託」という特殊な法制度について概説し、その後、信託関係法令の概要及び信託業・信託受益権販売業につき適用される規制の内容について解説を行う。また、証券化・流動化取引において問題となる法的論点と実務対応について解説する。さらに、信託法案及び金融商品取引法に関する最新の動向についても、信託受益権販売業の実務に与える今後の影響という点にポイントを絞って検討する。 |
| 開催日時 | 2006-08-23(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 企業買収の税務 ストラクチャー選択の有利・不利判定 |
| 講師 | 佐藤信祐事務所 所長 公認会計士 税理士 佐藤 信祐 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 企業買収が活発化しており、年々、増加傾向にある。 企業買収をどのように行うのが、税務上、有利なのかという検討は初期段階に行われることが多く、企業買収の成否に影響を与えることが多い。 また、企業買収の売り手サイドの株主は個人株主である場合と法人株主である場合とに分けられ、個人株主である場合の課税関係は所得税法により規定されており、法人株主である場合における課税関係は法人税法により規定されていることから、個人株主と法人株主の課税関係は大きく異なる。 そのため、本講演では、売り手の株主が個人株主である場合(オーナー企業を買収する場合)と法人株主である場合(他社の子会社を買収する場合)のそれぞれにおける企業買収のスキーム決定において税務上、どのような事項について検討する必要があるのかについて解説を行いたい。 |
| 開催日時 | 2006-08-10(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | リスクファイナンス戦略の基礎と具体的手法及び最新動向 三菱商事における実例を交えて |
| 講師 | 三菱商事株式会社 金融事業本部 金融企画ユニット シニアマネージャー 北出 公英 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 企業において「リスクマネジメント」の重要性が盛んに喧伝されている。これは最近の企業における内部統制強化と合致した動きであろう。しかし、財務的観点からのリスクマネジメントである「リスクファイナンス」においてはまだ戦略や体制が整備されていない企業が多く、保険を付保することがリスクマネジメントであると誤解してしまっているケースもある。 本講演では、財務的な観点から企業のリスクをどう考えるかを明確に整理し、そのリスクを効率的に処理する手段を提示する。そしてリスクファイナンス強化によっていかに企業価値を高めるかを解説するものである。また、三菱商事のリスクファイナンス戦略とその具体的な取組手法を紹介し実務的な解説を加える。さらに、最新リスクファイナンス動向と今後の方向性を紹介するとともに、リスクファイナンスにおけるこれからの注目すべき分野として「保険と金融の融合」をとりあげ、キャタストロフィー・ボンドをはじめとした保険リスク証券化の考え方や今後の可能性についても言及する。 |
| 開催日時 | 2006-08-08(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | チューリッヒ保険の成長戦略 |
| 講師 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー 日本における代表者 最高経営責任者 小関 誠 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-08-07(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法が金融商品の組成・販売に与える影響 |
| 講師 | 小笠原国際総合法律事務所 小笠原 耕司 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-08-04(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 外国籍私募投信の最新動向と実務対応 ~金融商品取引法への対応も含めて~ |
| 講師 | 三井法律事務所 パートナー 猪木 俊宏 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-08-03(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険専業チャネルは生き残れるか!? ~銀行・郵便局窓販戦略と生保営業職員・損保中核代理店の強化策~ |
| 講師 | 保険評論家・保険アナリスト 山野井 良民 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-08-02(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関におけるモバイルペイメント戦略 |
| 講師 | 株式会社日本総合研究所 調査部 金融ビジネス調査グループ 主任研究員 野村 敦子 氏 研究員 藤山 光雄 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-08-02(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険会社のコンプライアンスの論点と体制整備 「総合的な監督指針」ほか規制環境の変化も踏まえて |
| 講師 | KFi株式会社 代表取締役 青木 茂幸 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 最近の行政処分事例に見られるように、保険会社を巡る規制環境が大きく変化している。 本講演では、改正された総合的な監督指針の内容を踏まえ、保険会社のコンプライアンス体制の整備について実務的・実践的な解説を行う。 |
| 開催日時 | 2006-08-01(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関における日本版SOX法対応 |
| 講師 | 佐藤経営法律事務所 佐藤 孝幸 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-08-01(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 国際財務報告基準の重要性と今後の影響 2009年までに海外子会社の対応を含む日本企業の対応はどうあるべきか |
| 講師 | あずさ監査法人 IFRS本部 副本部長 KPMGパートナー 代表社員 公認会計士 金子 寛人 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は、会計基準の統一化に向けた世界の動向や日本と欧米における取組みの差などをわかりやすく解説し、国際財務報告基準(IFRS)の重要性と実務への影響について論ずるものである。 IFRSの影響は、確実に日本企業に浸透しつつある。 第一に欧州資本市場における資金調達、すなわち2007年問題であり、第二に会計基準のコンバージェンスに伴う海外子会社のIFRS基準の強制採用である。第三にヨーロッパとアメリカにおける財務諸表の相互承認である。 本講演では先ず、このような世界的な趨勢のなかで高まりつつあるIFRSの重要性について論ずる。 次に、わが国の企業会計基準委員会(ASBJ)が2006年1月31日に発表した「日本基準と国際会計基準とのコンバージェンスへの取組みについて」、また、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)が2006年2月27日に発表した「IFRSとUSGAAPの収斂に向けたロードマップ(覚書)」の解説を行い、統一化に向けたそれぞれの取組みを明らかにする。 最後に、現状、日本企業において会計基準の問題点を整理し、現時点におけるIFRS基準及び米国基準との差異を明確化した上で、今後、日本の会計基準がどう収斂化していくのか、日本企業がどう対応すべきかについて検討する。 |
| 開催日時 | 2006-07-31(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険のクロスセルと代理店・営業職員の再構築 |
| 講師 | 経営企画研究所 代表 丹羽 哲夫 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-07-27(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 保険コンプライアンスの新しい展開 |
| 講師 | 緒方法律事務所 緒方 延泰 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-07-26(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | バーゼルⅡがストラクチャード商品に与える影響 |
| 講師 | KFi 株式会社 代表取締役社長 齊藤 治彦 氏 エグゼクティブ・コンサルタント 三沢 信敬 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-07-26(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 中国における改正会社法とM&A 中国の改正会社法の重要なポイントとM&Aへの影響を具体例により解説 |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー ニューヨーク州弁護士 江口 拓哉 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 2006年1月1日に中国の会社法が13年ぶりの大改正を行った。主要な改正の趣旨はコーポレートガバナンスの強化にある。そこで、中国に子会社を保有する外国企業にも、いくつか重要な影響があるので、これについて概説する。 次に、既存の工場設備や販売網を取得するために中国企業の買収を検討する日本企業は少なくない。そこで、本講演においては、中国にて実際に行われているM&Aの典型的なケースをいくつか示し、各ケースの具体的手続及び問題点を解説する。その際に、上記中国の会社法改正により影響がある点についても言及する。 最後に、中国においては、外国企業による投資が制限されている業種(ICP会社が典型)がまだ残っている。このような業種を営む中国企業に対する投資方法について、NASDAQ上場例を参考にしながら、具体的に解説する。 |
| 開催日時 | 2006-07-25(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 食ビジネスを巡る最新動向と今後のポイント ケーススタディを交えて |
| 講師 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 コンサルティング本部 クリエイティブマネジメントコンサルタント 郷 好文 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演は、投融資先あるいは取引先として食品業界に関連する業務のほか、食品関連企業の事業再生などに携わる実務家を含め、現在または今後、食品ビジネスに関与する実務家を対象として、最新動向を紹介するとともに、今後の食品事業に対する評価あるいは再生などにおけるポイントについて解説するものである。 第一に、食を巡る政治・経済、食品業界の最近の動向について、食料輸入、FTA、トレーサビリティ、チェーン・マネジメント、業界再編、スローな高齢化社会、食場のボーダーレス化、LOHASなどのトピックについてポイント解説を行う。 次いで、今後のキーワードとして「サバイバル」、「インターネット」、「偽装」を切り口に、事例を紹介しつつ、食品事業に対する評価あるいは再生等に向けたヒントを提示する。 |
| 開催日時 | 2006-07-21(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 「事業信託」を巡る法的論点の検討 信託法改正、信託業法改正がもたらす可能性と課題 |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 水野 大 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成18年3月13日、改正信託法案および信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案が第164回通常国会に提出された。大正11年に制定されて以来、80年以上にわたって実質改正がなされてこなかった信託法を、時代の変化に対応させ、より使いやすい合理的なルールにしようとする改正がついに実現しようとしている。 改正信託法の下では、信託宣言(自己信託)、限定責任信託、受益証券発行信託等の新しい形態の信託が導入され、また、セキュリティ・トラストの有効性が明確になったこと等によって、「信託」の利用範囲・利用方法がますます拡大されていくであろう。そのような「信託」の利用範囲・利用方法の拡大の一場面として、負債を含めた事業全体を信託財産とする事業信託が存在し、この未知なる事業信託に対して実務は注目の眼差しを向けているように思われる。 もっとも、事業信託は従来存在しなかったものであるが故に、それに含まれる法的論点の抽出・検討は十分に尽くされているとはいえない。 そこで、本講演では、事業信託の利用が見込まれている典型事例を踏まえて、事業信託についてどのような法規制・法的論点が存在し、どのような論点が未解決事項、要検討事項として残っているのかを解説する。もちろん、改正信託法、改正信託業法(兼営法)は重要な問題であるが、会社法、金融商品取引法、労働法等その他の法令との関係でも検討すべき点は存在することから、可能な限り言及する。 |
| 開催日時 | 2006-07-20(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 電子債権法の法制化に向けた現状解説 実務への影響 |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 原 武之 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | いわゆる「電子債権法」を巡っては、経済産業省及び金融庁のワーキンググループ等における検討を経て、法務省において私法上の論点整理が行われた後、現在、法制審議会電子債権法部会での議論が行われている。 立法に向けたスケジュールを含め、具体的な姿は現段階では明らかではないが、「電子債権」という現在の売掛金(指名債権)や手形債権とは別のあたらしい類型の債権が認められることから、売掛債権の流動化や融資、信託、リース業務などにおける実務への多大な影響が予想される。 本講演では電子債権に関して、その意義、これまでの検討経緯、現状の議論の動向について、報告書や議事録等の公表資料の分析、研究に基づき解説を行うものである。将来的な可能性、今後の課題などについては、可能な限り具体的に検討する。 |
| 開催日時 | 2006-07-19(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法における法的諸問題と実務上の留意点 業規制と行為規制を中心に、立法作業経験者の視点から |
| 講師 | TMI総合法律事務所 中西 健太郎 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 金融商品取引法(いわゆる投資サービス法)が今通常国会において成立し、デリバティブ取引の範囲を拡大するとともに、有価証券概念を集団投資スキーム持分などを含める形に拡大した上で、既存の証券業のほか、金融先物取引業、商品投資販売業、信託受益権販売業、投資顧問業、投資信託委託業、投資法人資産運用業、ファンド型投資運用業などを1つの登録制度下に置くなど、従来型の縦割り型の制度を横断化するとともに、参入規制を業務の内容により段階化、行為規制についてもプロ・アマの区別により柔軟化する、銀行法、保険業法及び不動産特定共同事業法などへ行為規制を準用するなどの大々的な改正を伴う画期的な法制となっている。 本講演は、立法作業に深く携わった講師による講演を通じ、金融商品取引法のうち特に業規制及び行為規制について、改めて、その全体像、具体的内容を確認して、今後の金融商品取引業のあり方、金融ビジネスの進め方についての理解を深めることを目的とするとともに、実務上の留意点や今後の見通しについても、可能な限り解説するものである。 なお、国会審議や法案成立の過程における重要な変更等については、講演当日の最新の状況に応じて解説する予定である。 |
| 開催日時 | 2006-07-14(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | バーゼルⅡにおける信用リスクアセット計測方法に関する解説 |
| 講師 | 中央青山監査法人 金融部 レギュラトリーアドバイザリーザービス ディレクター 西原 弘道 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-07-14(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 不動産流動化・証券化の要点整理、実務上の留意事項、法改正等の最新動向 |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 勝山 輝一 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本年4月以降だけでも2つの信託銀行が金融庁から極めて重い行政処分を受けていることからも明らかな通り、不動産流動化・証券化に携わる実務家にとって、不動産流動化・証券化に関連する法的規制の十分な理解が必須となっている。 もっとも、不動産流動化・証券化には多数の法律が適用されるため、不動産流動化・証券化に関連する法的規制を理解することは容易ではない。更に、本年5月1日に会社法が施行され、不動産流動化・証券化の実務に多大な影響を与えたことは記憶に新しいが、今後も信託法の改正、金融商品取引法の施行等、不動産流動化・証券化の実務に極めて大きい影響を与える法改正等が控えており、法的規制に関する理解のアップデイトを常に行う必要がある。 本講演は、証券化に携わっている実務家、これから関与する実務家、さらには、コンプライアンス、財務、審査等の各部門において証券化の知識を必要とする実務家を対象とするものである。実務の最前線に立つ講師の経験も踏まえて、実務に必須となる知識を基本からわかりやすく解説するとともに、実務上の問題点及び留意点の具体的解説、さらには、法改正動向を初めとする最新動向の紹介を行う。 第一に、証券化の目的と基本スキームを改めて概説し、SPC、真正売買、倒産隔離といった証券化に必須となる概念の整理を行う。また、不動産特定共同事業法、投資信託法や資産流動化法についても扱う。 次いで、借入人、貸付人、受託者といった各プレイヤーにとっての実務上の留意点について、コンプライアンスからの観点も踏まえて、契約書におけるポイント等も交えて詳説する。 さらに、会社法、金融商品取引法、信託法改正などの動向を紹介するとともに、不動産流動化・証券化実務にもたらすインパクトについて検討する。 講義においては、必要に応じてドキュメンテーションのサンプルや図解に基づく解説のほか、文献等の情報源の紹介を行い、不動産流動化・証券化における要点の整理と実務への活用を図るものである。 |
| 開催日時 | 2006-07-13(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 医療法改正がもたらすインパクト 社会医療法人制度創設により官から民へ、新たな事業機会に関する具体的考察 |
| 講師 | 東日本監査法人 会計士補 長 英一郎 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成18年2月10日に通常国会に医療法改正案が提出された。改正案は5月10日現在、国会で審議中であるが、社会医療法人制度は平成19年4月1日に施行される見込みである。社会医療法人制度創設の趣旨は、自治体病院をはじめとした公的医療機関がこれまで担ってきた救急医療、へき地医療等の救急医療等確保事業を社会医療法人が担うことにある。社会医療法人認定により収益業務の実施や社会医療法人債の発行等が可能になるが、やはり認定による最大のメリットは全国に約1,000ある自治体病院の受け皿になりうることではないだろうか。 自治体病院に替わり社会医療法人がその役割を担う可能性、すなわち「官から民へ」の劇的な変化は、経営立直しのための老朽化した医療機械の更新、土地・建物等の買収資金などの新たな需要、あるいは自治体病院の病床削減に対応する他病院の増床や新規参入といった機会が生じることなどで、民間企業や金融機関に対しても大きなインパクトをもたらすことが予想される。 本講演では、医療法改正の概要を基礎に、社会医療法人、特定医療法人の実践的活用法に加え、医療法改正が金融機関を含む民間企業等へ及ぼす影響に関し、資金調達手段の多様化の可能性などを含めて解説する。 なお、改正案に関する国会審議や法案の成立等に伴う最新動向については、講演当日までの状況を踏まえ、必要に応じて言及する予定である。 |
| 開催日時 | 2006-07-12(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 新会社法施行後のM&A取引のポイント ストラクチャリングへの影響を中心に |
| 講師 | 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 藤原 総一郎 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本講演では、新会社法の施行により組織再編等に関する規制がどのように変わったのかを、法務省令等も踏まえた上で、実際にM&A取引のストラクチャを検討するにあたってどのような影響があるのかという視点から整理する。 また、新会社法に限らず、M&A取引のストラクチャ検討に影響を与えうる近時の又は近い将来予想される立法等の動向を概観し、実務上の留意点に言及する。 |
| 開催日時 | 2006-07-10(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 外国籍私募投信の法的諸問題 ~金融商品取引法への対応を含めて~ |
| 講師 | 東京青山・青木法律事務所 パートナー 小野 雄作 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-07-05(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ケイマン・ファンドの設立・ストラクチャリングにおける最近の傾向と法律事務 |
| 講師 | メープルズ・アンド・コールダー法律事務所 矢澤 豊 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-07-04(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 個人年金市場の構造変化とマーケティング戦略 |
| 講師 | ハートフォード生命保険 代表取締役 セールス・マーケティング統括本部長 砂川 和彦 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-07-04(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 物流業を巡る最新動向及び今後の評価と生き残りのポイント 基本知識から戦略的事業展開の事例、今後の課題まで |
| 講師 | 株式会社日通総合研究所 経営コンサルティング部長 山田 健 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | いま物流業が大きく変わろうとしている。海外生産シフトやロジスティクスの進展など荷主を取り巻く環境の変化と、規制緩和による競争の激化により、受注産業といわれていた物流業にはより戦略的な事業展開が求められてきているのである。 本講演は、物流業を取引先または投融資先とする実務家のほか、物流業に関与する実務家を対象に、物流に関する基本 知識から最新動向、さらには物流業の生き残り戦略や評価のポイントについて、講師の豊富なコンサルティング実績も踏まえて解説するものである。 まず、そもそも物流とは何かから始まり、マクロから見たわが国の物流、物流を大きく変えるロジスティクスとSCMの概要 など、業界を取り巻く環境変化を事例を交えて解説する。そして、これらの環境変化を踏まえ、これから物流業が生き残っていくために必要な戦略について、物流業の業態に大きな変化をもたらすものとして最近話題の3PL(Third Party Logistics)の課題を 中心に紹介する。 |
| 開催日時 | 2006-07-03(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 運用ビジネスの革新と金融機関のテクノロジー戦略 |
| 講師 | 株式会社インタートレード 業務執行役員 ビジネス推進部長 阿久津 智巳 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-06-30(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関のブランド戦略と女性マーケティング |
| 講師 | 株式会社博報堂 ブランドソリューションマーケティングセンター ビジネス推進部長 岩崎 拓 氏 コンサルタント 牛田 奈緒子 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-06-30(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 事業の証券化 具体的手法及び法的論点と事例分析 |
| 講師 | 森・濱田松本法律事務所 パートナー 武川 丈士 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 証券化の新たなアセットクラスとして「事業の証券化(Whole Business Securitization)」が注目されている。しかし、何をもって事業の証券化と定義するのか、また、どのような手法が日本法上可能であるか、その限界はどこにあるのかといった点について、必ずしもコンセンサスがあるとは言えない。 本講演では、多義的な概念である事業の証券化の手法について、一定の分類を試みるとともに、会社法の施行・改正信託法の内容といった法改正も踏まえつつ、日本における事業の証券化について法的な観点から分析・提案を行う。そのうえで、これまでに事業の証券化(又はそれに類似するもの)として公表されている事例について、公表資料に基づき上記分類を意識した分析を加える。 |
| 開催日時 | 2006-06-29(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | JCBにおけるブランドイメージ戦略と取組事例について |
| 講師 | 株式会社ジェーシービー マーケティング本部 チャネル統括部 チャネル企画グループマネージャー 相川 剛俊 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-06-29(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 情報家電と放送・通信・広告メディア産業の最新動向と展望 海外の先進的事例、新たなビジネスチャンスの示唆を交えて |
| 講師 | 株式会社野村総合研究所 情報・通信コンサルティング二部 主任コンサルタント 廣戸 健一郎 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 2003年から2004年に到来したデジタル家電ブームも一段落し、薄型テレビ以外の家電の売上は頭打ちになりつつある。 一方で、デジタル家電の普及により、消費者の映像・音楽コンテンツ視聴スタイルに大きな変化が生じつつある。iPodの登場による音楽保有形態の変化や、CD販売からダウンロード販売へのシフト、録画番組をPSPなどポータブル機器へのコンテンツエクスポートすることによるすき間時間でのコンテンツ視聴増加など、従来とは異なる視聴文化が生まれつつある。更に、総務省で地上デジタル放送のIP同時再送信が議論されるなど、デジタル家電をインフラとした新しいサービスや事業形態が次々に生まれてくると期待されている。その一方で、著作権法や、コンテンツの取引慣行など、新しいサービス展開の制約条件になる幾つかの前提もある。 本講演では、業界の最新動向を整理し、米国などでの先進的サービスなどを紹介しつつ、今後の家電、通信業、放送業、広告業、ネット事業を跨いだ今後の動向について予測する。 |
| 開催日時 | 2006-06-28(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関の排出権取引の可能性 現行の規制法上の問題点、最新の法改正及び契約書実務などの問題点も交えて |
| 講師 | 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 田場 洋史 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 本年2月10に京都メカニズムによる削減量の取得、保有及び移転の記録を行うための割当量口座簿の整備、クレジット取引の安全の確保等について定める「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が国会に提出され、国内排出権取引の制度整備が進行している。もっとも、いかに排出権取引の制度整備が進もうと、プレーヤーが現実に参加しない限り国家プロジェクトとして排出権取引を導入する意義は達成されない。そして、国家プロジェクトとしての排出権取引が成功を収めるためには、仲介機能を果たす金融機関の参加は不可欠であるといえる。ところが、現在までのところ、日本の金融機関は、規制業法上の解釈の問題ゆえに、ほぼ身動きを取れないでいる。 本講演では、諸外国の規制法上の位置づけや、排出権取引に係るリスクの検討を踏まえ、金融機関が排出権取引を行うことができるかを探る。また、金融商品取引法など、金融機関に関係する最新の法改正における問題やOTC取引の契約書作成実務など金融機関の法律実務的な問題にも言及したい。 |
| 開催日時 | 2006-06-27(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 日本版SOX法を睨んだ内部統制構築の実務 日米の制度動向、フレームワーク、具体的構築手順の解説 |
| 講師 | A.T.カーニー株式会社 マネージャー 松元 貴志 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | わが国では、2005年12月に金融庁企業会計審議会により「財務報告に係る内部統制の評価と監査の基準案」が公表された。これがいわゆる「日本版SOX法」であり、2006年の法制化、2007年の施行、2008年3月期からの適用を目指し、検討が進んでいる。 2002年に成立した企業改革法(SOX法)への対応を迫られてきた米国企業と、まったく同じ状況に今の日本企業は置かれており、内部統制に対する取り組みは他人事ではなく、具体的な取り組みを始める時期にさしかかっている。 本講演では、内部統制に関する制度の動向、内部統制フレームワークの概要を紹介するだけでなく、講師の豊富な コンサルティング実績も踏まえて、内部統制の仕組みを具体的に構築する手順について解説する。特に、内部統制構築の第一歩として重要な「内部統制の現状評価」について、具体的なワークシートを示して、その進め方を実践的に解説する。 |
| 開催日時 | 2006-06-26(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法における匿名組合ファンドの実務 |
| 講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 伊藤 哲哉 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 |
| 開催日時 | 2006-06-22(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 貸金業のコンプライアンスを巡る現状及び展望と態勢整備の具体的対応策 法改正などの環境変化を念頭に、事例や「評価」フレームワークの提示を交えて |
| 講師 | 専修大学客員教授 新日本インテグリティアシュアランス株式会社 執行役員 ファイナンスカンパニー事業部 プレジデント 経済産業省から出向 石川 和男 氏 新日本インテグリティアシュアランス株式会社 取締役 横田 祐次 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 次期貸金業制度改革として、2006年中にも出資法・貸金業規制法の改正が見込まれるなか、過払金返還請求等に関する判決が相次ぐなど、貸金業を取り巻く環境は激変している。また、会社法施行による内部統制システム構築の義務化が目前に迫り、さらには、2008年にも適用が予想される日本版SOX法(金融商品取引法)への対応も今後の重要な課題となる。 貸金業の将来に多大な影響を及ぼすことが予想される出資法・貸金業規制法改正の方向性は現時点で不透明であるが、貸金業が劇的な環境変化のなかにあるという認識に立った場合、優良な事業者の今後の生き残りと業界の健全な発展のために、コンプライアンス態勢の整備は緊急の課題のひとつであるといえる。また、資金需要者からの信頼感、ひいては国民世論全体から「適格な」事業者としての社会的評価を獲得するためには、万全な態勢整備を行うことに加え、何らかの客観的な評価基準や評価ポイントを確立する必要もあると考えられる。 本講演は、消費者金融会社、信販会社などにおいて企画、コンプライアンス、内部監査等に携わる実務家のほか、貸金業を含む金融ビジネスに関与する実務家を対象に、コンプライアンスの側面を中心に貸金業の現状と課題、今後の展望とともに、課題の解決策を提示するものである。 横田が豊富なコンサルティング実績に基づき、コンプライアンス態勢の構築に関し、フレームワークや評価のポイントについて事例等を交えた具体的な解説を行う。 また、経済産業省から民間出向中の石川が、出資法・貸金業規制法なども含めた法制定・改正状況も交えて、主としてコンプライアンスの観点から貸金業を巡る現状の動向と今後の展望について解説する。 |
| 開催日時 | 2006-06-21(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融商品取引法案と開示の方向性及び実務への影響 投資事業組合を巡る最新の議論等を含めて |
| 講師 | 新日本監査法人 金融部 社員 公認会計士 橋上 徹 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 2006年3月10日、「金融商品取引法案」が閣議決定され、3月13日衆議院に提出された後、4月20日現在審議中である。この法案は、従来の「証券取引法」による証券規制に替えて、昨今の集団投資スキーム(ファンド)に代表される金融商品の多様化・複雑化に対応し、「金融商品取引法」として規制を統合しようとするものである。この法案は今通常国会で成立し、2007年度から(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から)適用される見通しである。 本講演は、金融商品取引法施行により、特に開示の内容がどのように変わるのか、ファンド運営等の実務においてどのような影響が生じるのかを解説するものである。また、最近の情勢の変化を受けて急速に関心が高まっている、「投資事業組合」に対する会計処理の実務対応報告等の議論について概要を紹介する。さらには。信託法、会社法との関係、留意事項についても言及する。 |
| 開催日時 | 2006-06-20(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ホテル事業投資案件の近時動向と評価ポイント |
| 講師 | 株式会社KPMG FAS 取締役 パートナー 吉岡 雅博 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 地価の二極分化が鮮明となり、都市部の地価上昇を引っ張る商業用不動産投資のブームは留まることを知らず、バブルか否かの議論も喧しい。そうした投資・ファイナンス対象は、近時、ホテル不動産といった「ハコモノ」に広がっており、「買得感投資」から「戦略投資」に移行している。また、このホテル不動産・事業投資ブームは金融機関による積極的な融資姿勢や機関投資家によるファンド運用が支え、言わば、「金融商品化」の流れを汲んでおり、ホテル版J-REITの出現もあいまって新たなステージに足を踏み入れつつあると考えられる。 一方で、ホテル事業投資案件はオフィス、住宅、商業施設といったその他不動産投資案件と多くの違いを有しており、事業のストラクチャー、案件リスク、評価手法の理解とそれらを踏まえた取組み姿勢の構築が重要であり、バブル期における海外ホテル事業投資案件で踏んだ轍を繰り返してはならない。 本講演では、日米のホテル、リゾート関連案件のアドバイザリー、評価関連業務に携わってきた講師より、ホテル事業投資案件のマーケットの現況と背景、こうした案件における評価手法と留意事項について解説を行うものである。また、今後のマーケットを占うべく米国ホテル投資・ファイナンスマーケットの動向に触れつつ、国内ホテル事業投資案件の成長の鍵や将来展望についても言及する。 |
| 開催日時 | 2006-06-16(金) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 携帯と金融の融合 モバイルペイメントの動向と各社の戦略、国内外の事例を交えて |
| 講師 | 株式会社日本総合研究所 調査部 金融ビジネス調査グループ 主任研究員 野村 敦子 氏 株式会社日本総合研究所 調査部 金融ビジネス調査グループ 研究員 藤山 光雄 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | わが国の携帯電話加入者数は、2005年12月末時点で9千万を超え、固定電話を凌ぐ規模に成長している。現在、携帯電話は第二世代から第三世代への移行が進められているところであり、第三世代の携帯電話利用者の割合は全体の5割に達する勢いである。 この携帯電話の端末に、電子マネーやクレジットカード、交通カード、ポイントカードなど様々な機能を搭載させる動きが本格化している。クレジットカード会社や金融機関は携帯電話端末に決済機能を搭載することで、製品やサービスの購入にクレジットカード等が利用される機会を拡大しようとの狙いである。携帯電話事業者は、従来の音声通信中心のままでは、加入者の増加による市場の成長が見込めないことから、加入者の獲得・囲い込みならびに新たな収益源確保のために、モバイルペイメントに取り組んでいる。一方、ユーザーにとっては、常に持ち歩いている携帯電話端末にクレジットカードや交通カードなど様々な機能が搭載されることで、複数のカードを持ち歩いたり、小銭を持つ必要がなくなるなど、利便性が高まる。 本講演では、携帯電話事業者や金融機関、端末メーカーなどさまざまなプレーヤーにより、国内外で取り組みが進むモバイルペイメントについて、その動向と普及に向けた課題について海外の事例を交えて解説するとともに、各社の戦略を紹介する。 |
| 開催日時 | 2006-06-15(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関の次世代IT戦略 事例に基づく新たな施策の解説を中心に |
| 講師 | ITマネジメント・コンサルタント 田沢 務 氏 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | ITに対する理解が困難であるという声は、金融機関の経営トップを初め、役員、部門長以下の層にも根強い。ITは 今や金融ビジネスのライフラインであり、金融機関の投資額全体に占めるIT投資の割合は極めて高いものの、現状では何が理解できて、何が理解できないのかが、正しく理解されていないのが実態ではないだろうか。 他方、業績拡大、ローコストオペレーション、制度対応といった課題が山積するなか、金融機関経営はITを抜きにして考えられない状況にある。こうした状況下にあって、旧態依然のシステム開発・運用やスクラッチ開発などからのパラダイム転換を図っていく必要があろう。 本講演では、日米の金融業界に精通した講師の豊富なコンサルティング実績に基づき、金融機関の経営者や企画 担当、システム企画担当のほか、金融機関のITに関与する実務家を対象に、今後の経営課題に対応するための次世代 IT戦略を示すものである。具体的な対応策として、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、オフショア開発、共同化などの幾つかの施策について、事例も交えて解説を行う。 |
| 開催日時 | 2006-06-12(月) 13:30~16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 信託受益権販売業の実務と法的諸問題 信託に関する基礎知識から証券化・資産流動化に関連する法的論点と実務対応、最新動向まで |
| 講師 | 東京青山・青木法律事務所 谷笹 孝史 弁護士 |
| 開催地 | |
| 参加費 | |
| 概要 | 平成16年に改正・施行された信託業法により、信託受益権の販売につき新たに信託受益権販売業の登録が必要となった。この新たな規制により、実務上頻繁に行われている信託を利用した証券化・流動化取引その他の不動産取引の実務は大きな影響を受けており、また、これまで金融法に基づく規制とは関係が薄かった業態の会社も含め、信託受益権販売業の登録者は400を超えるに至っている(平成18年4月10日現在)。 信託受益権販売業を営む際には、「信託」という法制度や関係法令、信託業・信託受益権販売業等につき適用される規制などの知識が不可欠だが、「信託」という制度自体が特殊なものであり、また適用される法律も多岐にわたり内容も複雑であることから、正確な知識の習得は必ずしも容易ではない。また、監督指針10-2-1の解釈を始めとして、証券化・流動化取引の実務上検討が必要な法的論点がいくつかある。さらに、平成18年3月13日に信託法案及び金融商品取引法案(投資サービス法)が国会に提出され、来夏にも施行が予定されるこれらの法律が、信託受益権の売買実務にさらなる大きな影響を与えることが予想される。 本講演では、まず、「信託」という特殊な法制度について概説し、その後、信託関係法令の概要及び信託業・信託受益権販売業につき適用される規制の内容について解説を行う。また、証券化・流動化取引において問題となる法的論点と実務対応について解説する。さらに、信託法案及び金融商品取引法案に関する最新の動向についても、信託受益権販売業の実務に与える今後の影響という点にポイントを絞って検討する。 |
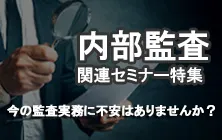
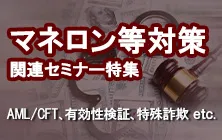
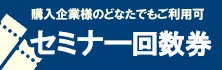
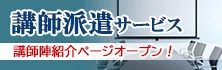
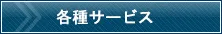
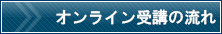

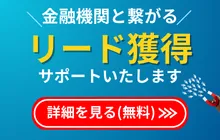
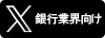


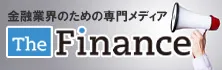
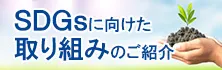
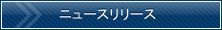
- 2025/12/17オフィス・カンファレンスルーム移転のお知らせ
- 2025/8/1創立20周年記念特設Webサイトオープン
- 2025/7/15株式会社グッドウェイとの業務提携について
- 2025/5/22申込規約改定のお知らせ
- 2025/3/19動画メディア「Finlink」オープン
- 2025/2/25動画メディア「PLACEY」オープン
- 2024/10/2「生成AIコース」開始
- 2024/7/12個人情報保護方針・Cookieポリシー改定のお知らせ
- 2024/4/23「(一社)金融データ活用推進協会」および「特定非営利活動法人金融IT協会」への加入のお知らせ
- 2024/4/3「LISTEN」に代表取締役社長小西のインタビューが掲載されました
- 2023/6/29セミナー累積開催数が5,000回を突破
- 2021/12/20「あしたのチーム HRアワード2021 優秀賞」を受賞
- 2021/9/1Webメディア「TheFinance」リニューアル
- 2021/8/6アクチュアリー試験対策講座の販売に関するお知らせ
- 2021/7/30受講票・請求書・領収証の送付方法変更のお知らせ
- 2021/5/13「講師派遣サービス」開始
- 2021/4/22 更新新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組み
- 2021/4/14「リバイバル配信セミナー」開始
© 1999-2026 Seminar Info Co.,Ltd. All rights reserved.