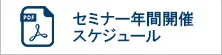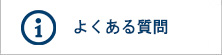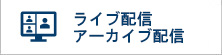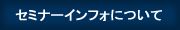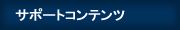|
|
 |
セミナー情報
SEMINAR INFORMATION
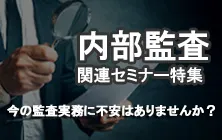
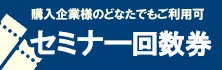
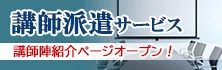
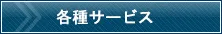
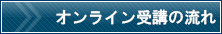

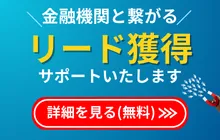
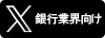




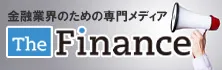
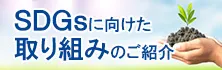
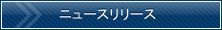
- 2025/8/1創立20周年記念特設Webサイトオープン
- 2025/7/15株式会社グッドウェイとの業務提携について
- 2025/5/22申込規約改定のお知らせ
- 2025/3/19動画メディア「Finlink」オープン
- 2025/2/25動画メディア「PLACEY」オープン
- 2024/10/2「生成AIコース」開始
- 2024/7/12個人情報保護方針・Cookieポリシー改定のお知らせ
- 2024/4/23「(一社)金融データ活用推進協会」および「特定非営利活動法人金融IT協会」への加入のお知らせ
- 2024/4/3「LISTEN」に代表取締役社長小西のインタビューが掲載されました
- 2023/6/29セミナー累積開催数が5,000回を突破
- 2021/12/20「あしたのチーム HRアワード2021 優秀賞」を受賞
- 2021/9/1Webメディア「TheFinance」リニューアル
- 2021/8/6アクチュアリー試験対策講座の販売に関するお知らせ
- 2021/7/30受講票・請求書・領収証の送付方法変更のお知らせ
- 2021/5/13「講師派遣サービス」開始
- 2021/4/22 更新新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組み
- 2021/4/14「リバイバル配信セミナー」開始
© 1999-2025 Seminar Info Co.,Ltd. All rights reserved.